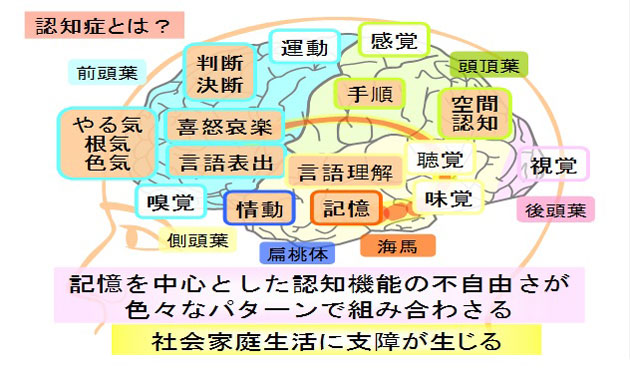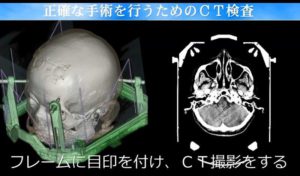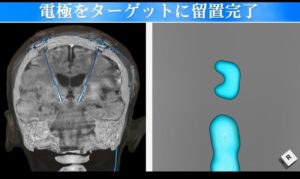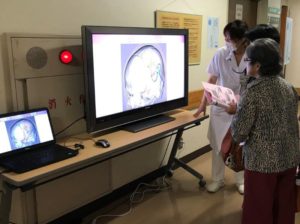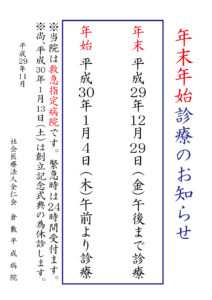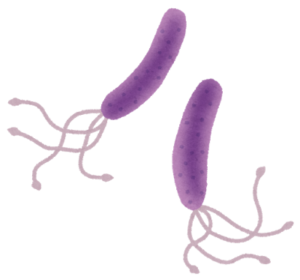11月に入り今年も残りわずかになりました。
最近では、朝晩だけでなく日中の気温も低くなってきました。
体調を崩されないように気をつけて下さい。
11月といえば、そろそろ紅葉のシーズンになります。
県北では、奥津渓が見頃を迎えて、渓流沿いの木々が赤や黄色と綺麗に色づいています。
私は、この時期になると京都へ出かけ紅葉を楽しむようにしています。
もともと京都は好きなのですが、この時期は特に好きです。
オススメは、龍安寺の石庭を眺めながらの紅葉、高台寺で夜間ライトアップをされた紅葉が池に映るのはとても綺麗です。その他にもいろいろありますが、きりがないのでこの辺で・・・
インフルエンザが流行する時期になっていますが、みなさんは、予防接種はお済みですか?
私たち、ショートの職員は全員済みました。
それでも毎年、数名はインフルエンザにかかり休んでしまうスタッフがいます。
外出の際には、マスクの着用、外出から帰ってきたら、手洗いうがいを行い、さいしんの注意を払って、元気に利用者の方々のケアをしたいと思います。
ケアセンタショーステイ T.H