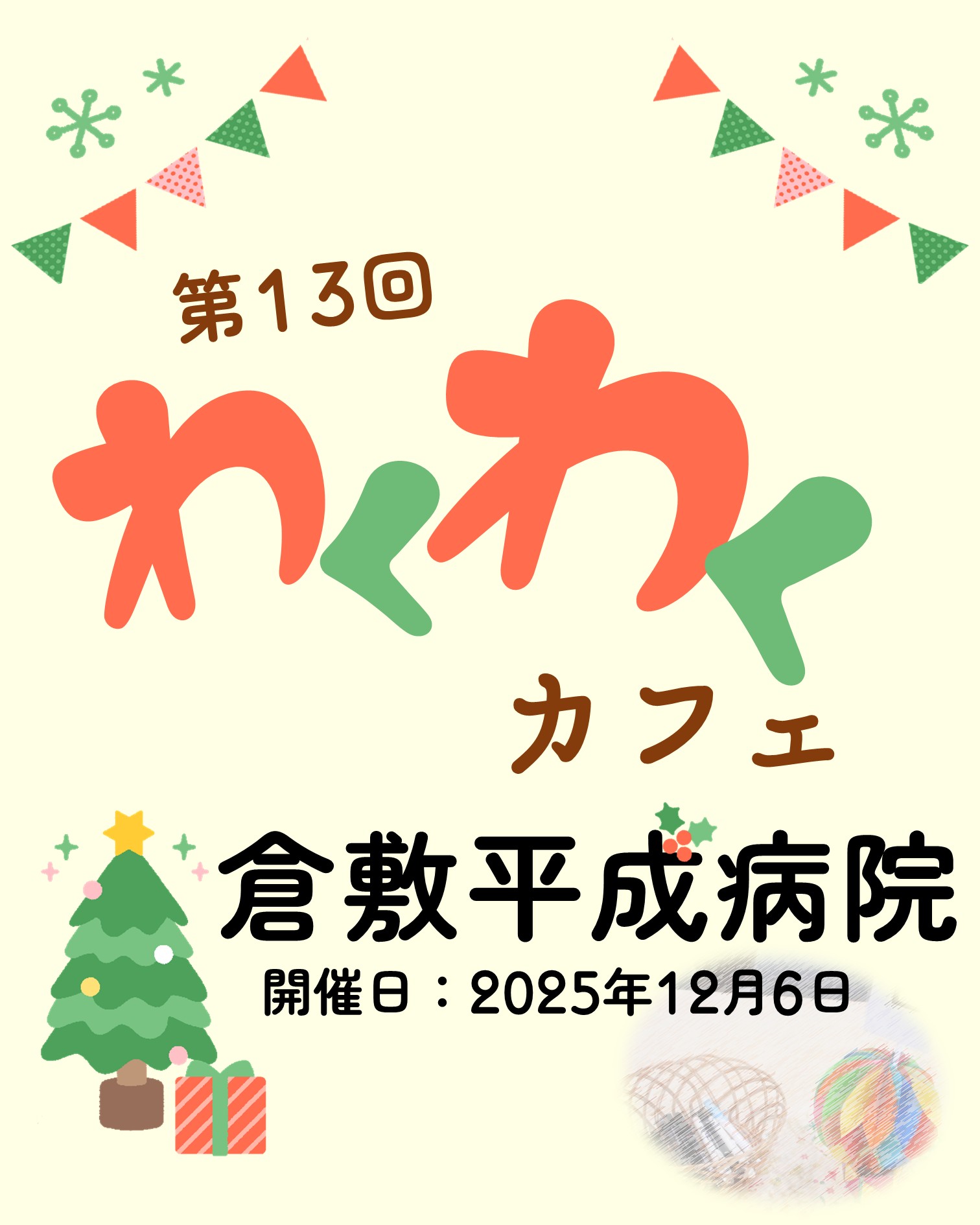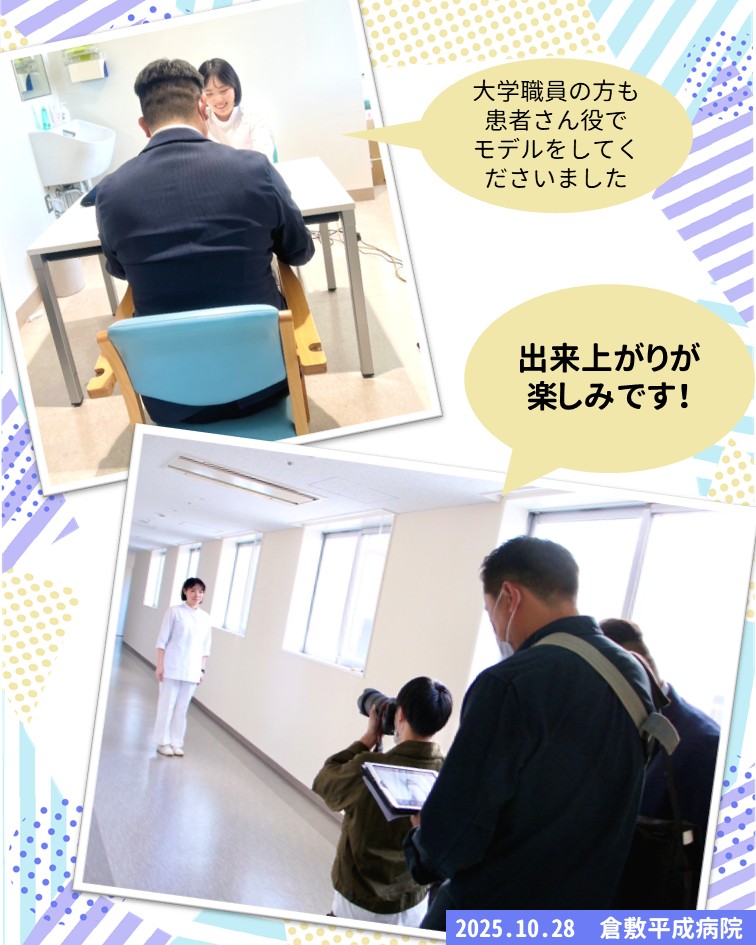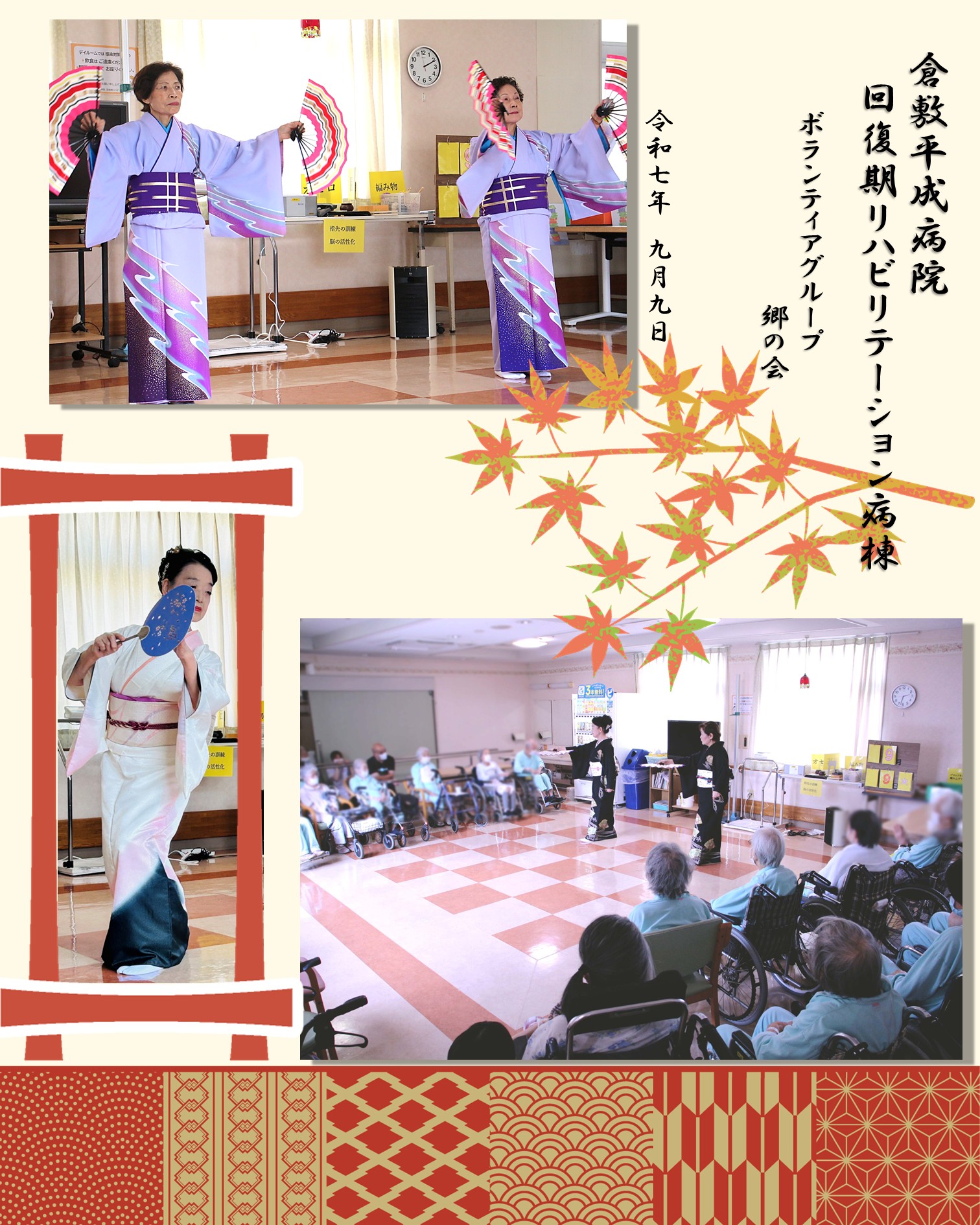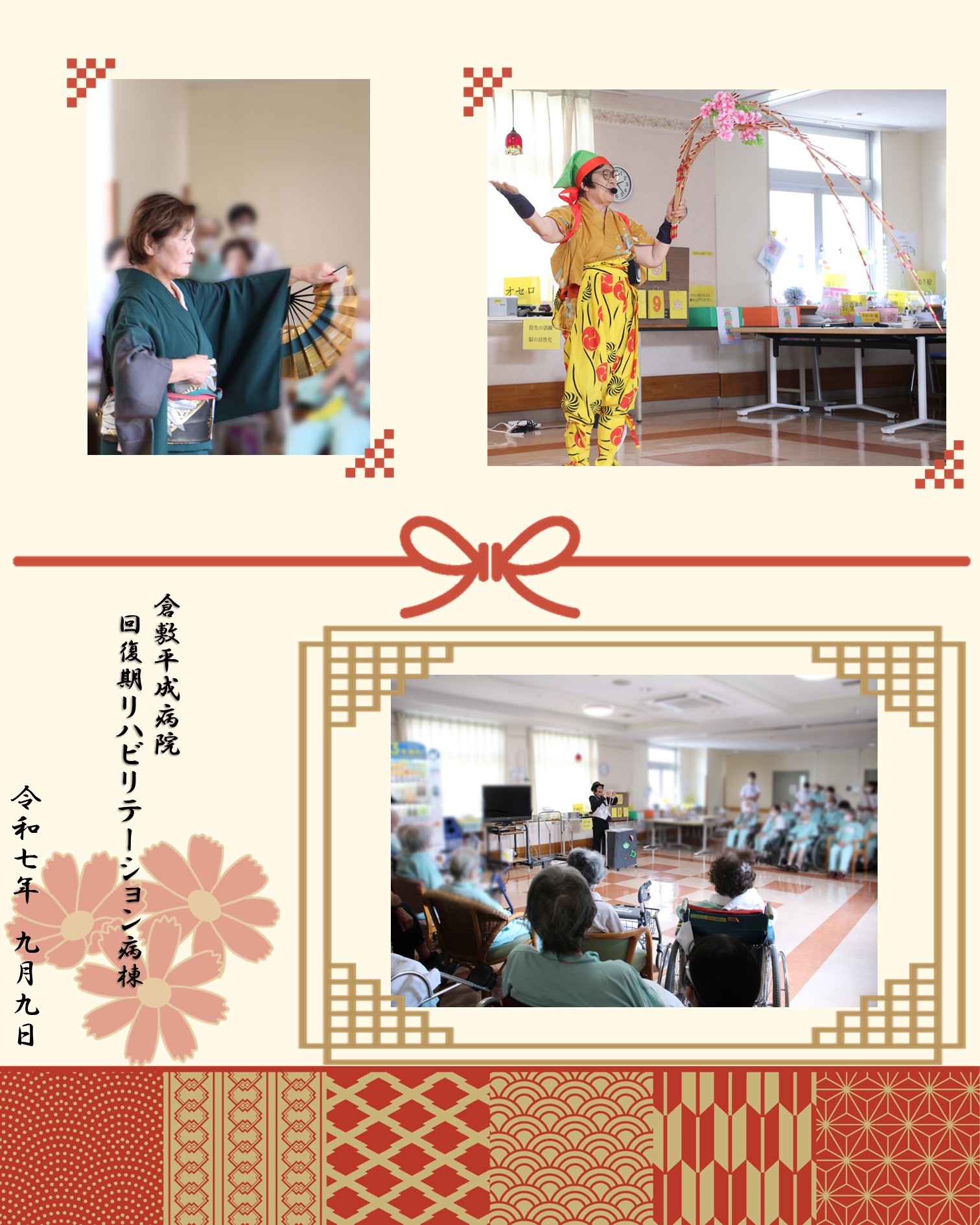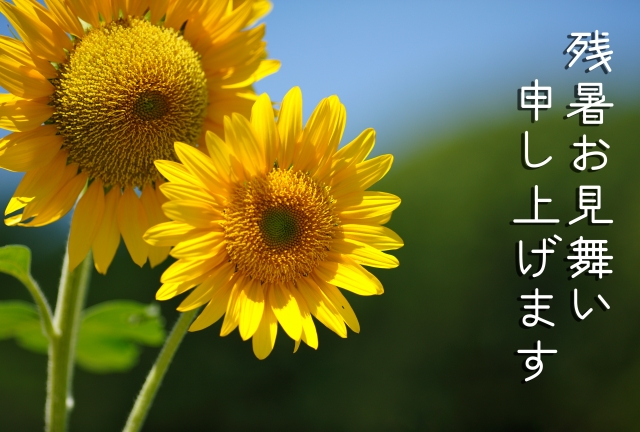こんにちは、公認心理師Oです。
新しい年を迎え、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて、私の職業である公認心理師とは、2017年に日本で初めて誕生した心理職の国家資格です。保健医療・福祉・教育などの分野において、心理学に関する専門的な知識や技術を用いて支援を行う心理支援の専門家として活躍しています。
心理系の資格はこの公認心理師のほかにも、さまざまな種類があります。
今回は、その中でも歴史のある「臨床心理士」という資格と、私が秋に受験した臨床心理士試験についてお話ししたいと思います。
皆さまは「臨床心理士」という資格をご存じでしょうか。
臨床心理士とは、「人にかかわり、人に影響を与える心の専門家」です。一人ひとりが持つ考え方や感じ方の多様性を尊重し、その人らしい自己実現を支援することを大切にしています。この資格は数ある心理系の資格の中でも歴史が長く、免許番号第一号が誕生したのは昭和63年(1988年)です。長年にわたり、医療・教育・福祉・司法など、様々な領域で心理支援を担ってきました。
臨床心理士になるための試験は、一次試験(筆記試験)と二次試験(口述面接試験)の二段階で行われます。
一次試験では、マークシート形式の知識問題に加え、決められたテーマについて論述する問題が出題されます。この一次試験に合格すると、二次試験である口述面接試験を受験することが出来ます。口述面接試験では、知識だけでなく、これまでの経験や心理支援に対する考え方、専門家としての姿勢などが問われます。
無事に一次試験を突破し、二次試験への準備を通して、これまで自分が学んできたことや心理士としての姿勢、支援の中で大切にしていることについて、改めて振り返ることが出来ました。また、病院の中で心理士が果たす役割や、患者さまとの関わりについても深く考える時間となり、試験対策にとどまらない、とても良い機会になりました。この振り返りは、今後も皆さまの支援に携わっていくうえで、とても大切なものになると感じています。
入職して間もなく1年を迎えますが、これからも学び続ける姿勢を忘れず、皆さまによりよい支援を届けられるよう、日々努めていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

リハビリテーション部 公認心理師 O