このたび、10月より薬剤師と薬剤補助の制服を一新しました。
近年、病院で働く薬剤師の数が減少傾向にあります。
そこで「病院薬剤師の魅力をもっと知ってもらいたい!」という思いから、制服を新しくすることにしました。
制服変更の背景
薬剤師といえば「白衣」を着て「薬局内で調剤をする」というイメージが強いかもしれません。
しかし、病院の薬剤師は薬局の中だけでなく、病棟を回って患者さんのお薬の管理や服薬指導なども行っています。
そのため、「薬局の中にいる薬剤師」から「病棟で活躍する薬剤師」へと、より現場に寄り添う新しいイメージに変えていきたいと考えました。
色へのこだわり
新しい制服の色を決める際には、薬剤部のスタッフみんなで意見を出し合いました。
こだわったポイントは次の3つです。
①薬剤師が一目でわかること
白衣を着ている職種は多く、これまで患者さんが「誰に薬のことを聞けばいいの?」と迷われることもありました。
新しい制服は、薬剤師がすぐにわかるような色にしています。
②ジェンダーレスなデザイン
薬剤部は女性スタッフが多いですが、男性薬剤師も働いています。
どんな人にも似合う、落ち着いた中にも優しさのある色合いを選びました。
③他職種との区別
他の病院では紺色の制服を採用しているところも多いのですが、当院では他職種とかぶらない色を選びました。
また、薬剤補助の制服も薬剤師とは違う色にしていただき、患者さんが混乱されないよう工夫しています。
新しい制服をきっかけに、より親しみやすく、頼れる薬剤師を目指してまいります。
薬剤部




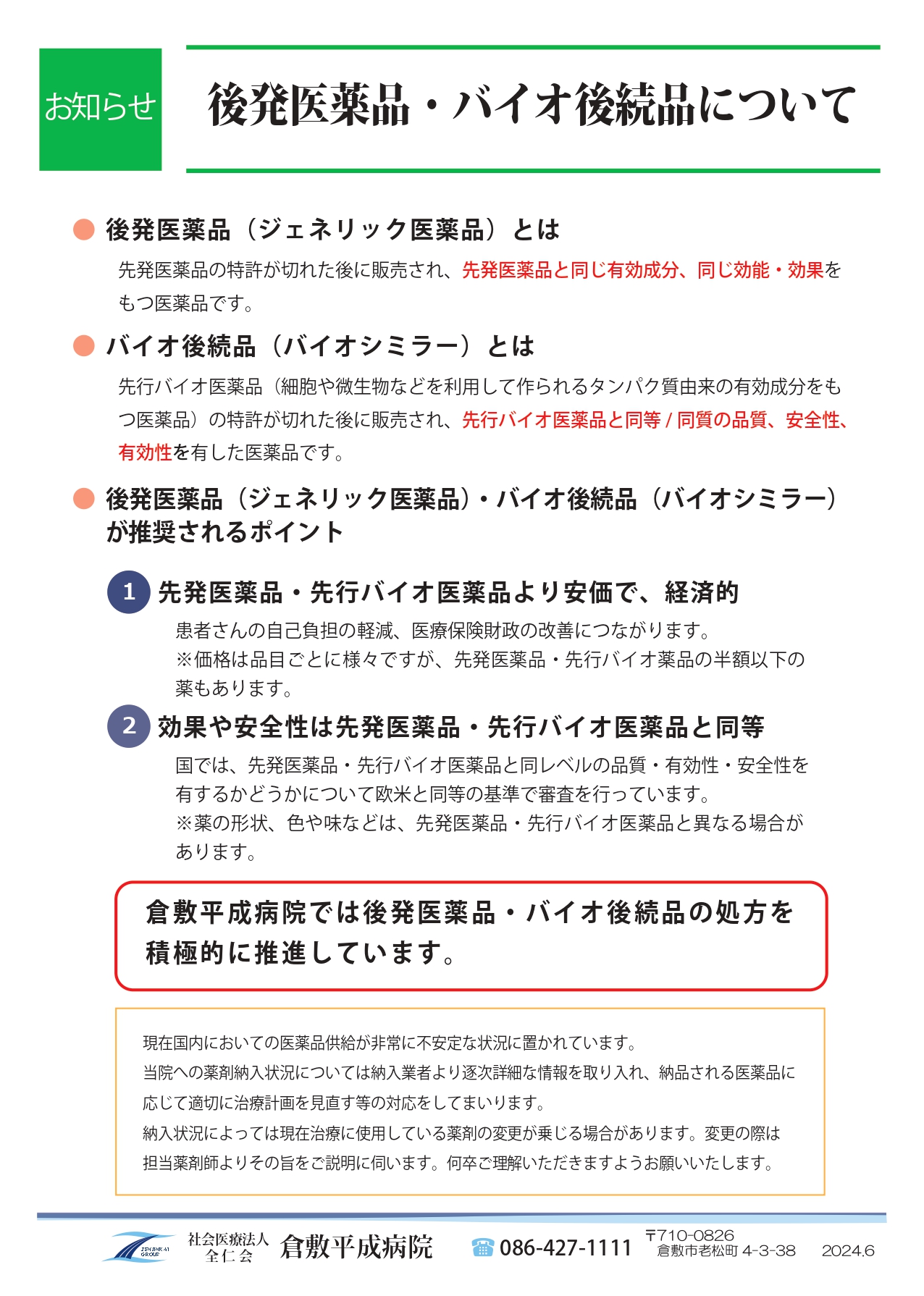
 ところで、薬を何で飲んでいますか?薬を口の中でボリボリ噛んで服用しているということをたまに耳にします。一般的な薬は水に溶けることで吸収が良くなり効果を発揮します。
ところで、薬を何で飲んでいますか?薬を口の中でボリボリ噛んで服用しているということをたまに耳にします。一般的な薬は水に溶けることで吸収が良くなり効果を発揮します。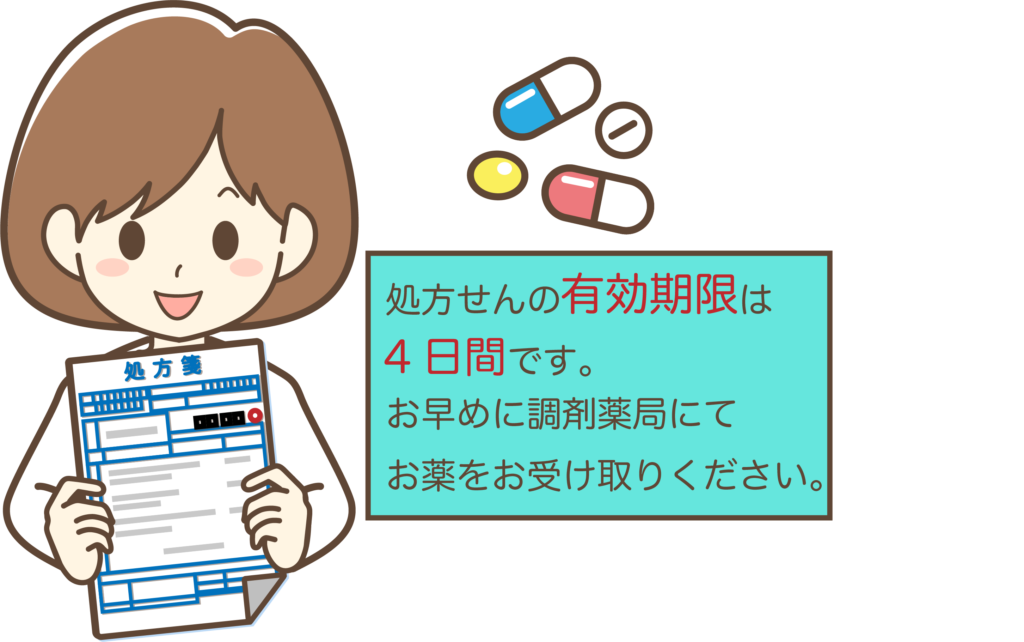
 花粉が原因で起こる肌荒れを、「花粉皮膚炎」といいます。冬の乾燥でバリア機能が弱った肌に、花粉が忍び込むことで発症します。マスクやティッシュの繊維が肌を摩擦し、肌のうるおいバリア機能をさらに低下させてしまうこともあります。
花粉が原因で起こる肌荒れを、「花粉皮膚炎」といいます。冬の乾燥でバリア機能が弱った肌に、花粉が忍び込むことで発症します。マスクやティッシュの繊維が肌を摩擦し、肌のうるおいバリア機能をさらに低下させてしまうこともあります。 薬剤部 いっちー
薬剤部 いっちー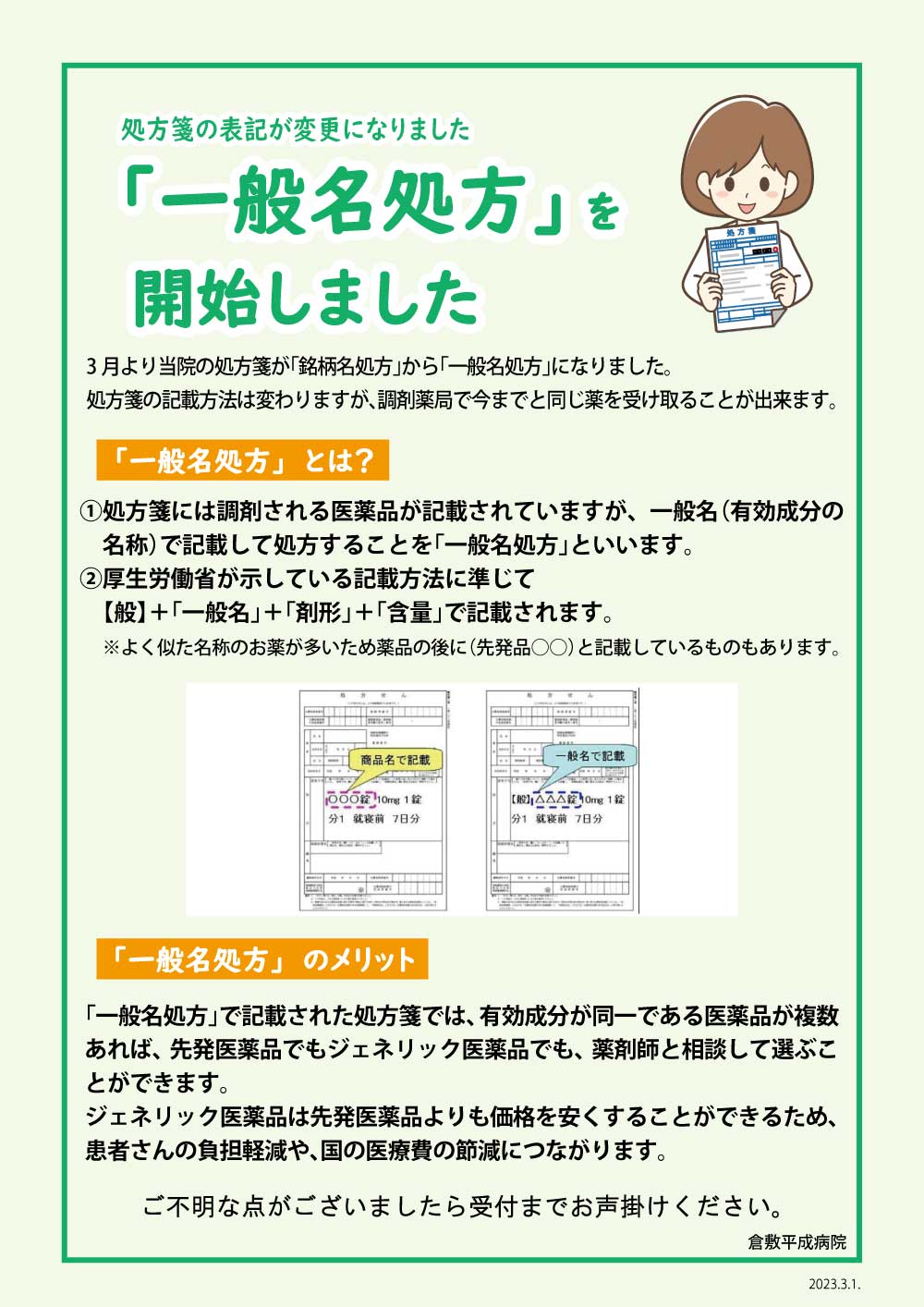
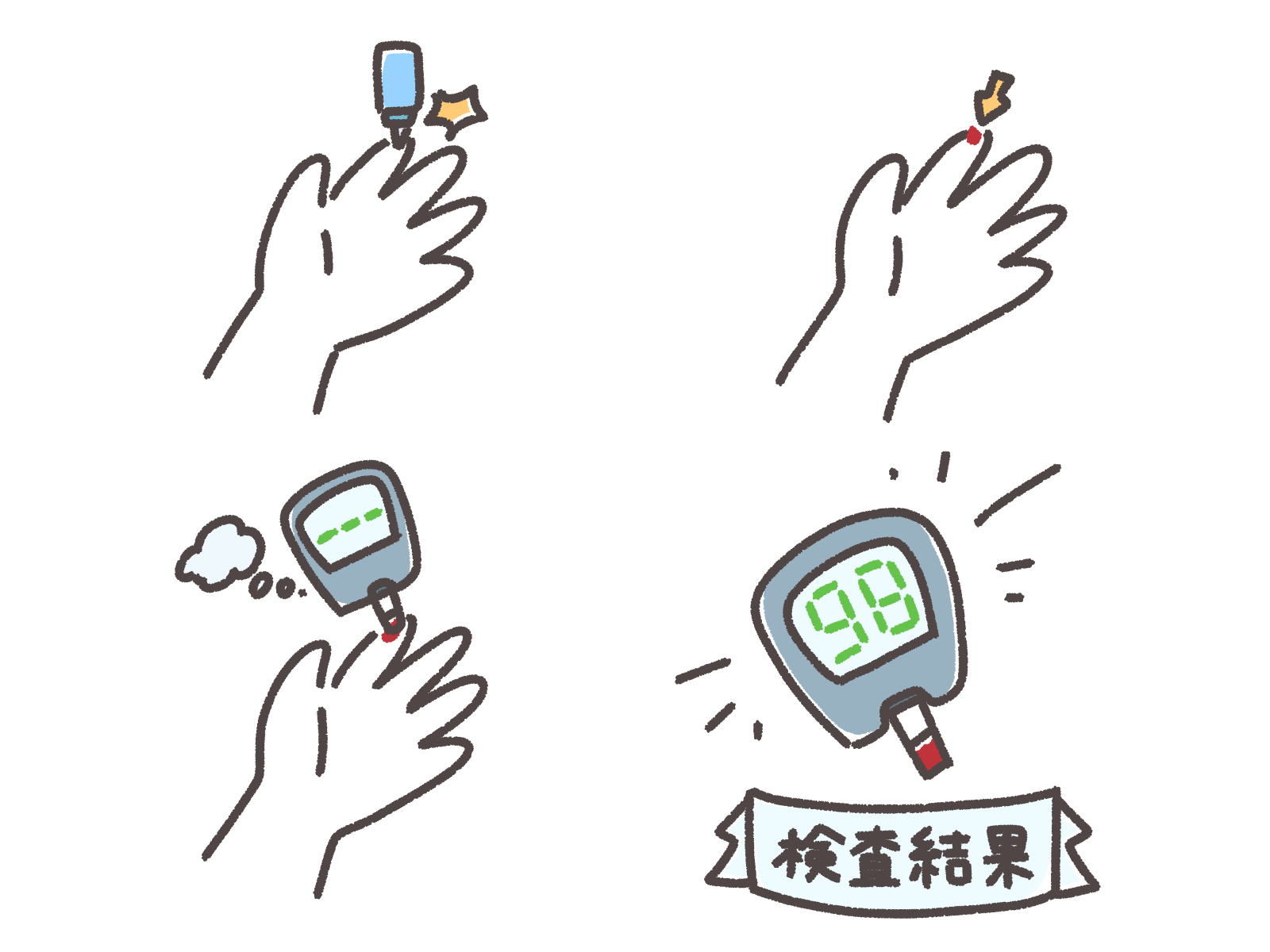
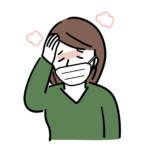 でも1月6日にインフルエンザ注意報(流行シーズン入り※岡山県発表)が発令されています。当院でもインフルエンザの患者さんが増えてきているように感じます。そこで、インフルエンザの治療薬、予防薬についておさらいしようと思います。(投与量は体重や腎機能等によって調節される場合があります)
でも1月6日にインフルエンザ注意報(流行シーズン入り※岡山県発表)が発令されています。当院でもインフルエンザの患者さんが増えてきているように感じます。そこで、インフルエンザの治療薬、予防薬についておさらいしようと思います。(投与量は体重や腎機能等によって調節される場合があります)