やわらかな春風に心華やぐ季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
予防リハビリも新年度を迎え、スタッフの異動に伴い、新たな想いで日々営業を行っております。今年度は介護報酬の改定もあり、地域包括ケアシステムの推進が一層強化されます。地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的とし、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制を構築1)することとされています。
そこで重要となるワードの一つが“自助”です。簡単に言うと、「自分の健康管理を自分で行う」ことであり、地域包括ケアシステムを構築するためには、皆様に“自助”する力を養ってもらう必要があります。その中において、予防リハビリの担う役割は、利用者様一人一人の自助能力を高める事だと考えています。まずは予防リハビリを利用して下さっている方々が、ご自身で健康管理ができるよう、プログラムを通して運動習慣の確立や外出機会の増加などを促しています。
今後も予防リハビリでは地域の健康を支えられるよう、スタッフが一丸となって質の高いサービス提供に努めて参ります。
利用に興味のある方は、ぜひ一度ご連絡下さい!
理学療法士 S
◎お問い合わせ◎
社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)
TEL:070-6690-2763 (相談員:あいやま)
MAIL:genki2reha@heisei.or.jp

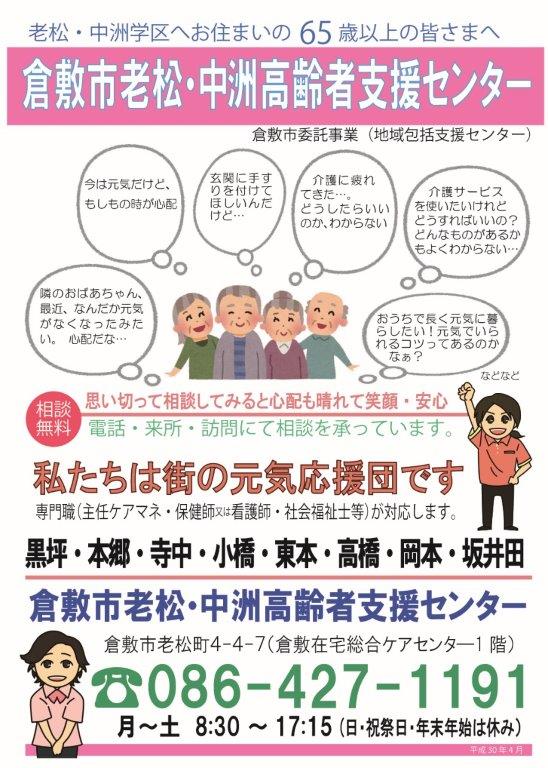
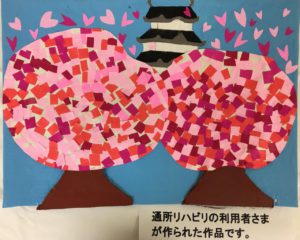







 倉敷ニューロモデュレーションセンターが開設されて本日で1年となりました。あっという間に過ぎた印象です。
倉敷ニューロモデュレーションセンターが開設されて本日で1年となりました。あっという間に過ぎた印象です。 では神経活動測定する機器操作や刺激電池の登録作業を行っています。病棟や外来ではSCSの痛み調整を医師の指示のもとで実施しています。患者さんのそばにほぼ毎日、何度も出向いて痛みがよくなるよう刺激調整を行っています。痛みが強く、苦悶して動けない患者さんにSCSを実施し刺激を開始すると、痛みが緩和され、表情もよく、起き上がってリハビリを一生懸命すると表情が良くなっていきます。退院時に「ありがとう」と話してくれるととてもうれしくなります。
では神経活動測定する機器操作や刺激電池の登録作業を行っています。病棟や外来ではSCSの痛み調整を医師の指示のもとで実施しています。患者さんのそばにほぼ毎日、何度も出向いて痛みがよくなるよう刺激調整を行っています。痛みが強く、苦悶して動けない患者さんにSCSを実施し刺激を開始すると、痛みが緩和され、表情もよく、起き上がってリハビリを一生懸命すると表情が良くなっていきます。退院時に「ありがとう」と話してくれるととてもうれしくなります。 「痙縮」は脳卒中や頭部外傷後に意思とは関係なく筋肉の緊張が高まり、手や足が勝手につっぱったり曲がってしまったりしてしまう状態のことで、日常生活に支障をきたす状態です。これについての薬物療法(バクロフェン髄腔内投与療法やボツリヌス療法)や手術療法などの最新治療法について聴講しました。
「痙縮」は脳卒中や頭部外傷後に意思とは関係なく筋肉の緊張が高まり、手や足が勝手につっぱったり曲がってしまったりしてしまう状態のことで、日常生活に支障をきたす状態です。これについての薬物療法(バクロフェン髄腔内投与療法やボツリヌス療法)や手術療法などの最新治療法について聴講しました。