ひと雨ごとにあたたかくなり、春の訪れを感じる今日この頃ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
我が家のクロッカスも落ち葉を押し上げて顔を出しました♡(写真)
先日『歌声広場』の研修(湊たましま大歌声喫茶)に行ってまいりました。ご報告いたします。
グランドガーデン南町の誕生会では2部が『歌声広場』となっており、よりよい会になるように、と研修が計画されました。
当日は早めの到着にも関わらず駐車場が混んでいて大変でした。やっと停めて会場入りすると70代~90代位と思われる方で一杯でした。中には3世代とお見受けするご家族もあり人気の高さを感じました。
入場時に歌声の本の貸し出しがあり、リクエストカードなども渡されました。私もさっそく書きましたが多くの方が積極的にリクエストされていました。そして開演です。まず、司会の『新宿ともしび』のお二人が素晴らしかったです。プロの歌手の方の司会のお声はまるで音楽を奏でるようで、うっとりしました。すーっと曲に入りやすい司会でした。また、声にも笑顔があるのだなって感じました。
童謡100周年の話より『ゆりかごの歌』『ウサギのダンス』いきなりの大合唱で始まりました。正直こんなに会場の方が大きな声で歌われるとは思っておらず、驚きました。『リンゴのひとりごと』『月の砂漠』私の右隣のご高齢の男性はさらに驚くほど大きなお声でした。左隣の女性(80代と紹介頂きました)も同じく大きなお声で歌われました。歌のリードも素晴らしく『あざみの歌』では荘厳な『山小舎の灯』では弾むようなお声で、会場の皆さん気持ちよさそうに歌われていました。
ゲスト、『ベイビー・ブー』のアカペラも圧巻でした。『証城寺の狸林』の重なる音の美しさはなんとも言えませんでした。
そして「次はにじ歌いましょう。」ピアノ伴奏があり「庭のシャベルが一日ぬれて・・・」とはじまったとたん私は涙腺が緩んでしまいました。急に娘が保育園だったころ思い出してしまいました。歌いながら当時のことが走馬灯のように思い出され(かけっこで転んだ、友達と喧嘩した、今日のおやつは美味しかった、太陽を見て歩いたら川に落ちた、みんなと運動会でお遊戯できた、びっくりするほど大きな口を開けてにじを歌った娘)よく熱を出し、けがする我が娘、それでも働く自分を責めたこともありました。それでもこうやって大きな声で歌っている、元気に娘は成長している、そう感じた頃の思い出の歌でした。
そのあとの『原爆を許すまじ』も懐古の曲となりました。私も大きな声で歌いましたが声合わせ歌うことでより一層昔を思い出すきっかけになっているのだと思います。ここで私の頭に浮かんだのは、小学生だった自分、廃校寸前の小さな木造の小学校の講堂、校長先生はじめ先生方の多くは泣きながら歌っていたように記憶しています。怖い歌だな、戦争嫌だな、、、友達と話したのを覚えています。講堂でみんなで見た戦争映画も思い出しました。怖くて目をそむけたとき、映写機から出る光に埃が舞っていたことまで鮮明に思い出しました。
一瞬にして当時を思い出す、、、みんなで歌う歌の力はすごいと改めて感じました。
特に戦中戦後を生き抜いてこられた年代の方にとって当時の歌とはいかほどのものだったか。
琴線に触れる・・・というのでしょうか。
それぞれの方がそれぞれの人生において思い出の歌があり、みんなで集い歌い、その時間を共有する場所。それこそが歌声広場なのだと改めて感じました。
相手を敬い愛情をもって介護を行う、歌声も同じだと感じました。
どうやったら歌いやすくなるのか、まだまだ課題はありますが、『大切なこと』をひとつ教わったと感じています。
最後に湊たましま大歌声喫茶実行委員の方々大変お世話になりました。
素直に楽しかったです。そして大切なこと学ばせて頂きました。
ありがとうございました。
今後のご発展をお祈りいたします。
グランドガーデン南町 介護福祉士S,H
 :086-427-1111
:086-427-1111
 まず、山陰合同銀行倉敷支店高橋一成支店長より、「我々ごうぎん一粒の麦の会は、山陰合同銀行の役職員が募金を行い、地域社会への感謝の気持ちを表すために奉仕していくことを目的といています。このたび、ささやかではありますが、車椅子をお贈りします。全仁会にてお役立ていただければ幸いです」とのご挨拶がありました。
まず、山陰合同銀行倉敷支店高橋一成支店長より、「我々ごうぎん一粒の麦の会は、山陰合同銀行の役職員が募金を行い、地域社会への感謝の気持ちを表すために奉仕していくことを目的といています。このたび、ささやかではありますが、車椅子をお贈りします。全仁会にてお役立ていただければ幸いです」とのご挨拶がありました。
 高尾理事長からは、「この車いすの寄贈を大変ありがたく思っております。当院は脳神経疾患専門病院として設立した経緯からも、車椅子を必要とされる患者さんが多くおられます。山陰合同銀行の地域社会貢献活動の精神を、日常の診療活動の中からしっかりと地域の皆様に伝えてまいります」との言葉がありました。
高尾理事長からは、「この車いすの寄贈を大変ありがたく思っております。当院は脳神経疾患専門病院として設立した経緯からも、車椅子を必要とされる患者さんが多くおられます。山陰合同銀行の地域社会貢献活動の精神を、日常の診療活動の中からしっかりと地域の皆様に伝えてまいります」との言葉がありました。
 3月14日(水)、ケアハウスで卯月茶会を開催!!
3月14日(水)、ケアハウスで卯月茶会を開催!! Mで流れてくる琴の音や梅の甘い香りも風流でしたね。
Mで流れてくる琴の音や梅の甘い香りも風流でしたね。


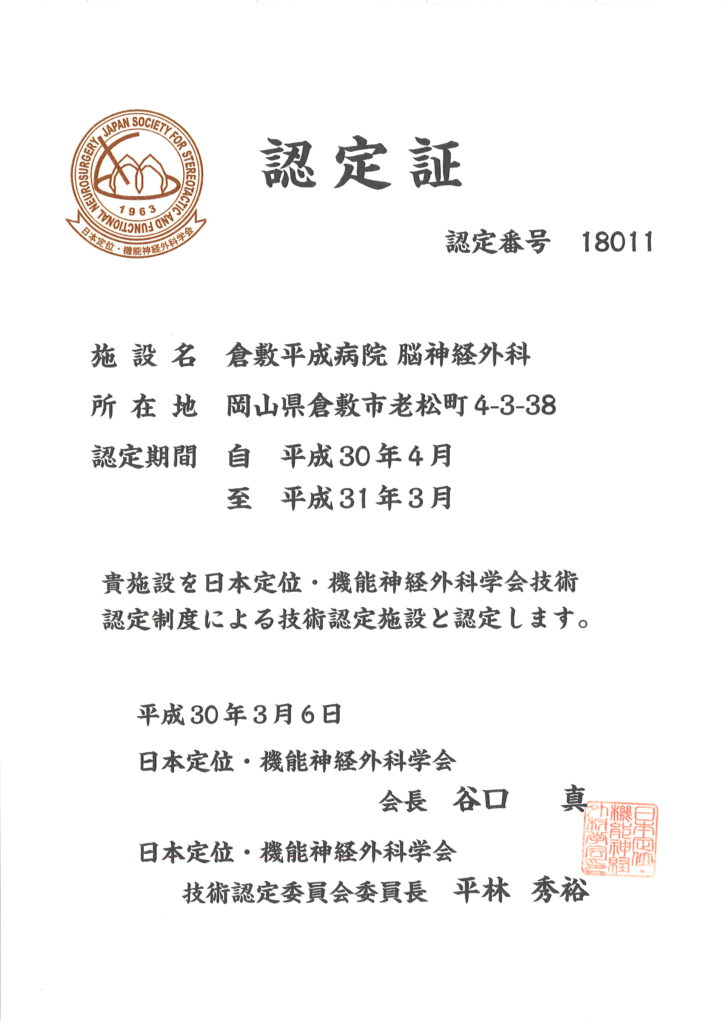 昨年4月に開設いたしました、倉敷ニューロモデュレーションセンターですが、1年間の活動実績が認められ、平成30年4月より日本定位・機能神経外科学会技術認定施設となることが決まりました。
昨年4月に開設いたしました、倉敷ニューロモデュレーションセンターですが、1年間の活動実績が認められ、平成30年4月より日本定位・機能神経外科学会技術認定施設となることが決まりました。





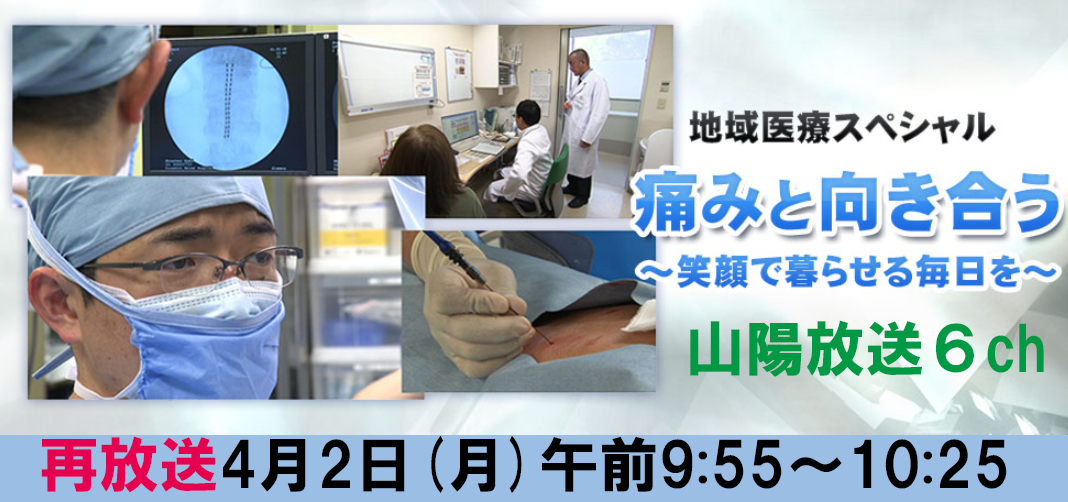

 平成30年3月26日(月)10時30分~ 第65回院内コンサートが開催されました。
平成30年3月26日(月)10時30分~ 第65回院内コンサートが開催されました。
 前日の25日に岡山県では桜の開花宣言がなされましたが、倉敷平成病院の桜並木もちらほら咲き始め、春の訪れを感じさせる暖かい陽光が降り注ぐ外来にて開催されました。
前日の25日に岡山県では桜の開花宣言がなされましたが、倉敷平成病院の桜並木もちらほら咲き始め、春の訪れを感じさせる暖かい陽光が降り注ぐ外来にて開催されました。


 るとまた新たにフレッシュな後輩たちがリハビリテーション部にも入ってきます。自分が入職したときのことを思い出すと懐かしいです。業務に慣れるまではいつもバタバタしており、迷惑もたくさんかけてしまったけれど、先輩や同期など周りのたくさんの方々に助けられながらここまで来ることが出来たと思います。
るとまた新たにフレッシュな後輩たちがリハビリテーション部にも入ってきます。自分が入職したときのことを思い出すと懐かしいです。業務に慣れるまではいつもバタバタしており、迷惑もたくさんかけてしまったけれど、先輩や同期など周りのたくさんの方々に助けられながらここまで来ることが出来たと思います。