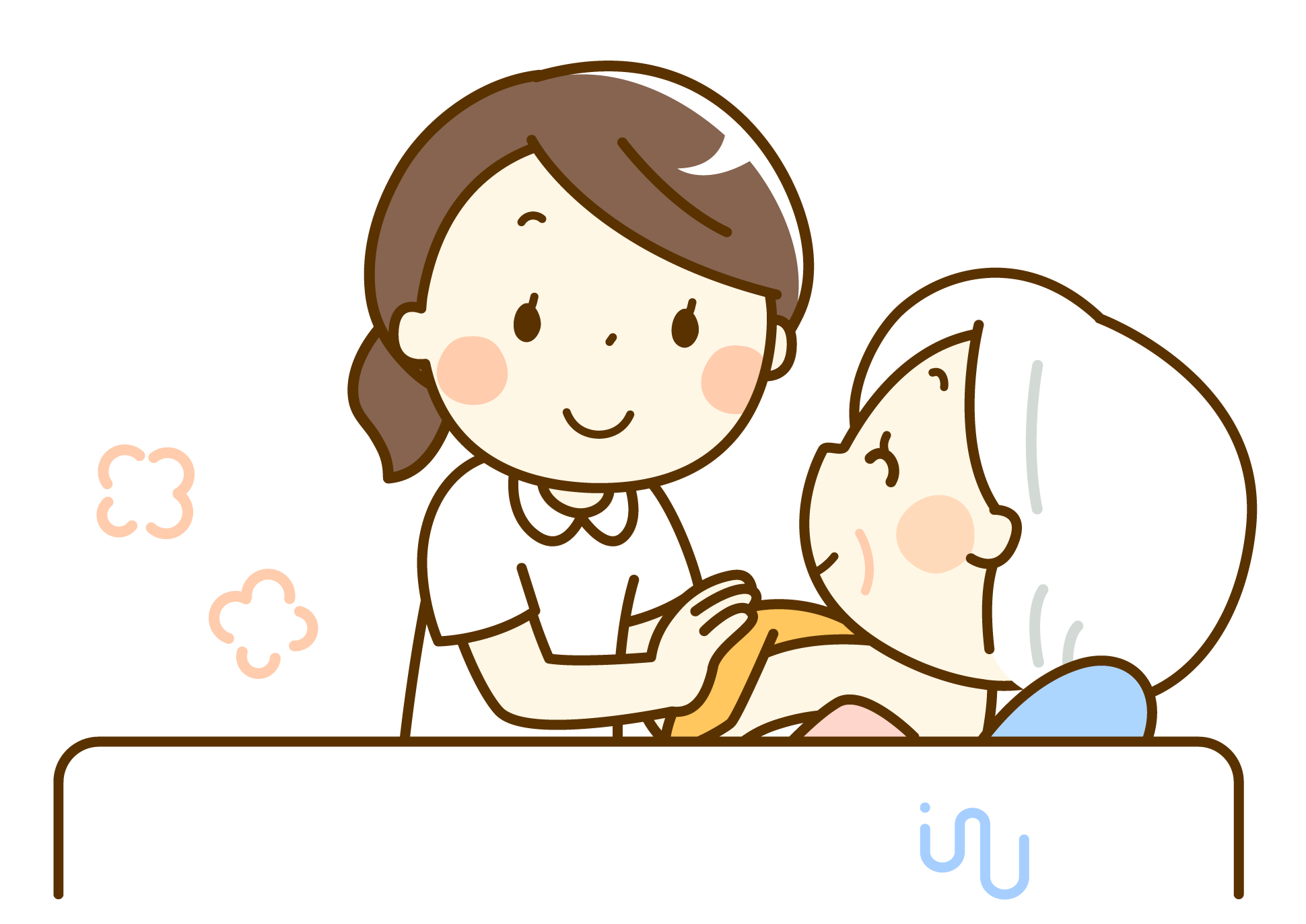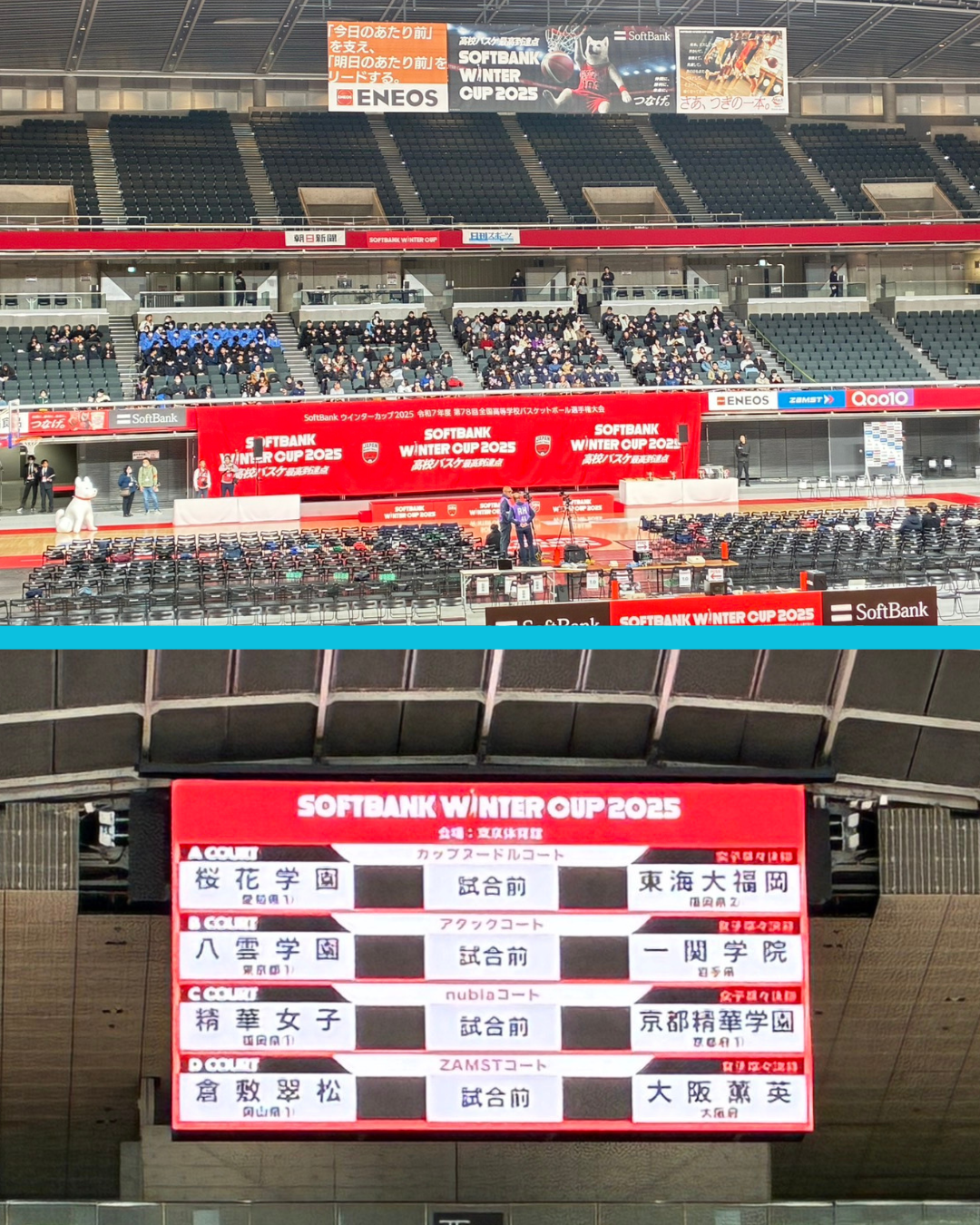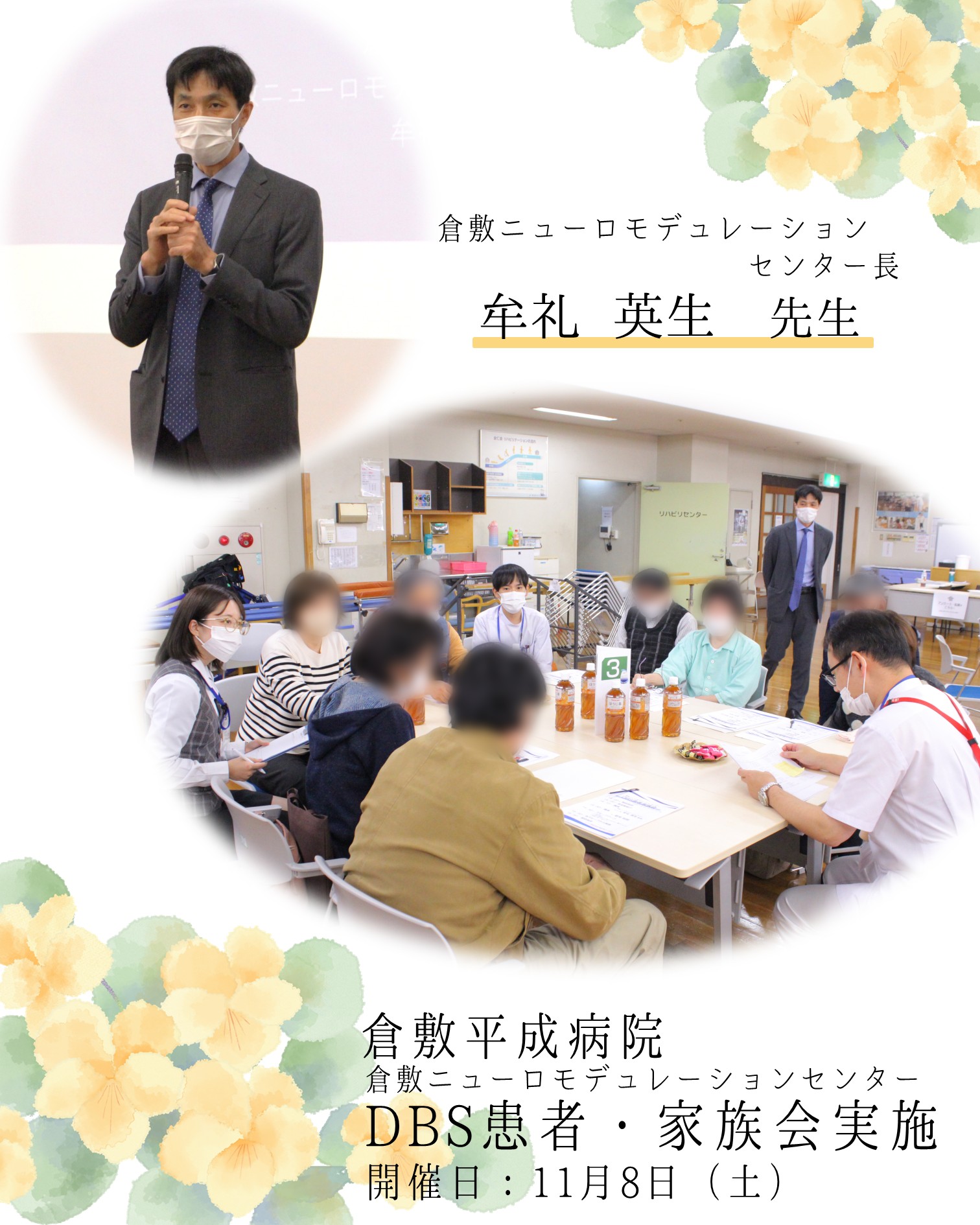12月26日(金)、倉敷平成病院 回復期リハビリテーション病棟にて、軽やかな音楽に包まれながら「クリスマス会」を開催しました。
会場では、赤いサンタ帽やトナカイのカチューシャを身につけた患者さんの姿があちこちに見られ、いつもとは少し違う、わくわくした雰囲気が広がっていました。
音楽療法の一環として、職員によるフルートとピアノの演奏が始まると、やさしい音色のクリスマスメドレーが病棟に響き渡り、自然と口ずさむ声が聞こえてきました。患者さんは手作りの楽器を手に、それぞれのペースで音楽を楽しまれていました。
また、今回は院内保育の子どもたち5名も参加してくれました。
演奏の途中では、患者さんから子どもたちへ、心を込めて用意したプレゼントを手渡す場面があり、「どうぞ」と声をかける患者さんと、少し照れながらでも目線を合わせて受け取る子どもたちの姿に、会場は自然と笑顔とあたたかな拍手に包まれました。
優しい音色が流れる中、患者さんも子どもたちも穏やかな表情を見せ、楽しそうな様子がとても印象的でした。短い時間ではありましたが、音楽を通して同じ時間を共有し、世代を超えたふれあいを感じられる、心温まるクリスマスのひとときとなりました。
4階西病棟 介護副主任 O