倉敷平成病院の沿道の桜も少しずつ咲き始め、春の陽気が感じられるようになってきました。
現在、人事課ではリクルート用動画の作成を行っています。
最近では、「入職1年目の看護師インタビュー動画」「介護職募集用動画」を新たにYouTubeにて公開いたしました。約3分程度のショートムービーとなっておりますのでぜひお気軽に閲覧いただき、就職を検討されている方のみならず、より多くの方にも全仁会の魅力を知っていただける機会となれば幸いです。
【倉敷平成病院 1年目看護師 インタビュー】
【全仁会グループ 介護職 募集動画】
今年度は感染対策のため、直接病院や施設に学生の皆様をご案内できず、リモート説明会に変更いただいたことも多々ありました。そのため求職者の皆様にとっては、職場の雰囲気や職員の様子も伝わりづらい部分もあったかと思います。
そういった反省点を受け、来年度は新しい生活様式に合わせたリクルート活動ができるよう、人事課でも様々な職種・内容の動画を作成し、工夫を凝らしたPRを行って参りたいと考えています。
最新の求人情報につきましては、当院ホームページをご参考いただくか、お電話やメールにて人事課までお問い合わせください。来年度もよろしくお願いいたします。
人事課 H

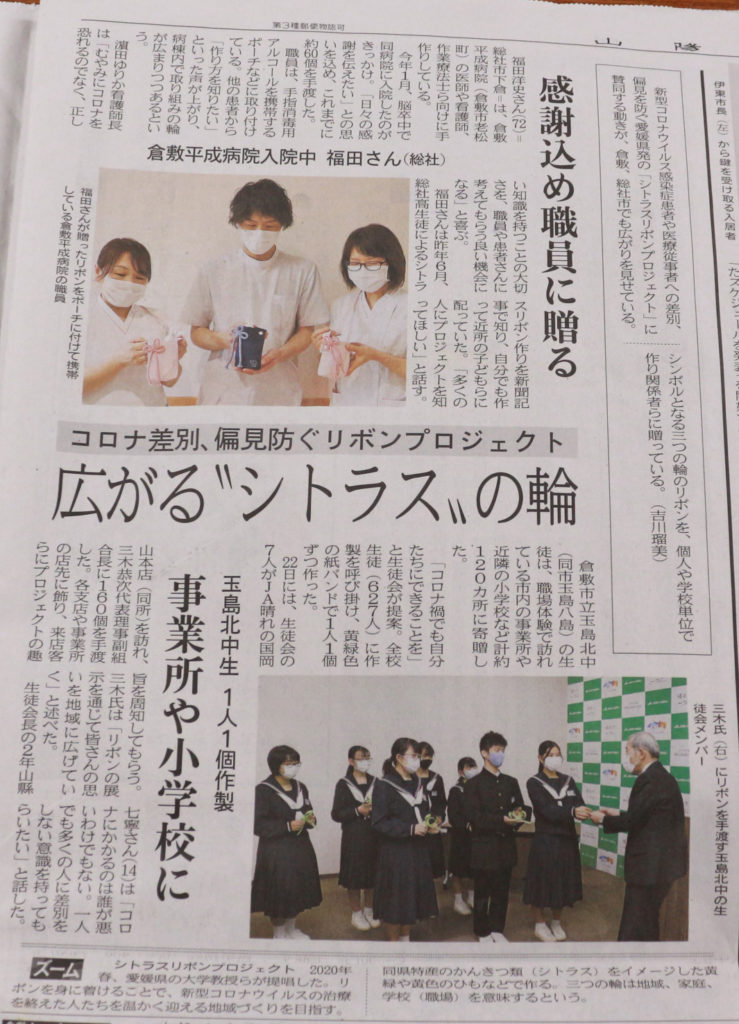
 ホームヘルパーとは、ご利用の方が日常生活上困難なことを援助し、穏やかに住み慣れた自宅で過ごすことができるようお助けする、言わばお助けマンです!!!
ホームヘルパーとは、ご利用の方が日常生活上困難なことを援助し、穏やかに住み慣れた自宅で過ごすことができるようお助けする、言わばお助けマンです!!! う健康講座を実施しています。
う健康講座を実施しています。
 先日、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の緊急事態宣言がされましたが、まだまだ油断できない日々が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか?
先日、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の緊急事態宣言がされましたが、まだまだ油断できない日々が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか? 様はお変わりなく過ごされていますでしょうか。
様はお変わりなく過ごされていますでしょうか。




 早いもので、もう年度末の3月がやってきてしまいました。
早いもので、もう年度末の3月がやってきてしまいました。 何も目的のない運動はしぶしぶですが、楽しい目的がある時の動きは素早いものです。(目的って大切だなぁ)と痛感します。
何も目的のない運動はしぶしぶですが、楽しい目的がある時の動きは素早いものです。(目的って大切だなぁ)と痛感します。