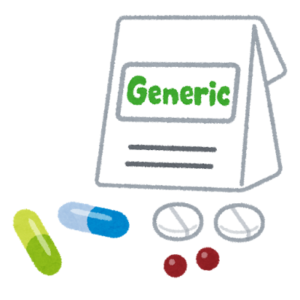糖尿病治療では毎日の血糖コントロールが重要になりますが、糖尿病患者の中には秋から冬にかけて血糖コントロールが上手くいかないと訴える人が多く見られます。
季節の変化で血糖値が影響を受けることは本当にあるのでしょうか?
季節による血糖値の変動については、今までにいくつもの報告がありました。日本では、福島・東京・三重・和歌山・島根・大分など、各地で調査が行われています。日本国内だけでなく、海外でも同じような疫学調査が行われています。
調査ではいずれも、HbA1c(ヘモグロビンA1c)の数値が1~3月に高くなり、8~10月に低くなるという結果になりました。つまり各地で行われた研究の結果では、血糖値は秋から冬にかけて高くなり、夏には低くなるという傾向があったということになります。
なぜ季節によって血糖値が変化するのかは、まだはっきりと分かっていませんが、季節による生活の変化が原因だと見られています。
秋から冬にかけては、食べ物がおいしくなる季節です。特に、秋に実る梨・柿・みかんといった果物は糖度が高くて美味しいのですが、果物の食べ過ぎで糖尿病を悪化させてしまう例もあります。
また、年末年始は忘年 会・新年会といった行事が多くあります。そういった機会に、つい食べ過ぎてしまうことも関係しているとみられています。さらに冬は寒いため、どうしても運動量が少なくなってしまうという人も多いのではないでしょうか。そういった日常生活の変化が重なって、秋から冬にかけては血糖値が上昇してしまうのです。
会・新年会といった行事が多くあります。そういった機会に、つい食べ過ぎてしまうことも関係しているとみられています。さらに冬は寒いため、どうしても運動量が少なくなってしまうという人も多いのではないでしょうか。そういった日常生活の変化が重なって、秋から冬にかけては血糖値が上昇してしまうのです。
夏の暑さで落ちていた食欲も、秋になると戻ってきます。しかし、血糖値を安定させるためには食べ過ぎないよう心がけることが大切です。
食べる順番にも気を配りましょう。最初にサラダやおひたしといった野菜料理を食べると、血糖値の急激な上昇を抑えることができます。糖度の高い果物は、体を動かしている日中に摂るようにしましょう。また、夕食後に果物を食べると、果糖が体に貯まりやすくなります。
シルバーウィークや年末年始の長期休暇中は、ついだらけてしまいがちです。気がつくと、一日中なにかを口にしていたということも。だらだら食べをしないように心がけ、食べた量をきちんと把握するようにしましょう。
糖尿病療養指導士 薬剤部 S.A


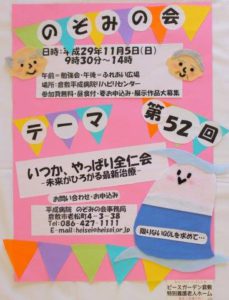


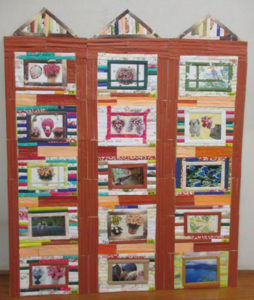
 秋空が広がり、少し暑さも感じる中、平成29年9月23日(土)に、JA岡山西吉備路農業祭に、渉外課、事務、看護師、理学療法士の6名で参加してきました。
秋空が広がり、少し暑さも感じる中、平成29年9月23日(土)に、JA岡山西吉備路農業祭に、渉外課、事務、看護師、理学療法士の6名で参加してきました。

 9月30日(土)午後、倉敷在宅総合ケアセンター四階多目的ホールにて新入職員フォローアップ研修(6ヵ月目)が開催されました(参加者72名)。
9月30日(土)午後、倉敷在宅総合ケアセンター四階多目的ホールにて新入職員フォローアップ研修(6ヵ月目)が開催されました(参加者72名)。
 職種間連携・報連相・コミュニケーション等の大切さ
職種間連携・報連相・コミュニケーション等の大切さ を改めて共有する事が出来たのではないかと思います。次に「振り返りチェックシート」を用いて、3ヵ月目と現在の自分自身を比較し、成長出来た事・今後努力が必要な事を振り返りました。続いて4枚の画用紙に「入職前」「3ヵ月目」「6ヵ月目」のそれぞれ当時の気持ちや様子と、「半年後の課題・目標」をまとめてもらい、グループ毎に発表していただきました。紙芝居形式の発表を行い、イラスト等も取り入れる事により各グループで当時の気持ちをしっかり振り返る事が出来ていました。また、どのグループも悩んでいる内容や時期には共通点があり、それを乗り越え新たな目標も明確に設定出来ていました。
を改めて共有する事が出来たのではないかと思います。次に「振り返りチェックシート」を用いて、3ヵ月目と現在の自分自身を比較し、成長出来た事・今後努力が必要な事を振り返りました。続いて4枚の画用紙に「入職前」「3ヵ月目」「6ヵ月目」のそれぞれ当時の気持ちや様子と、「半年後の課題・目標」をまとめてもらい、グループ毎に発表していただきました。紙芝居形式の発表を行い、イラスト等も取り入れる事により各グループで当時の気持ちをしっかり振り返る事が出来ていました。また、どのグループも悩んでいる内容や時期には共通点があり、それを乗り越え新たな目標も明確に設定出来ていました。