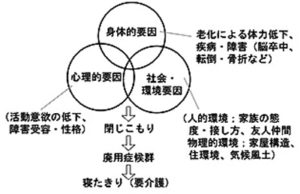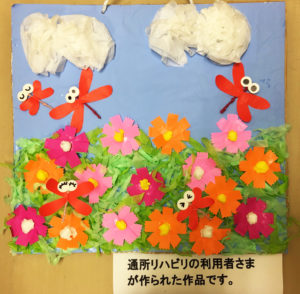さわやかな秋晴れの続く今日此頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
月1回掲載させて頂いている通所リハビリのブログでは先月から3回に分けて『閉じこもりと廃用症候群』についてお話しさせて頂いています。
今月は“廃用症候群の症状”についてお話しします。
廃用というのは(体の機能を)用いない・使わないこと、すなわち生活が不活発なことの意味を表します。
廃用症候群とは「生活不活発病」とも呼ばれ、進行は早く、特に高齢者はその現象が著明です。1週間寝たままの状態を続けると、10%~15%程度の筋力低下が見られます。足腰が弱くなり、動くと息が切れトイレに行くのも困難になることがあります。また高齢の場合、病気やケガなどでしばらく寝たきりになると立てなくなったり、あるいは歩けなくなったりすることもあります。絶対安静の状態になり筋収縮が行われなくなると、廃用症候群が起きてしまいます。
廃用症候群の主な症状として
①体の一部に起こるもの(関節拘縮、筋力低下、廃用性骨萎縮、皮膚萎縮、褥瘡、肺塞栓症)、
②全身に影響するもの(心肺機能低下、起立性低血圧、食欲不振、便秘、脱水)、
③精神や神経の働きに起こるもの(うつ状態、知的活動低下、周囲への無関心、自律神経不安定、姿勢・運動調節機能低下など)などがあります。
ここで問題なのは①は比較的知られていますが、②③はあまり知られていないことです。しかし実際には②③に属するものも重要で、特に心肺機能低下は持久力を中心とした総合的体力が低下することであり、廃用症候群の初期症状の一つである『疲れやすさ』もこれが主な原因です。このような多様な症状があまり知られていない為、廃用症候群が発生していても見過ごされていることも多いものです。
また一部の症状に注意が偏り筋力増加や関節可動域訓練など特定の「身体機能」への対応だけにならないよう注意が必要です。廃用症候群の発見の為には、これらの症状がはっきり出てから気付くのではなく、生活が不活発であれば生じているはずという観点で探すことが大事です。
次回は廃用症候群の予防法についてご紹介をしていきます。
通所リハビリ 介護福祉士 K
 こんにちは、通所リハビリです。11月1日に今月の作品を外来に飾りました。「六重塔と紅葉」です。本当は五重塔にする予定でしたが、もう一段高くしてもいいんじゃない?とのことで六重塔が完成しました。
こんにちは、通所リハビリです。11月1日に今月の作品を外来に飾りました。「六重塔と紅葉」です。本当は五重塔にする予定でしたが、もう一段高くしてもいいんじゃない?とのことで六重塔が完成しました。 ほぼ切り絵の作品ですが、特に鹿のシルエットを切り抜くのは大変そうでした。はさみで作業をするのですが、細かいところは時間をかけて丁寧に切り抜いてくださいました。
ほぼ切り絵の作品ですが、特に鹿のシルエットを切り抜くのは大変そうでした。はさみで作業をするのですが、細かいところは時間をかけて丁寧に切り抜いてくださいました。
 こんにちは、通所リハビリです。10月1日に今月の作品を外来待合に飾りました。
こんにちは、通所リハビリです。10月1日に今月の作品を外来待合に飾りました。 真っ赤な夕焼けに赤とんぼが舞っています。トンボは爪楊枝に毛糸を巻いて胴体を作り、赤いフィルムを羽根にしました。トンボの羽根の透明感が伝わりますでしょうか。また柿はティッシュを丸めて制作しましたが、実際に自宅に柿の木をお持ちの方が枝ぶりや柿の実が枝についている様子など工夫してくださいました。
真っ赤な夕焼けに赤とんぼが舞っています。トンボは爪楊枝に毛糸を巻いて胴体を作り、赤いフィルムを羽根にしました。トンボの羽根の透明感が伝わりますでしょうか。また柿はティッシュを丸めて制作しましたが、実際に自宅に柿の木をお持ちの方が枝ぶりや柿の実が枝についている様子など工夫してくださいました。 今日は敬老の日ですね。さて、9月10日(日)に、倉敷労働会館にて「平成29年度老松学区敬老会」が開催されました。当院からは外来看護師、管理栄養士、医療福祉相談員、事務2名、介護士、理学療法士の計7名で参加してきました。
今日は敬老の日ですね。さて、9月10日(日)に、倉敷労働会館にて「平成29年度老松学区敬老会」が開催されました。当院からは外来看護師、管理栄養士、医療福祉相談員、事務2名、介護士、理学療法士の計7名で参加してきました。

 敬老会に参加させて頂き、皆さんの楽しんでいる姿に、私も元気をもらいました。また、この敬老会が地域に根ざし、心待ちにされている会だと実感するとともに、今後もこういった機会に全仁会の一員として地域との交流を深めていきたいと思いました。
敬老会に参加させて頂き、皆さんの楽しんでいる姿に、私も元気をもらいました。また、この敬老会が地域に根ざし、心待ちにされている会だと実感するとともに、今後もこういった機会に全仁会の一員として地域との交流を深めていきたいと思いました。 9月7日(木)、通所リハご利用の方2名と今年度最後の読み聞かせを行いました。当日は雨が降り、園の方にもタオルをご用意いただく等ご配慮下さいました。
9月7日(木)、通所リハご利用の方2名と今年度最後の読み聞かせを行いました。当日は雨が降り、園の方にもタオルをご用意いただく等ご配慮下さいました。
 会の最後には、園児たちとお二人の交流タイムも設けられ、手作りの首飾りをプレゼントしてもらい、握手をして親交を深めました。AさんもYさんも、最初はとても緊張されていましたが、「とてもかわいい園児たちに絵本を読めてよかった」と、戻られてからも大変晴れ晴れした表情でおられました。また新田中学校2年生の生徒たち2名が職場体験で園にこられており一緒に参加してくれました。
会の最後には、園児たちとお二人の交流タイムも設けられ、手作りの首飾りをプレゼントしてもらい、握手をして親交を深めました。AさんもYさんも、最初はとても緊張されていましたが、「とてもかわいい園児たちに絵本を読めてよかった」と、戻られてからも大変晴れ晴れした表情でおられました。また新田中学校2年生の生徒たち2名が職場体験で園にこられており一緒に参加してくれました。