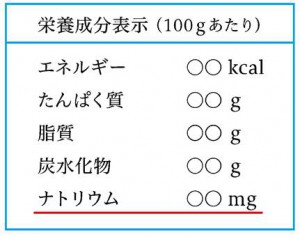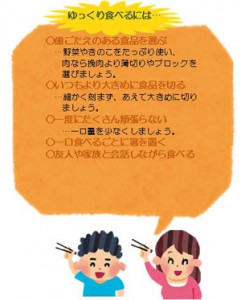10月3日(土)、倉敷生活習慣病センターにおいて『第80回糖尿病料理教室』を開催しました。今回のテーマは『素敵な朝ごはん♪』。ついつい簡単に済ませてしまいがちな朝ごはんのバランスを整えるため、最近流行りのスティックオープンサンドや花束サラダに挑戦。乗せたり巻いたり、楽しく華やかに仕上げることができました。夏の猛暑で疲れた体をいたわって、少し丁寧な食事をしてみるのもいいですね。デザートのヨナナスメーカーで作ったパフェも珍しくて好評でした。
10月3日(土)、倉敷生活習慣病センターにおいて『第80回糖尿病料理教室』を開催しました。今回のテーマは『素敵な朝ごはん♪』。ついつい簡単に済ませてしまいがちな朝ごはんのバランスを整えるため、最近流行りのスティックオープンサンドや花束サラダに挑戦。乗せたり巻いたり、楽しく華やかに仕上げることができました。夏の猛暑で疲れた体をいたわって、少し丁寧な食事をしてみるのもいいですね。デザートのヨナナスメーカーで作ったパフェも珍しくて好評でした。
次回は12月に、おせち料理に活かせるような和食をテーマに開催予定です。
◎デザートタイム◎
冷凍した果物をヨナナスメーカーでスカッシュ(押し出す)すると、果物がまったりとジェラートのように変身!バナナとブルーベリーを混ぜて濃厚おいしいデザートができました。カロリーコントロールアイスと合わせても80kcal以下なんてヘルシー♪
◎本日のメニュー◎
●スティックオープンサンド
・きゅうり+かにディップ:かに缶と水切ヨーグルトを混ぜたディップが簡単で美味しい。
・プチトマト+水切ヨーグルト:2色のトマトを使ってカラフルに。オリーブオイルでいただきます。
・ゆで卵+アボカド+えび:カロリーハーフのマヨネーズを塗って順序良く並べて。
・プルーン+水切ヨーグルト+くるみ:プルーンは1晩紅茶に漬けることで柔らかく食べやすく。
●ビーフシチュー:具を一口大に切って食べ応え抜群に。ルウも赤ワインとデミグラスソースで手作りしました。
●和風ピンチョス:型抜きした野菜をつまようじで刺せばかわいいピンチョスの完成!柚子胡椒を入れたドレッシングで少し和風に。
●花束サラダ:油や水に強いワックスペーパーで、サーモン、卵、きゅうりでできた花を包めば見た目もかわいい花束サラダに変身。
●ヨナナスパフェ:冷凍した果物で作ったヨナナスとカロリーコントロールアイスを使ったパフェならヘルシーで美味しいデザートに。
計576kcal
※メニューご希望の方は倉敷生活習慣病センター受付にてお訊ね下さい。
糖尿病療養指導士・管理栄養士 E.O