最近、カフェやレストランのドリンクメニューで『チャイ』を見かけることが増えてきたように思います。あまり飲んだことがなく敬遠されている方が多いかもしれません。
チャイとはヒンディー語で「茶」を意味します。国によってチャイのスタイルは様々で、インドでは茶葉とスパイスを煮だし、牛乳と砂糖を加えたミルクティーのようなチャイ、ロシアやトルコのチャイは牛乳を入れず砂糖のみの甘い紅茶です。
海外でチャイをオーダーするときは、「砂糖なし」と言わなければ甘すぎて日本人の口に合わない事が多々あります。
日本で最もメジャーなチャイはインド式のスパイスの入ったマサラチャイです。マサラとはヒンディー語で「スパイス」を意味します。入れるスパイスの種類、量によって何通りものチャイを楽しむことができます。
使用するスパイスはシナモン、カルダモン、クローブ、スターアニスが代表的です。シナモンはお菓子を作られる方にはお馴染みですね。
 シナモンには抗菌作用、発汗作用があり、多くの効能があります。
シナモンには抗菌作用、発汗作用があり、多くの効能があります。
その他に、 ・毛細血管の老化防止、修復
・毛細血管を丈夫にすることによるシミ、しわ、たるみ、抜け毛の予防、改善
・脂肪細胞を小さくする
・血行促進による冷え、むくみの改善
・中性脂肪、コレステロールを下げる
・血栓予防
・リラックス、安眠効果
などがあります。
1日の摂取量は3ℊ程度が適量とされ、過剰摂取(1日10ℊ以上)は肝機能に影響を与える可能性がありますのでご注意を。
シナモン一振りが約0.6ℊ、小さじ1杯は約2ℊですので、お菓子作りに使用する程度の量であれば問題ありません。
その他のスパイスの効能は、
カルダモン:消化器官の不調を改善し、消化不良の際に唾液や胃液の分泌を促し消化を助ける。
腸内に溜まったガスを取り除く。
クローブ:鎮痛効果と抗菌作用。
消化を促進し胃腸を整える。
スターアニス:胃腸の働きを促進。
月経を順調にする。
これらはほんの一部ですが、薬のような効能がありますね。実際、シナモンは桂皮(けいひ)、スターアニスは大茴香(だいういきょう)と呼ばれ漢方薬に使われています。
 ちなみにスターアニスに含まれるシキミ酸は、インフルエンザ治療薬のタミフルの原料です。しかし、タミフルに利用されているのは化学合成したもので、スターアニスをスパイスとして料理などに使用しても効果はありませんのであしからず。
ちなみにスターアニスに含まれるシキミ酸は、インフルエンザ治療薬のタミフルの原料です。しかし、タミフルに利用されているのは化学合成したもので、スターアニスをスパイスとして料理などに使用しても効果はありませんのであしからず。
これらのスパイスを買いそろえてチャイを作るのは大変ですが、スパイスと茶葉をブレンドしたティーパックも売られています。そこへ好みのスパイスを追加してオリジナルのチャイを作ってみては?
管理栄養士 S.N




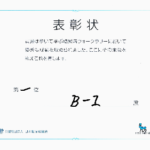






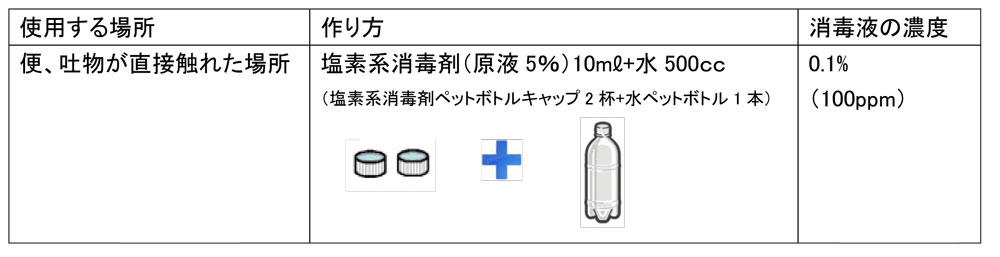 0
0