まだまだ風邪やインフルエンザが猛威をふるっていますが、お元気にお過ごしでしょうか?そして、寒い日が続き、トイレが近くなる季節でもありますが、安全にトイレに行けていますか?今回は、廃用症候群の1つ「失禁」に対する体操のご紹介です。
 排泄は、人の尊厳に関わる重要な課題です。現在、排尿に問題を抱えておられる方が800万人を超えると言われており、その症状の多くは、「尿漏れ」や「トイレが近い」「夜間排尿回数が多い」などです。その為「外出がおっくうになった」「気が滅入って友達との交流も少なくなった」「夜間熟睡できないので、日中も疲労感がある」など、心理的にも社会的にも影響を及ぼしていきます。また身体が不自由な人の排尿障害は、本人だけでなくお世話する家族にとっても苦労の多い問題です。おむつの使用は、経済面だけでなく、皮膚障害や感染症などの問題を引き起こします。それ故、おむつを使用しない生活を維持すること、一時的におむつを使用しても、できるだけ早くおむつからの離脱・自立を行う必要があります。その為には、膀胱機能(骨盤底筋)を強化する「排泄リハ体操」が有効です。
排泄は、人の尊厳に関わる重要な課題です。現在、排尿に問題を抱えておられる方が800万人を超えると言われており、その症状の多くは、「尿漏れ」や「トイレが近い」「夜間排尿回数が多い」などです。その為「外出がおっくうになった」「気が滅入って友達との交流も少なくなった」「夜間熟睡できないので、日中も疲労感がある」など、心理的にも社会的にも影響を及ぼしていきます。また身体が不自由な人の排尿障害は、本人だけでなくお世話する家族にとっても苦労の多い問題です。おむつの使用は、経済面だけでなく、皮膚障害や感染症などの問題を引き起こします。それ故、おむつを使用しない生活を維持すること、一時的におむつを使用しても、できるだけ早くおむつからの離脱・自立を行う必要があります。その為には、膀胱機能(骨盤底筋)を強化する「排泄リハ体操」が有効です。
通所リハビリ6フロアでは毎日15:30~16:00の30分間排泄リハ体操を行い骨盤底筋群を鍛えています。トイレにて排泄を行う為には沢山の手順を取ります。6フロアでは4過程に分けて体操をしています。
①一連の排泄行為までの移動(トイレの部屋へ近づく、トイレから離れる)
②トイレの便座へ移動(トイレに移る、車いすに移る)
③トイレ動作(服を下げる、服を上げる)
※②と③はバランス感覚を鍛えます
この体操はバランス感覚を鍛えていく体操の一例です。トイレ動作には方向転換などのバランスのいる動作が多いため、転倒予防で行っています。
④排泄管理(軽い尿漏れを防ぐ為に、トイレまで我慢できるように、尿道括約筋を鍛える、後始末)
 この中で一番力を入れているのは④番です。体操中やふと力が入った時などに尿漏れしないように骨盤底筋をしっかり鍛えています。(骨盤を上下左右に動かしたり、立ったまま臀部・膣・腹筋に力を入れたまま10秒20秒30秒とだんだん時間を延ばしながら2分までやっていきます。
この中で一番力を入れているのは④番です。体操中やふと力が入った時などに尿漏れしないように骨盤底筋をしっかり鍛えています。(骨盤を上下左右に動かしたり、立ったまま臀部・膣・腹筋に力を入れたまま10秒20秒30秒とだんだん時間を延ばしながら2分までやっていきます。
この体操は骨盤を動かす体操の一例です。腰を上下左右に動かし、骨盤のゆがみを整えたり、動かしやすくする体操です。
ご自分にどの練習が必要なのかがこの4つを見ればわかると思います。もし排泄問題を抱えている方がいれば是非我々と楽しく予防体操をして問題を解決していきましょう。通所リハビリテーションに興味がある方はお気軽にご連絡ください。いつでも見学・体験をお待ちしております。
通所リハビリテーション 介護士M



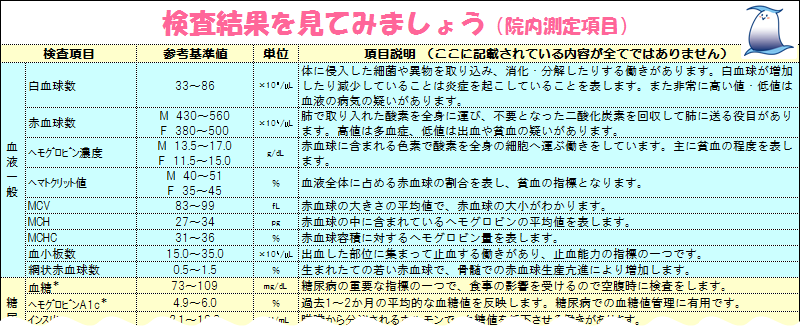




 『老松小学校のみなさん。倉敷老健入所中のおじいさんが作ってくれた作品を、大事にしてくれてありがとうございます。みなさんが空き缶を頑張って集めて届けてくれた車椅子、私たちも大事に使います。』
『老松小学校のみなさん。倉敷老健入所中のおじいさんが作ってくれた作品を、大事にしてくれてありがとうございます。みなさんが空き缶を頑張って集めて届けてくれた車椅子、私たちも大事に使います。』 医師・病院と患者をつなぐ医療検索サイト
医師・病院と患者をつなぐ医療検索サイト しています。
しています。 最新のフッ化物配合歯磨剤の使用量は、うがいができない2歳までの子供には切った爪くらい、3~5歳では約5mm、6~14歳では1cm、15歳以上では2cm程度の歯磨剤を使うとよいとされています。
最新のフッ化物配合歯磨剤の使用量は、うがいができない2歳までの子供には切った爪くらい、3~5歳では約5mm、6~14歳では1cm、15歳以上では2cm程度の歯磨剤を使うとよいとされています。 ニューロモデュレーションにおける臨床工学技士の果たす役割は大きく6つに大別され、1)DBSおよびSCSの手術支援、2)SCSの刺激調整、3)患者・家族への機器説明、指導の実施、4)院内スタッフに対する機器説明、指導の勉強会の実施、5)DBSコンタクトスクリーニングの実施、6)学会への参加等多岐にわたっています。
ニューロモデュレーションにおける臨床工学技士の果たす役割は大きく6つに大別され、1)DBSおよびSCSの手術支援、2)SCSの刺激調整、3)患者・家族への機器説明、指導の実施、4)院内スタッフに対する機器説明、指導の勉強会の実施、5)DBSコンタクトスクリーニングの実施、6)学会への参加等多岐にわたっています。 平成31年1月16日(水)ドリームガーデン倉敷、デイサービスドリームの新年会及び誕生日会を開催しました。ご入居の方々や、ご来賓の方、全仁会グループの関係者を合わせ、110名の方にご参加いただきました。賑やかに無事開催することができ改めて感謝申し上げます。
平成31年1月16日(水)ドリームガーデン倉敷、デイサービスドリームの新年会及び誕生日会を開催しました。ご入居の方々や、ご来賓の方、全仁会グループの関係者を合わせ、110名の方にご参加いただきました。賑やかに無事開催することができ改めて感謝申し上げます。 快晴で寒さも感じる中、皆様笑顔でお集まり頂き、目の前には美味しいおせち料理とお赤飯、ご入居の皆様と一緒に丹精込めて作り上げた干し柿も添えられ、初めて参加された方も「食べやすく、美味しかったです。また一年頑張りますよ」と笑顔で感想を述べて下さいました。1月生まれの方は1日生まれの方をはじめ8名おられ、皆様と一緒にドリームガーデンの式歌を合唱し、お祝いの花をお渡し和やかな雰囲気でした。
快晴で寒さも感じる中、皆様笑顔でお集まり頂き、目の前には美味しいおせち料理とお赤飯、ご入居の皆様と一緒に丹精込めて作り上げた干し柿も添えられ、初めて参加された方も「食べやすく、美味しかったです。また一年頑張りますよ」と笑顔で感想を述べて下さいました。1月生まれの方は1日生まれの方をはじめ8名おられ、皆様と一緒にドリームガーデンの式歌を合唱し、お祝いの花をお渡し和やかな雰囲気でした。
 このドリームガーデンに入って良かったと思って頂き、生活の一部に楽しみや安らぎ感じてもらえるように、スタッフが協力しながら、温かく支えていけたらと思います。本年もどうか宜しくお願い致します。
このドリームガーデンに入って良かったと思って頂き、生活の一部に楽しみや安らぎ感じてもらえるように、スタッフが協力しながら、温かく支えていけたらと思います。本年もどうか宜しくお願い致します。