 雨が降ったりやんだりすっきりしない天気が続いていますね。
雨が降ったりやんだりすっきりしない天気が続いていますね。
九州の方では雨が降り止まず甚大な被害が出ているというニュースを見て、2年前の真備の災害を経験した私たちとしても他人事とは思えません。
日本では、これから台風の時期にもなってきます。
もしもの時、慌てないように日頃から準備をしておくことが大切です。
日頃の備えとして、「洪水ハザードマップ」で浸水が想定されている地域を確認しておきましょう。避難場所は、災害種別によって違ってきます。災害発生時に素早く安全に避難できるように予め確認しておき、いざというときに慌てないようにしましょう。
非常用の飲料水や非常食、また常備薬などの準備はできていますか?災害発生時に家族と落ち合う場所や安否確認の方法は話し合っていますか?
また気象庁が発表している「防災気象情報」で情報収集をしましょう。
多くの場合、自治体が発令する避難勧告よりも先に発表されます。警戒レベルは5段階で設定されていて、「警戒レベル3」で高齢者等は避難、「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難。警戒レベルは順番で発表されるとは限らないので、防災気象情報を参考にしながら、避難行動を取りましょう。
何事も起こらないことが理想ですが、相手は自然災害です。災害から命を守るために、日頃から備えるようにしていきましょう。
糖尿病療養指導士 看護師 K

 色とりどりのアジサイが花を咲かせ、梅雨入りの時候を感じると同時に、夏に向かって急激に気温が上昇してきましたね。
色とりどりのアジサイが花を咲かせ、梅雨入りの時候を感じると同時に、夏に向かって急激に気温が上昇してきましたね。 尿の量を増やすためには、体の中の水分を使います。高血糖状態を改善するために、体の中の水分が多量に使われてしまうと、脱水状態になります。
尿の量を増やすためには、体の中の水分を使います。高血糖状態を改善するために、体の中の水分が多量に使われてしまうと、脱水状態になります。 最近、“フレイル”と言う言葉をよく耳にするようになりました。
最近、“フレイル”と言う言葉をよく耳にするようになりました。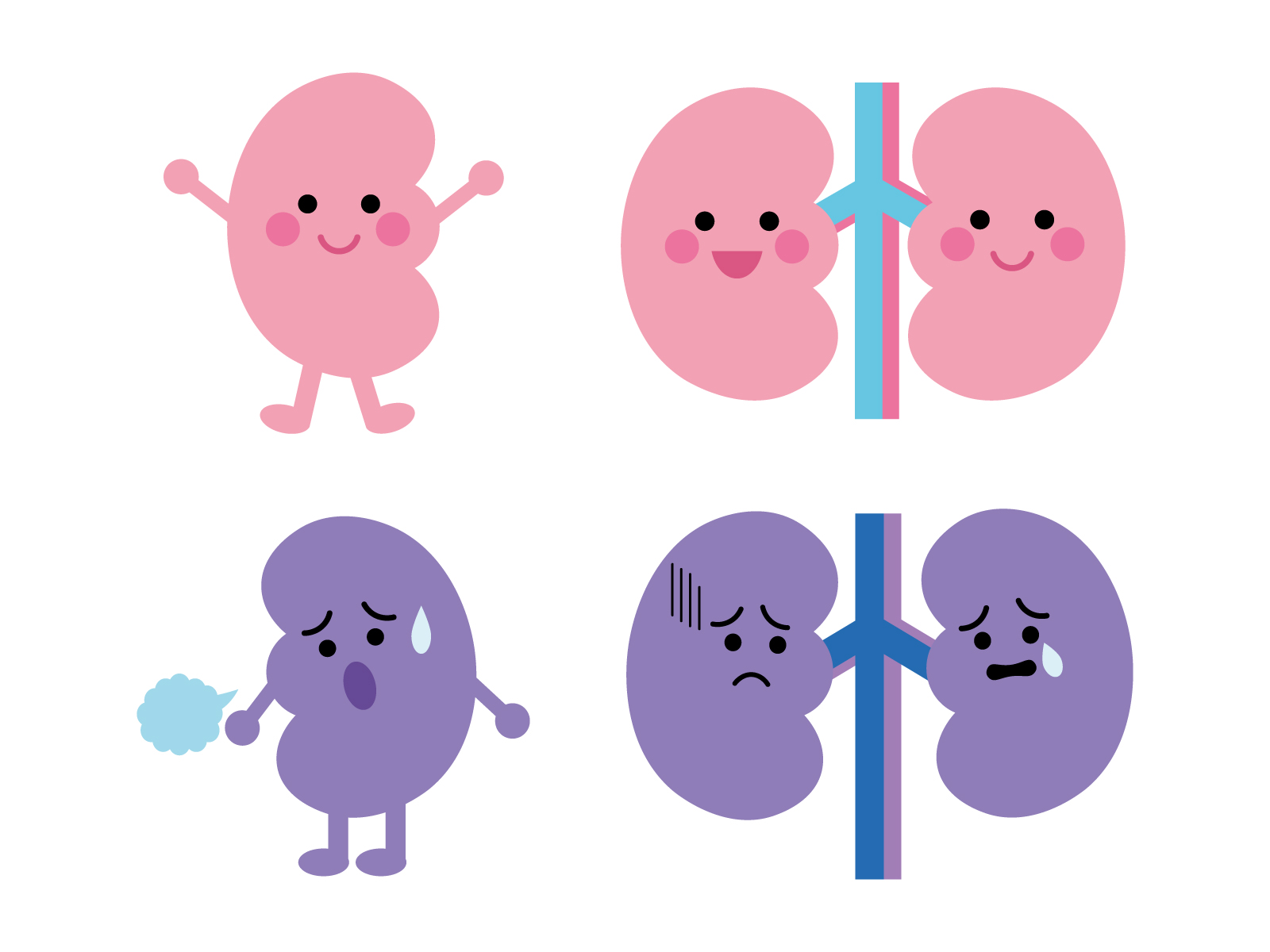




 2月1日(土)倉敷生活習慣病センターにおいて「第106回糖尿病料理教室」を開催しました。
2月1日(土)倉敷生活習慣病センターにおいて「第106回糖尿病料理教室」を開催しました。 【デザートタイム】
【デザートタイム】 インスリンやGLP-1受容体作動薬、骨粗鬆症治療薬などの自己注射や自己血糖測定をされている患者さんも多いかと思いますが、使用済の注射針は適切に廃棄できているでしょうか?
インスリンやGLP-1受容体作動薬、骨粗鬆症治療薬などの自己注射や自己血糖測定をされている患者さんも多いかと思いますが、使用済の注射針は適切に廃棄できているでしょうか?
