 早いもので気がつけば12月、朝晩はすっかり冷え込むようになりました。
早いもので気がつけば12月、朝晩はすっかり冷え込むようになりました。
今年の冬はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行が懸念されています。
寒くなってきていますが、換気、手洗い、マスクの着用など、基本的な感染対策を引き続き行っていきましょう。
国内に患者がおよそ1000万人いるとされる糖尿病について、病気の実態を示しておらずイメージも悪いとして、専門の医師らで作る「日本糖尿病協会」は病名の変更を求める方針を決めました。今後、新たな病名を提案したいとしています。
糖尿病は膵臓から出るホルモンのインスリンが不足するなどして血糖値が高い状態が続き、腎臓病や失明、神経障害などの合併症につながる病気で、免疫の異常や食べ過ぎ、運動不足などが関係して起きるとされています。
高血糖時には腎臓の働きで、血液中にあふれているブドウ糖(血糖)が尿の中に排泄され、尿糖としてからだの外に排出されます。これは、高血糖という異常事態を少しでも正常に近付けようとする、からだの正常な反応の結果といえます。糖尿病という病名は、この尿糖が出る(尿に糖が混ざる)現象から名付けられたものです。
日本糖尿病協会は、共通する症状は高血糖で、尿に糖が出ない患者も多く、症状を正確に表していないうえ、「尿」という言葉から不潔なイメージでみられるなどとして、病名の変更を求める方針を決めました。今後、1年から2年のうちに新たな病名について日本糖尿病学会とも連携して提案するとしていて、候補として共通する症状の「高血糖」を使うことなどが考えられるとしています。
長年、幅広い年代に理解され、認知されている「糖尿病」という名称を改名することは、簡単なことではないと思われますが、「○○○=糖尿病」と、誰もが誤解なくスムーズに理解していける名称に変更されることを願いたいものです。
糖尿病療養指導士 薬剤師 MM
参考:日本糖尿病協会ホームページ、糖尿病ネットワークホームページ

 11月に突入し、秋も深まり肌寒くなってきました。
11月に突入し、秋も深まり肌寒くなってきました。
 私が外来で服薬指導をする時、いつも心がけていることがあります。
私が外来で服薬指導をする時、いつも心がけていることがあります。 今日は糖尿病についての基本をお話ししたいと思います。
今日は糖尿病についての基本をお話ししたいと思います。 第22回日本糖尿病療養指導士認定試験が行われ、当院から受験した管理栄養士2名、薬剤師5名全員が合格しました。倉敷生活習慣病センター診療部長 青山 雅 先生をはじめ、糖尿病療養指導士の先輩方に何度もご指導いただきました。この場をお借りし、心より感謝申し上げます。
第22回日本糖尿病療養指導士認定試験が行われ、当院から受験した管理栄養士2名、薬剤師5名全員が合格しました。倉敷生活習慣病センター診療部長 青山 雅 先生をはじめ、糖尿病療養指導士の先輩方に何度もご指導いただきました。この場をお借りし、心より感謝申し上げます。 糖尿病患者はうつ病になりやすく、またうつ病患者も糖尿病になりやすいといわれています。うつ病になると、血糖値のコントロールが難しくなり、糖尿病の合併症リスクも上昇するため、うつ病を早期に発見し適切な治療を受けることが重要です。
糖尿病患者はうつ病になりやすく、またうつ病患者も糖尿病になりやすいといわれています。うつ病になると、血糖値のコントロールが難しくなり、糖尿病の合併症リスクも上昇するため、うつ病を早期に発見し適切な治療を受けることが重要です。 栄養、衛生、感染の重要性が高まっています。そこで今回は,爪楊枝に関する素朴な疑問をまとめてみました。
栄養、衛生、感染の重要性が高まっています。そこで今回は,爪楊枝に関する素朴な疑問をまとめてみました。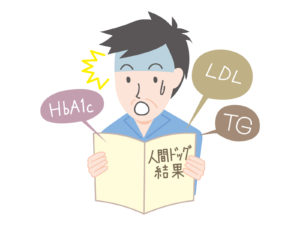 血糖値をコントロールすることは糖尿病の進行を予防する上でとても重要です。今回は血糖を上手にコントロールするために運動の観点からお話しさせていただきます。
血糖値をコントロールすることは糖尿病の進行を予防する上でとても重要です。今回は血糖を上手にコントロールするために運動の観点からお話しさせていただきます。 春の暖かさが待ち遠しい今日この頃、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
春の暖かさが待ち遠しい今日この頃、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。