連日湿度も高く、30度を超す日も多くなってきました。
気温の上昇とともに気をつけたいのが、脱水症や熱中症ですね。
脱水症になると体に様々な異変が表れます。めまい、吐き気、脱力感、手足の震えなどが主な症状となります。
また、体内の水分が奪われることにより、血液濃度の上昇にもつながります。そうすると血液の流れが悪くなり、血栓ができやすくなってしまします。
脳梗塞は、冬に多い印象がありますが、夏も脳梗塞には注意が必要です。
脳梗塞の前触れとしては、片側の手足の麻痺や、顔面の麻痺、しびれ、ろれつ不良、片方の目が見えにくいなどがあげられます。
このような症状がでれば、できるだけ早く医療機関への受診が必要です。
夏の脳梗塞の予防には、こまめな水分補給が必要です。喉が渇いた自覚があるときにはすでに脱水が始まっています。特に高齢に方は、喉の渇きも感じにくくなることもあります。
就寝中にも汗をかくため、就寝前、起床後に水分補給をおすすめします。

これからが夏本番です。水分補給をしっかりと行い、脱水症、熱中症には十分気をつけてこの夏を乗り越えましょう。
地域医療連携センター H
イラスト:イラストAC



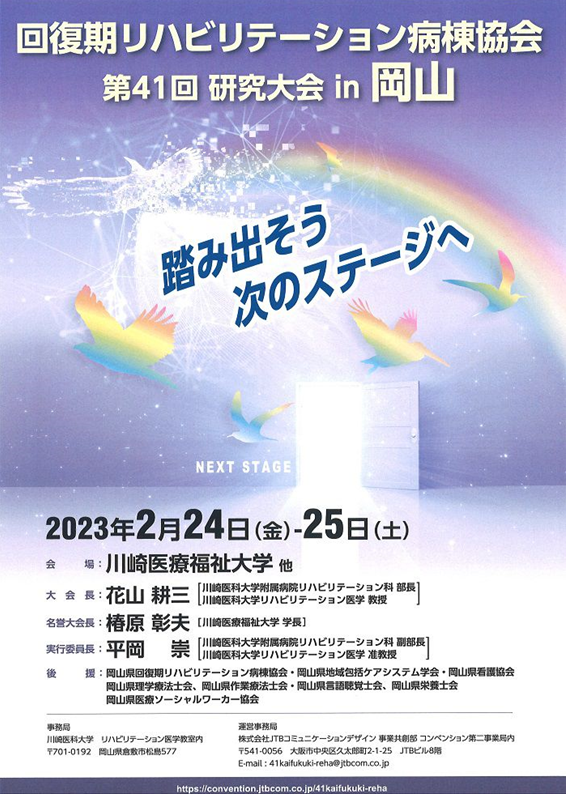 世間では3月13日以降、マスクの着用についは「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられる。」と政府より発表されていますが、医療の現場ではまだまだ感染症対策は気が抜けない日々が続いています。
世間では3月13日以降、マスクの着用についは「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられる。」と政府より発表されていますが、医療の現場ではまだまだ感染症対策は気が抜けない日々が続いています。 地域医療連携センター pooh
地域医療連携センター pooh 近では患者さんやご家族と面接をしたり、ケアマネさんや施設の相談員さんなどと情報を共有したりと、徐々に私も入退院支援に関わらせていただいております。業務量も入職したときよりも増え、あっという間に1日が終わってしまうことも多いですが、4月に設定した自分の目標の大切さを自分自身の体験で実感する出来事がありました。
近では患者さんやご家族と面接をしたり、ケアマネさんや施設の相談員さんなどと情報を共有したりと、徐々に私も入退院支援に関わらせていただいております。業務量も入職したときよりも増え、あっという間に1日が終わってしまうことも多いですが、4月に設定した自分の目標の大切さを自分自身の体験で実感する出来事がありました。
 朝晩と冷え込むようになり、日中でも長袖を着るようになりました。早いもので今年も後2ヶ月程となり、月日が過ぎるのは本当に早いと感じています。
朝晩と冷え込むようになり、日中でも長袖を着るようになりました。早いもので今年も後2ヶ月程となり、月日が過ぎるのは本当に早いと感じています。
 9/19「敬老の日」に会わせて総務省より、65歳以上の3627万人(全人口の29.1%)となり過去最高を更新。100歳以上の高齢者も初めて9万人を超えました。
9/19「敬老の日」に会わせて総務省より、65歳以上の3627万人(全人口の29.1%)となり過去最高を更新。100歳以上の高齢者も初めて9万人を超えました。 伝えたりすることが、出来なくなると言われています。その命の危機が、いつ訪れるのかを予測することは困難です。そのため、自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むのかを自分自身で前もって考え、家族や周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。自身で考え、その思いを家族や信頼する人に伝えることで、自分自身の望む医療やケアを受け、最期を迎えることが出来るのです。
伝えたりすることが、出来なくなると言われています。その命の危機が、いつ訪れるのかを予測することは困難です。そのため、自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むのかを自分自身で前もって考え、家族や周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。自身で考え、その思いを家族や信頼する人に伝えることで、自分自身の望む医療やケアを受け、最期を迎えることが出来るのです。