通所リハビリの1フロアでの取り組みについてご紹介です。
 通所リハビリは利用者の身体・認知レベルに合わせて4つの部屋に分かれて、それぞれのスケジュールで過ごしています。1フロアは1日平均利用者数が90名程度の大規模なフロアです。大人数のフロアですが数年前より、利用者の身体機能にあわせて、3つのユニットに分かれています。日中は少人数に分かれた3つのユニット内で、それぞれ利用者のレベルに応じた体操やレクリエーションを提供しています。今年度は、よりリハビリ意識をもってプログラムが提供できるように、担当の介護スタッフが体操やレクリエーションの役割・目的などの勉強会を開き、理解を深めながらプログラムを行っている所です。
通所リハビリは利用者の身体・認知レベルに合わせて4つの部屋に分かれて、それぞれのスケジュールで過ごしています。1フロアは1日平均利用者数が90名程度の大規模なフロアです。大人数のフロアですが数年前より、利用者の身体機能にあわせて、3つのユニットに分かれています。日中は少人数に分かれた3つのユニット内で、それぞれ利用者のレベルに応じた体操やレクリエーションを提供しています。今年度は、よりリハビリ意識をもってプログラムが提供できるように、担当の介護スタッフが体操やレクリエーションの役割・目的などの勉強会を開き、理解を深めながらプログラムを行っている所です。
みなさん、「コグニサイズ」と聞いたらどんなものか、知っているでしょうか?最近は多くの部署で取り入れられていると思うので、どんなものか知っているかと思います。いままでは通所リハビリでも個々では行っていましたが、今年度改めてフロア全体で取り組むことになりました。
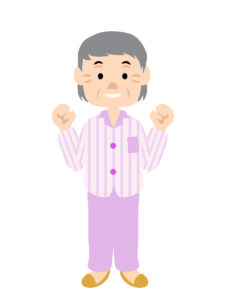 コグニサイズとは、国立長寿医療センターが開発した運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称です。どんな運動や認知課題でもよいとされていますが、次の2点が考慮されている内容が必要です。
コグニサイズとは、国立長寿医療センターが開発した運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称です。どんな運動や認知課題でもよいとされていますが、次の2点が考慮されている内容が必要です。
①運動は全身を使った中強度のもの(軽く息がはずむ・脈拍数が上昇する程度)
②運動と同時に実施する認知課題によって、運動の方法や認知課題自体をたまに間違えてしまう程度の負荷がかかっているもの(難易度の高い認知課題)
以上2点に気を付けながら、1フロアの利用者が「できそうだけど、ちょっと難しい!」
と感じられる課題を話し合いながら作成し行っています。
 実際に行ってみると、最初の動作は簡単なのでほとんどの方が出来ますが、動作が増えたり、複雑になってくると「ありゃ?!まちごぉ~たぁ!!」「もう!できんわぁ~(笑)」と言いながらも皆さん笑顔で取り組んでいます。
実際に行ってみると、最初の動作は簡単なのでほとんどの方が出来ますが、動作が増えたり、複雑になってくると「ありゃ?!まちごぉ~たぁ!!」「もう!できんわぁ~(笑)」と言いながらも皆さん笑顔で取り組んでいます。
スタッフは、「簡単すぎては意味がないので、間違えても大丈夫ですよぉ~」「間違えている今!脳が若返っています!」「スタッフの私も間違えましたぁ~(笑)」など言いながら進行していき、一緒にコグニサイズを楽しんでいます。
いつも集団体操は行っていない利用者が、コグニサイズはちょっとですがやっていたり、あまり表情のない方が笑顔で行われていたりと、コグニサイズを全体で取り組むようになって、よかったなぁと思います。
利用者様が自宅で出来るだけ長く、自分らしい生活を過ごせるようなサポートが行えるように1フロアのスタッフは考えています。「体操!」と言ったら高齢者の方には負担に感じられる方もいるので、コグニサイズのように楽しみながら身体を動かす機会を今後も増やせていけたらなぁと思います。
通所リハビリの1フロアは大人数で圧倒されるイメージですが、運動・脳トレ・リラックスタイムから創作・ゲーム・ボランティアまで、たくさんのプログラムを提供できるので、ご自分の好きな時間が見つけられるかと思います。ぜひ、お気軽にご連絡ください。見学・体験等お待ちしています。

通所リハ T
 9月のタイトルは「秋のコスモス畑」です。
9月のタイトルは「秋のコスモス畑」です。





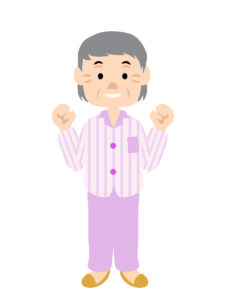











 今回は、Oさん(80歳)とNさん(75歳)のお二人が参加されました。Oさんは『ちびゴリラのちびちび』の絵本を読まれました。「歌ったんだって」「大きくなったんだって」とアドリブも加え、語りかけるような朗読に園児たちは引き込まれるように聞き入っていました。Nさんは『やさいさん』の絵本を読まれました。テンポの良い朗読に、園児たちも「やさいさん、やさいさん」と楽しそうに声を合わせ、とても和やかな雰囲気でした。最後に園児より手作りの首飾りをプレゼントしていただき、一人一人と握手をして、楽しいひと時を過ごしました。
今回は、Oさん(80歳)とNさん(75歳)のお二人が参加されました。Oさんは『ちびゴリラのちびちび』の絵本を読まれました。「歌ったんだって」「大きくなったんだって」とアドリブも加え、語りかけるような朗読に園児たちは引き込まれるように聞き入っていました。Nさんは『やさいさん』の絵本を読まれました。テンポの良い朗読に、園児たちも「やさいさん、やさいさん」と楽しそうに声を合わせ、とても和やかな雰囲気でした。最後に園児より手作りの首飾りをプレゼントしていただき、一人一人と握手をして、楽しいひと時を過ごしました。


