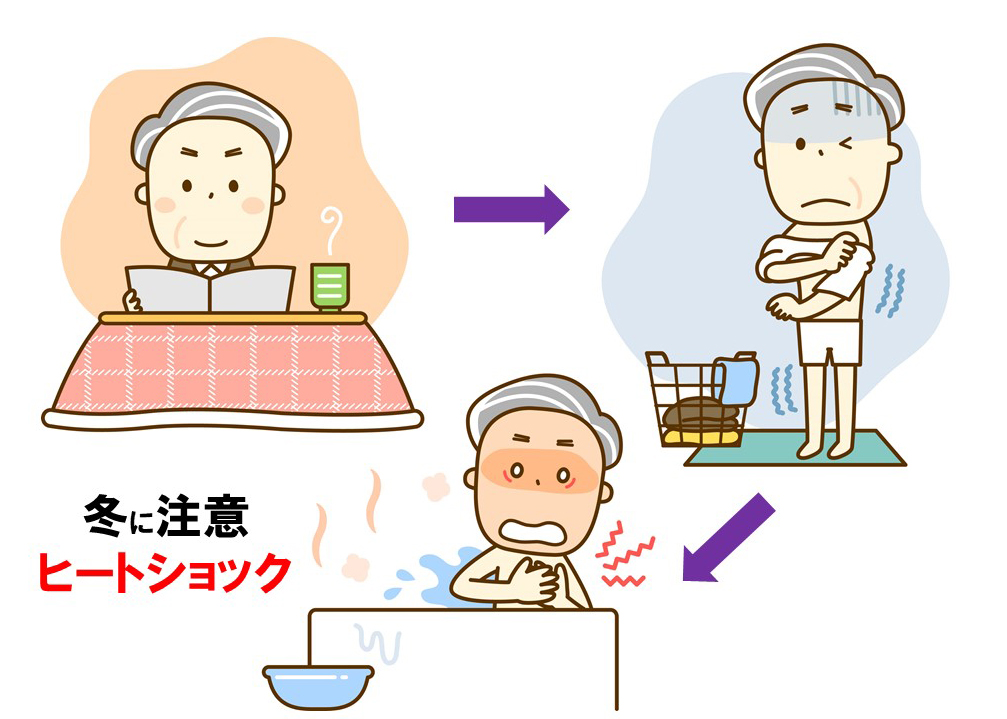訪問看護ステーションに異動し、1年が過ぎました。車での移動中、窓を開けると季節の移ろいを感じることができます。春のうららかな陽気、夏の刺すような日差し、秋の空の高さ。最近では高梁川河原一面にススキが陽の光を受けてキラキラと輝いています。また冷たくなってきた風に冬の気配を感じます。
訪問看護ステーションに異動し、1年が過ぎました。車での移動中、窓を開けると季節の移ろいを感じることができます。春のうららかな陽気、夏の刺すような日差し、秋の空の高さ。最近では高梁川河原一面にススキが陽の光を受けてキラキラと輝いています。また冷たくなってきた風に冬の気配を感じます。
ご自宅にはその家そのものの歴史、患者さんご自身の思い出や想いが詰まっているように感じます。
季節ごとの花や小物を飾られていたり、自身の作品で溢れていたり、ご自身の子供さんだけでなくお孫さんや曾孫さんなどご家族の写真が所狭しと並べられていたりなど、見ているこちらが心温まることが多いです。
またご自宅そのものが先祖代々のものであることや自分たちが苦労して建てた家であることなど並々ならぬ思いを持たれている方もたくさんおられます。そのお家で一日でも長く生活したい、その気持ちが常に溢れているように思います。
ご自宅に伺ってリハビリをさせてもらうことは、その方の領域に入り込むことであって、最初は私自身がその状況に慣れず、私に何ができるか迷い悩んだこともありましたが、
「体が楽になったよ。」
「この前外出したけど、痛みがなく歩けたよ。」
「手すりのおかげで玄関が上がりやすくなったよ。」などのお声掛けにより、ご自宅でリハビリを提供できることに楽しさを感じることができるようになりました。利用者様はやはりいくつになっても少しずつ変化されます。その変化にお互いが気づいたとき、その喜びは倍になります。長期的な関わりになるからこそ、気づけることなのかなと思います。
ご利用者様の中には、なかなか外出できない方もおられます。そういった方には出来るだけ季節の移ろいを具体的にお伝えするようにしています。一人暮らし等であまりお話しすることがない方にはなるべくたくさんお話しし、笑顔で過ごせるようにリハビリを進めています。
一日でも長く安全に、ご自宅で過ごしていただくために。時にはきついリハビリが少しでも楽しいものとなるように。
今日も季節を感じながら、訪問車を走らせます。
「おはようございます。訪問リハビリに伺いました!」
訪問看護ステーション PT(理学療法士) H

 ※写真はイメージです
※写真はイメージです
 ちょっと気分転換。「今日は何の日なぞなぞ」の出題です‼
ちょっと気分転換。「今日は何の日なぞなぞ」の出題です‼

 4月になり、日中は半袖で過ごせるくらい暖かくなりました。季節の変わり目真っ只中ですが、みなさん体調は崩されていないでしょうか?
4月になり、日中は半袖で過ごせるくらい暖かくなりました。季節の変わり目真っ只中ですが、みなさん体調は崩されていないでしょうか? こんにちは。3月に入ってやっと暖かく感じる日が多くなってきましたね。ついこの間2022年を迎えたと思っていましたが・・・。年始からコロナ禍に入り気持ちが落ち着かなかった日が続きモヤモヤした日々を過ごしている中で感じた事。コロナ禍第6波の中で私達訪問看護での感染対策の日ごろの取り組み、日々の様子についてとその中で感じている事を少しお話したいと思います。
こんにちは。3月に入ってやっと暖かく感じる日が多くなってきましたね。ついこの間2022年を迎えたと思っていましたが・・・。年始からコロナ禍に入り気持ちが落ち着かなかった日が続きモヤモヤした日々を過ごしている中で感じた事。コロナ禍第6波の中で私達訪問看護での感染対策の日ごろの取り組み、日々の様子についてとその中で感じている事を少しお話したいと思います。