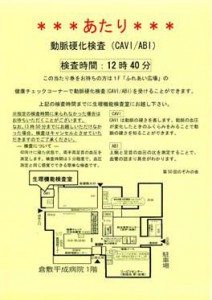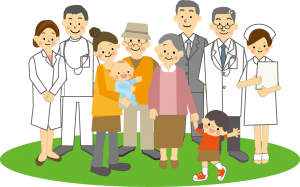昨年末より、今季は暖冬だと言われ続けスキー場も通常営業できない程でしたが、
先月、約40年ぶりと噂された大寒波が訪れ、野菜や魚などの高騰化に悩まされました。
それと同時に、気温の急激な変化によって体調を崩され、発熱やインフルエンザで受診される患者さんが急激に増えたように感じます。
「寒くなるし、風邪引かんようにせんといけんなあ~。」
と、職員と話していた時、ふと私が小学校低学年の頃に抱いていた素朴な疑問を思い出しました。
「暖かい時は風邪を引かなくて、寒くなると風邪を引くのはなんでだろう・・・。」
みなさんは疑問に思ったことはありませんか?
当時はそんなことより遊びの方が重要だった私は調べもせず、その疑問を抱いていたことさえすぐに忘れてしまいました。
ですが、今回ブログを書く機会を頂いたので、この場をお借りして十何年か越しに当時のモヤモヤを解消させたいと思います。
“寒くなると風邪を引く”には、主に2つの原因があります。
1つ目は、ウイルスは低温・低湿な環境が大好きということです。
ウイルスは基本的に熱に弱いので、寒くなると、特に15度以下でウイルスはとても過ごしやすく元気になります。また、湿度が高いとチリやほこりと一緒に地面に落ちてしまうのですが、冬はとても乾燥しているため、空気中を飛び回ります。
なので、活発な上に空気中を漂って人の体内に侵入する量が増えるので、感染しやすくなるのです。
2つ目は、免疫力の低下です。
実は、人は体温が1度下がると、免疫力が約30%以上も低下してしまいます。
そのメカニズムは、体温が下がると血流が悪くなるだけではなく、免疫を担当している白血球の動きが鈍くなります。そのため、体内に細菌やウイルスなどの異物を発見しても、本来なら素早く集まって駆除してくれるはずの白血球が集まりにくく、攻撃も鈍くなり、ウイルスや細菌に負けて風邪などを発病してしまうということです。
逆に、体温が1度上がると免疫力は約60%上がるそうです。
今まで、ただ単に寒いと風邪を引くと言ってきましたが、実はこんなしっかりとした科学的根拠があったようです。
小学校低学年の頃の私には難しかったでしょう。
私は普段薄着でいることの方が多いのですが、体温が1度下がるだけで免疫力が約30%以上も下がるということは初耳でした。
特に私に言えることですが、みなさんも体調を崩さないように、家の中でも外でも暖かい格好を心がけましょう。
また、暖房をつけていると、つけていない時よりも湿度が約30%も下がるとエステティシャンの友人から聞きました。加湿器でしっかりと湿度を上げ、定期的に換気を行ってウイルスを室内から追い出しましょう。
さらに、寝不足、栄養不足にならないようにしっかり体調管理を行うことも免疫力を下げないためにとても大切です。
もうすぐ春ですが、ウインタースポーツやおいしい食べ物、バレンタインデーなど、まだまだ冬に楽しみたいことはたくさんあります。
体調管理を常に心がけ、楽しく冬を過ごしましょう!!
臨床検査部 M・T