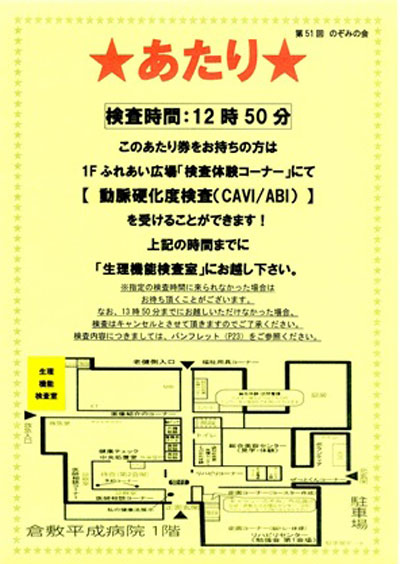皆さんこんにちは!最近はかなり冷え込むようになり、ついに冬本番という感じになりましたね。当院でも発熱で受診される患者さんも増えてきたように思います。手洗い、うがい、乾燥対策等をして体調管理には充分お気をつけください。
皆さんこんにちは!最近はかなり冷え込むようになり、ついに冬本番という感じになりましたね。当院でも発熱で受診される患者さんも増えてきたように思います。手洗い、うがい、乾燥対策等をして体調管理には充分お気をつけください。
さて、私事ですが先日高知市で開催された第49回中四国支部医学検査学会に参加し、演題発表をさせて頂きました。臨床検査技師になって4年目になりますが、学会で発表するのは初めてのことだったので自分に務まるのだろうかと不安でしたが、準備を進めていく中で新たに得る知識があったり、時には先輩方にアドバイスを頂きながら順調に本番を迎えることができました。当日は少し緊張しましたが無事に発表を終えることができ、本当にほっとしました。また、他院の発表を聞いて勉強になることもたくさんあり、とても良い刺激を受けました。
また、特別講演で「生き方雑記帳 2016」と題して小説家の山本一力先生のお話を聴く機会がありました。その中で、ご自身の検査体験や通院している中で、検査があったから今の自分があると力説されており、「臨床検査技師という職業はあまり知る機会が無いが、とても尊いことであって自信を持ってこれからも頑張って欲しい」という言葉にとても励まされました。
今回の学会で、普段の業務の中で学ぶ事とはまた違う臨床検査技師のやりがいを感じ、私にとってこれからの糧となる貴重な経験となりました。
臨床検査技師 M