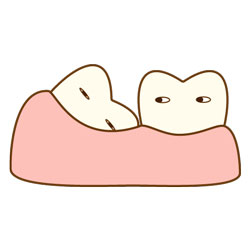先日知り合いのお子さんの乳歯が初めて抜けたと嬉しそうに報告がありました。
今では、抜けた乳歯を大切に保管するケ-スもたくさん売られていて、最近のお母さんはそのケ-スの中に抜けた乳歯を保管しているそうです。
私達の子供の頃は、「ネズミの歯と変えとくれ~」と言いながら、上の歯は床下に、下の歯は屋根上に投げたものです。これは、ネズミの歯が後ろから後ろから伸び続けることにあやかったことだそうです。
欧米では抜 けた乳歯を袋に入れ、枕の下において眠ると「Tooth Fairy(歯の妖精)」が抜けた歯を集めに来てくれるという言い伝えがあるそうです。この集めた歯の代わりにコインを置き、このTooth Fairyは、健康な白い歯だけを集めにくるので、歯を磨かない子や、抜けた歯が虫歯の場合はTooth Fairyはやってきません。
けた乳歯を袋に入れ、枕の下において眠ると「Tooth Fairy(歯の妖精)」が抜けた歯を集めに来てくれるという言い伝えがあるそうです。この集めた歯の代わりにコインを置き、このTooth Fairyは、健康な白い歯だけを集めにくるので、歯を磨かない子や、抜けた歯が虫歯の場合はTooth Fairyはやってきません。
欧米では「歯を磨かないと妖精がこないわよ。」と親が子供に言い聞かせながら歯を磨く動機づけをしているそうです。
また、メキシコヤフランス・スペインなどでは、枕の下に置いた乳歯はちびネズミが持ってかえり、代わりにプレゼントを置いていってくれるそうです。慣習は国によって大きく変わりますが、子供の健やかな成長を願う気持ちはどの国も共通しています。
歯科 コバ子

 スとはさまざまな要因で唾液の分泌量が低下し、お口の中が乾燥する病気です。加齢に伴い唾液腺が萎縮するなど唾液腺自体に問題がある場合や、糖尿病や腎不全などの病気に関連して起こる場合、シェーグレン症候群、ストレス、薬剤の副作用で起こることもあります。
スとはさまざまな要因で唾液の分泌量が低下し、お口の中が乾燥する病気です。加齢に伴い唾液腺が萎縮するなど唾液腺自体に問題がある場合や、糖尿病や腎不全などの病気に関連して起こる場合、シェーグレン症候群、ストレス、薬剤の副作用で起こることもあります。


 毎年この時期になると、歯科の診療室から見える保育園の運動会の練習を子供達が頑張っていて、年長さんの鼓笛の演奏も日に日に上達し、毎日癒されています。我が家の次男も2歳6カ月で毎日運動会の練習を頑張っているみたいで、夜はすぐ寝入ります。
毎年この時期になると、歯科の診療室から見える保育園の運動会の練習を子供達が頑張っていて、年長さんの鼓笛の演奏も日に日に上達し、毎日癒されています。我が家の次男も2歳6カ月で毎日運動会の練習を頑張っているみたいで、夜はすぐ寝入ります。 歯には、虫歯菌に溶かされた部分を元に戻そうとする“再石灰化”いう働きがあり、唾液の中には再石灰化に必要なミネラルが含まれていますが、夜の睡眠中は唾液の分泌が少なくなります。そのため、夜間は歯の再石灰化が進まず、虫歯になりやすくなるのです。ぜひ、歯磨きが苦手なお子さんにも寝る前は清潔なガ-ゼを指に巻き歯を拭いてあげたり、大人が仕上げ磨きをするなど、寝る前に歯をしっかりきれいにしてあげてください。
歯には、虫歯菌に溶かされた部分を元に戻そうとする“再石灰化”いう働きがあり、唾液の中には再石灰化に必要なミネラルが含まれていますが、夜の睡眠中は唾液の分泌が少なくなります。そのため、夜間は歯の再石灰化が進まず、虫歯になりやすくなるのです。ぜひ、歯磨きが苦手なお子さんにも寝る前は清潔なガ-ゼを指に巻き歯を拭いてあげたり、大人が仕上げ磨きをするなど、寝る前に歯をしっかりきれいにしてあげてください。