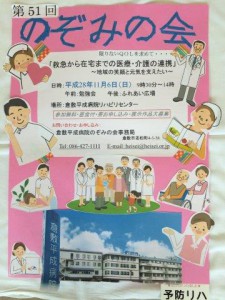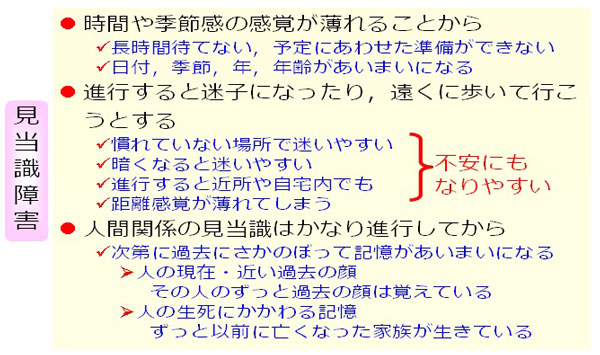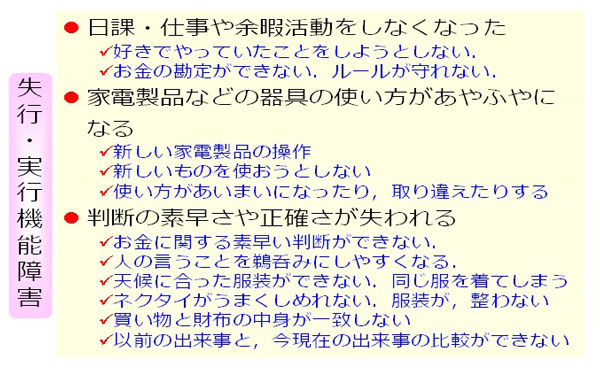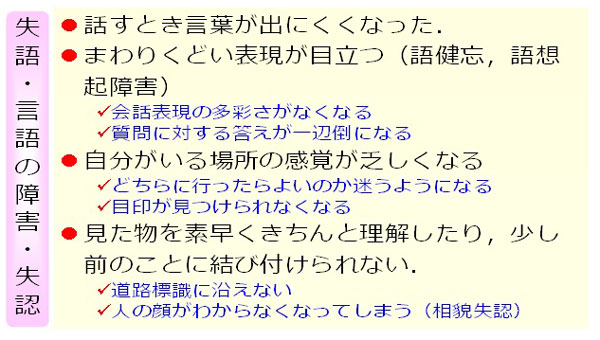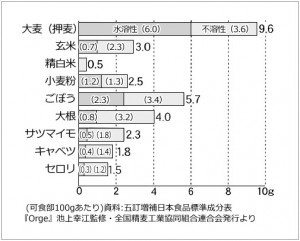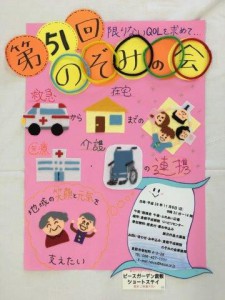私事ですが糖尿病療養指導士の資格をとって早4年、あっという間に今年が更新の時期になりました。更新をするためには、各地で開催されている研修会・学会に出席し単位をとらなければなりません。
私事ですが糖尿病療養指導士の資格をとって早4年、あっという間に今年が更新の時期になりました。更新をするためには、各地で開催されている研修会・学会に出席し単位をとらなければなりません。
単位は1単位~4単位もらえるものまで様々あり、計40単位の取得が条件の1つになります。
マイペースな私は今年に入り隔月でどこかの勉強会に参加し単位取得に明け暮れています。先日は徳島県で開催された第16回中四国糖尿病研修セミナーに行ってきました。
6時間30分という長丁場、座りっぱなしでの聴講は病院での看護業務とは違い学生に戻った気分になりましたが、やっぱりしんどかったです。
しかし、「患者に資し地域に活きる糖尿病チーム医療」という今回のテーマのもと、地域に貢献する糖尿病療養指導、高齢糖尿病患者への実践的対応、糖尿病腎症予防を実現するための専門的な技術や情報を中心にたくさんの話が聞けました。
岡山からは岡山大学病院の長田看護師が岡山県における糖尿病医療連携の取り組みという講演で、「おかやま糖尿病サポーター」の認定と役割について学ぶことができました。これはかかりつけ医や調剤薬局など、より地域に密着した施設で働くメディカルスタッフに糖尿病療養指導の知識と技術を身につけてもらうことを目的に認定された制度だそうです。
また、高齢糖尿病患者のインスリン療法導入、継続のための支援や食事療法、薬物療法についてのシンポジウムでは、私も病棟で高齢の糖尿病患者さんに接することが多いので指導に携わる中で活かしていきたいと思えるものがたくさんありました。
個人的には徳島大学の黒田医師がご自身の経験のもと1型糖尿病の治療の現在と未来について話して下さったのが、すごく分かりやすかったです。
さらに、企業の共催ブースでは患者さんにわかりやすい資料やパンフレットを拝見し、サノフィはインスリンのペンを滑りにくくするカラフルなゴムを展示していました。サンスターから歯周病についてブラシを使用した歯間ケアの必要性を、大塚食品からは食事コントロールのためにレトルト食品をうまく役立てようと100kcalシリーズの紹介をするなど、前回よりも新しい情報もたくさんあり楽しく学べ、無事2単位取得して帰りました。今後の療養場面で活かしていけるようにこれからも頑張りたいと思いました。
4西 NS T