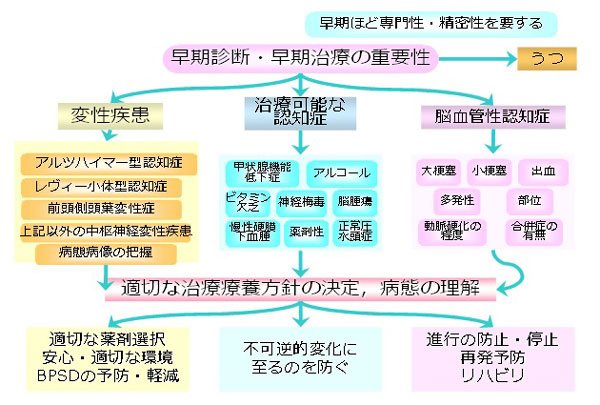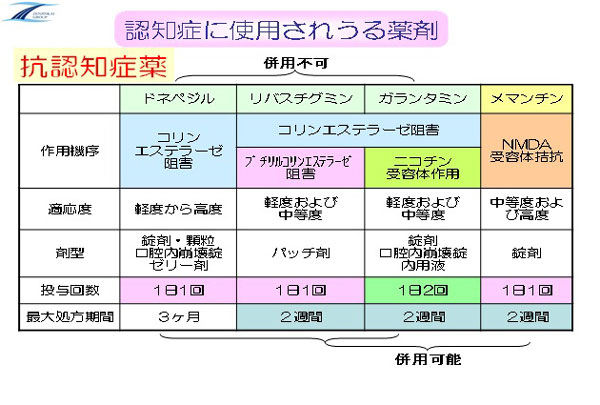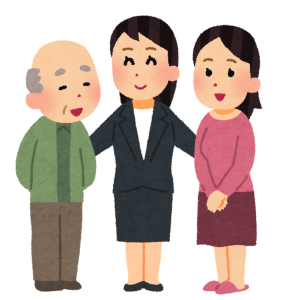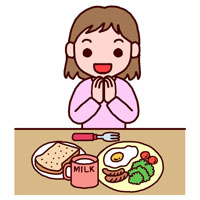早いものでもう12月です。12月から1月にかけて忘年会に始まり、クリスマス、年末年始、新年会などイベントが目白押しです。この時期は食生活が乱れやすくついつい食べ過ぎてしまうという方が多いのではないでしょうか?
糖尿病のコントロール指標でもあるHbA1cは血糖の過去1、2ヶ月間の平均を表すので、食べ過ぎてしまった12月~1月の結果は2月~3月の血液検査に反映されてきます。
今回は年末年始の食生活の注意点についてお話ししたいと思います。
まず、忘年会。1回ではなく何件も掛け持ちという方が多いと思います。
居酒屋だと料理が大皿盛で提供されます。小皿に少しずつ取って食べるようになるので、どれくらい食べたか分からずついつい食べ過ぎてしまってはいませんか?
まずはメニューの把握をしておきましょう。何品、どんな内容のものが出てくるのか知っておけば、メニューによって食べる量を配分できます。
また、揚げ物などの高脂肪のものやフライドポテトやパスタなどの炭水化物の料理が多く、どうしても野菜を食べる量が少なくなってしまいます。忘年会に出かける前の昼食や翌日の食事でしっかり野菜を食べるようにしましょう。
 次にお正月には欠かせないお餅とおせち料理です。おせち料理は日持ちがするように砂糖や醤油で煮込んでいて味付けが濃くなっているものが多く、塩分やカロリーも高くなっています。おせちのなかでも、栗きんとん、くわい、レンコン、黒豆はヘルシーなようで炭水化物が多いので食べ過ぎには気をつけましょう。
次にお正月には欠かせないお餅とおせち料理です。おせち料理は日持ちがするように砂糖や醤油で煮込んでいて味付けが濃くなっているものが多く、塩分やカロリーも高くなっています。おせちのなかでも、栗きんとん、くわい、レンコン、黒豆はヘルシーなようで炭水化物が多いので食べ過ぎには気をつけましょう。
皆さんはお餅のカロリーをご存知ですか?なんと100gあたり約240kcalもあります。ご飯だと100g、160kcalです。市販の切り餅(各メーカーによって違いがあります)はだいたい1個50gくらいなので、お餅を食べる目安は2個くらいまでにしておくといいでしょう。ご自宅で餅つきをして、自分たちで丸める方もいらっしゃると思います。そうすると1個がかなり大きいお餅になってしまうので食べる前に量りましょう。
もち米は、ご飯のうるち米より血糖が上がりやすいので糖尿病の方は特に気をつけましょう。
冬の時期に食べ過ぎると、花粉症のある人は症状がきつくなるという話もあります。できる事から少しずつ気をつけて楽しい12月をお過ごしください。
糖尿病療養指導士 管理栄養士 S.N