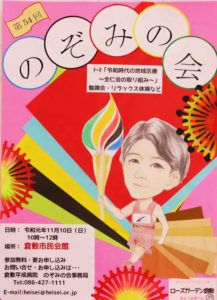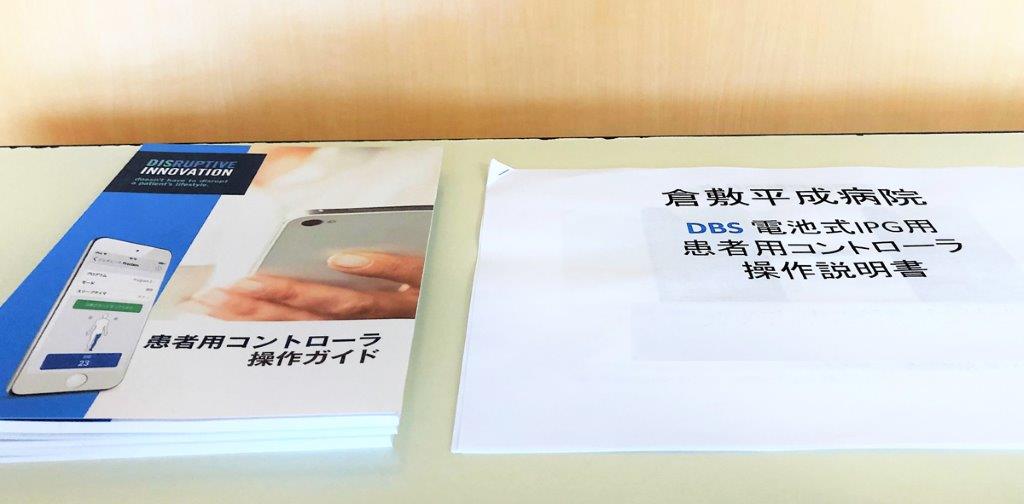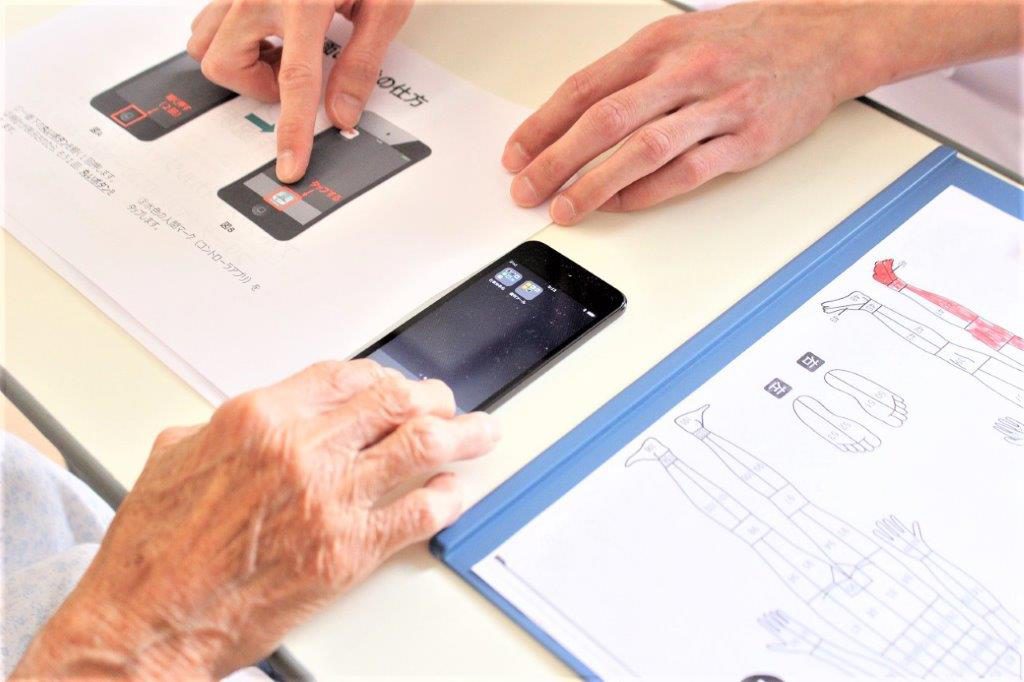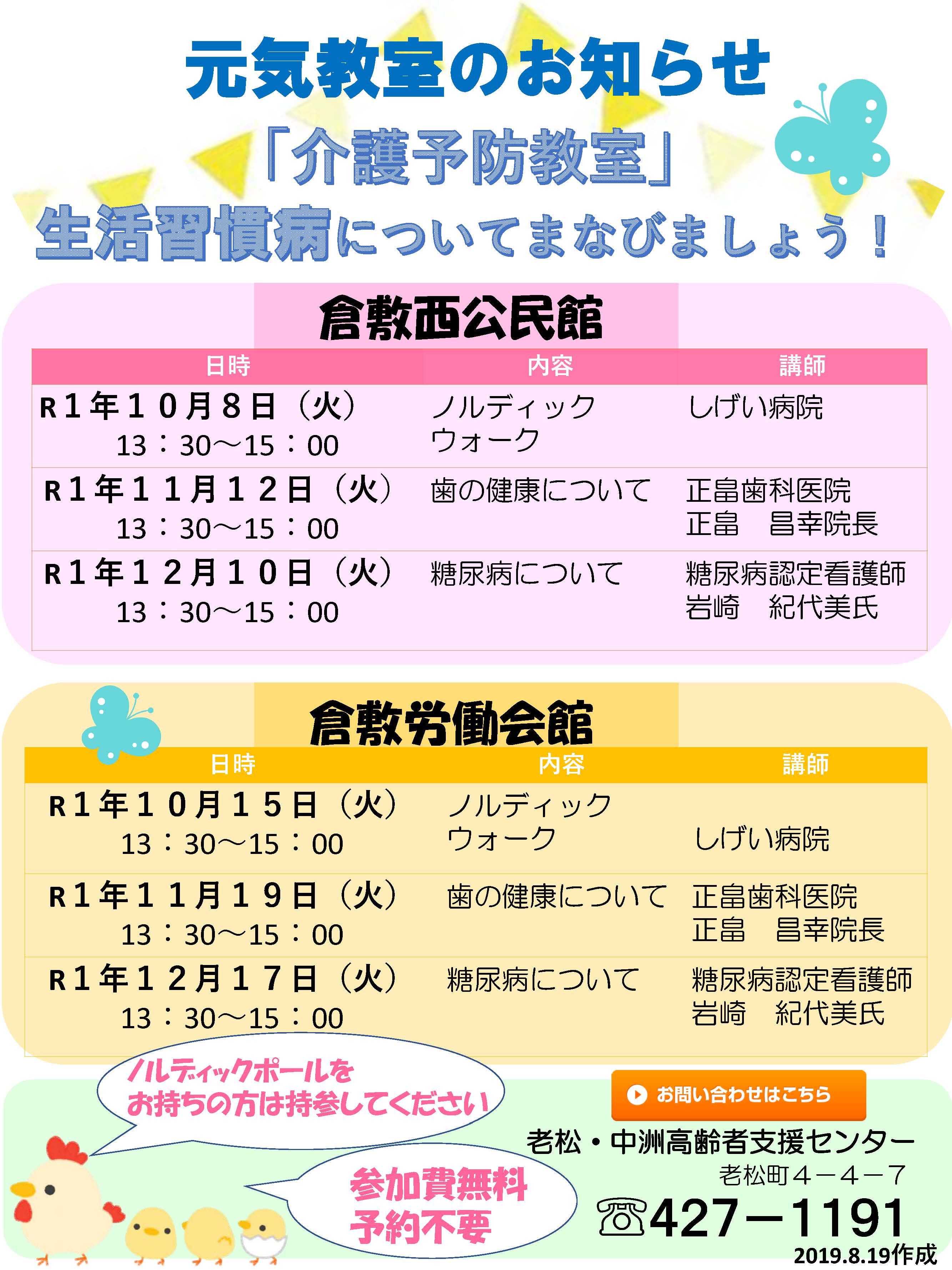10月5日(土)に全仁会グループ主任副主任研修を開催しました(総勢75名参加)。
10月5日(土)に全仁会グループ主任副主任研修を開催しました(総勢75名参加)。
 今回、倉敷青年会議所より松本昌彦氏と熊本雄介氏を講師にお招きし、『カードゲームで学ぶSDGs~2030 SDGs~』と題しご講演いただきました。
今回、倉敷青年会議所より松本昌彦氏と熊本雄介氏を講師にお招きし、『カードゲームで学ぶSDGs~2030 SDGs~』と題しご講演いただきました。
SDGsとは「持続可能な開発目標」のことで、2030年までの世界をより良くするために「誰一人取り残さない世界の実現」を目指し、社会・環境・経済をめぐる課題に取り組むための国際的な目標です。
 カードゲームの内容はとても奥深く、ゴールの達成にはチーム同士での協力も不可欠で、体験をしながらSDGsへの理解を深めることができました。またグループワークでは、全仁会の取り組みがSDGsの「17の目標」にどう当てはまるかを考えました。
カードゲームの内容はとても奥深く、ゴールの達成にはチーム同士での協力も不可欠で、体験をしながらSDGsへの理解を深めることができました。またグループワークでは、全仁会の取り組みがSDGsの「17の目標」にどう当てはまるかを考えました。
普段の業務がSDGsの掲げる目標に多く関わりがあることがわかり、個々の意識が変わるきっかけになったと思います。夜は懇親会を開き、部署を超えて主任・副主任同士で交流を深めました。
この研修で、SDGsは管理職として業務に当たる上で重要な考え方だと感じました。今後は、目標達成のため自らが起点となり、行動に移せるよう意識していきたいです。
人事課 H