 7月も下旬になり本格的な猛暑の到来ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
7月も下旬になり本格的な猛暑の到来ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
未だ減らないコロナ感染。暑さと感染症対策の両立が日に日に難しくなってきているように感じます。
さて、私事ですが先月第1子が生まれました。性別は待ち望んでいた女の子でした。出生時は未熟児で心配をしましたが、現在はしっかりミルクも飲みすくすく成長しています。
日に日に成長していく姿をみて毎日メロメロの日々を送っております。
早いもので7月21日で1ヶ月を迎えました。子供の成長は早いと言いますが、本当にその通りだなと感じております。
しっかり成長過程を記録していきたいと思います。
生活環境の変化は楽しみでもありますが、同時に不安や心配もつきものだと思います。
突如発生する病気や怪我も生活環境に大きな影響を与えます。
我々MSW(社会福祉士)は入院中の療養相談はもちろんのこと、退院後の生活について患者さん・ご家族が少しでも安心して生活を送れるようお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。
厳しい暑さがまだまだ続いていきますので、水分補給を十分に行って行くと共に感染対策もにもお気を付けてお過ごし下さい。
地域医療連携センター 相談室のペリカン

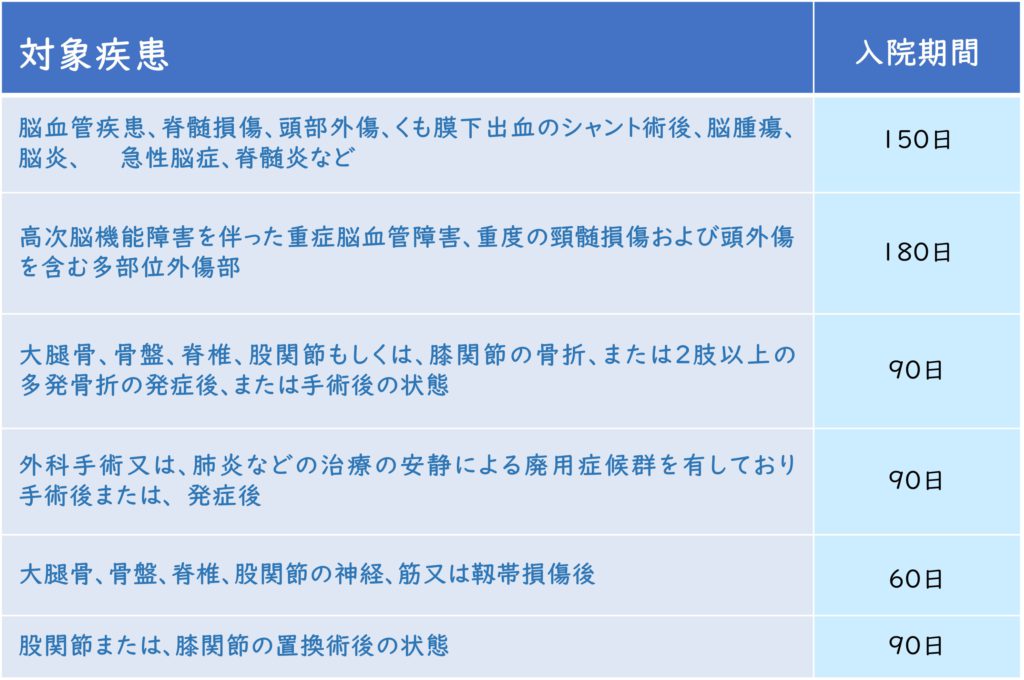

 令和4年度がスタートしました。
令和4年度がスタートしました。 私の所属する
私の所属する 私事ですが、我が家の娘は3月で保育園を卒園、4月にはピカピカの1年生です。ランドセル、制服、学習用品など着々と準備を進めていますが、「うちの子が勉強についていけるのか。新しい環境に馴染めるのか」今から心配で仕方ありません。本人も「友達が出来なかったらどうしよう」と度々つぶやき、不安いっぱいの様子です。
私事ですが、我が家の娘は3月で保育園を卒園、4月にはピカピカの1年生です。ランドセル、制服、学習用品など着々と準備を進めていますが、「うちの子が勉強についていけるのか。新しい環境に馴染めるのか」今から心配で仕方ありません。本人も「友達が出来なかったらどうしよう」と度々つぶやき、不安いっぱいの様子です。 突然起こる病気や怪我もまた、大きな環境や生活の変化をもたらします。私たち医療ソーシャルワーカーは、病気や怪我により、今までとは異なる状況に不安を感じている患者様やそのご家族が、少しでも安心して入院生活、退院後の生活を送れるようにサポート致します。
突然起こる病気や怪我もまた、大きな環境や生活の変化をもたらします。私たち医療ソーシャルワーカーは、病気や怪我により、今までとは異なる状況に不安を感じている患者様やそのご家族が、少しでも安心して入院生活、退院後の生活を送れるようにサポート致します。 さて、私事ですが先日、日本医療ソーシャルワーカー協会が主催するオンライン研修に参加しました。そこでは日本全国に勤務する3年未満の医療ソーシャルワーカーが参加しておりグループワークを通して様々な意見交流が出来ました。
さて、私事ですが先日、日本医療ソーシャルワーカー協会が主催するオンライン研修に参加しました。そこでは日本全国に勤務する3年未満の医療ソーシャルワーカーが参加しておりグループワークを通して様々な意見交流が出来ました。
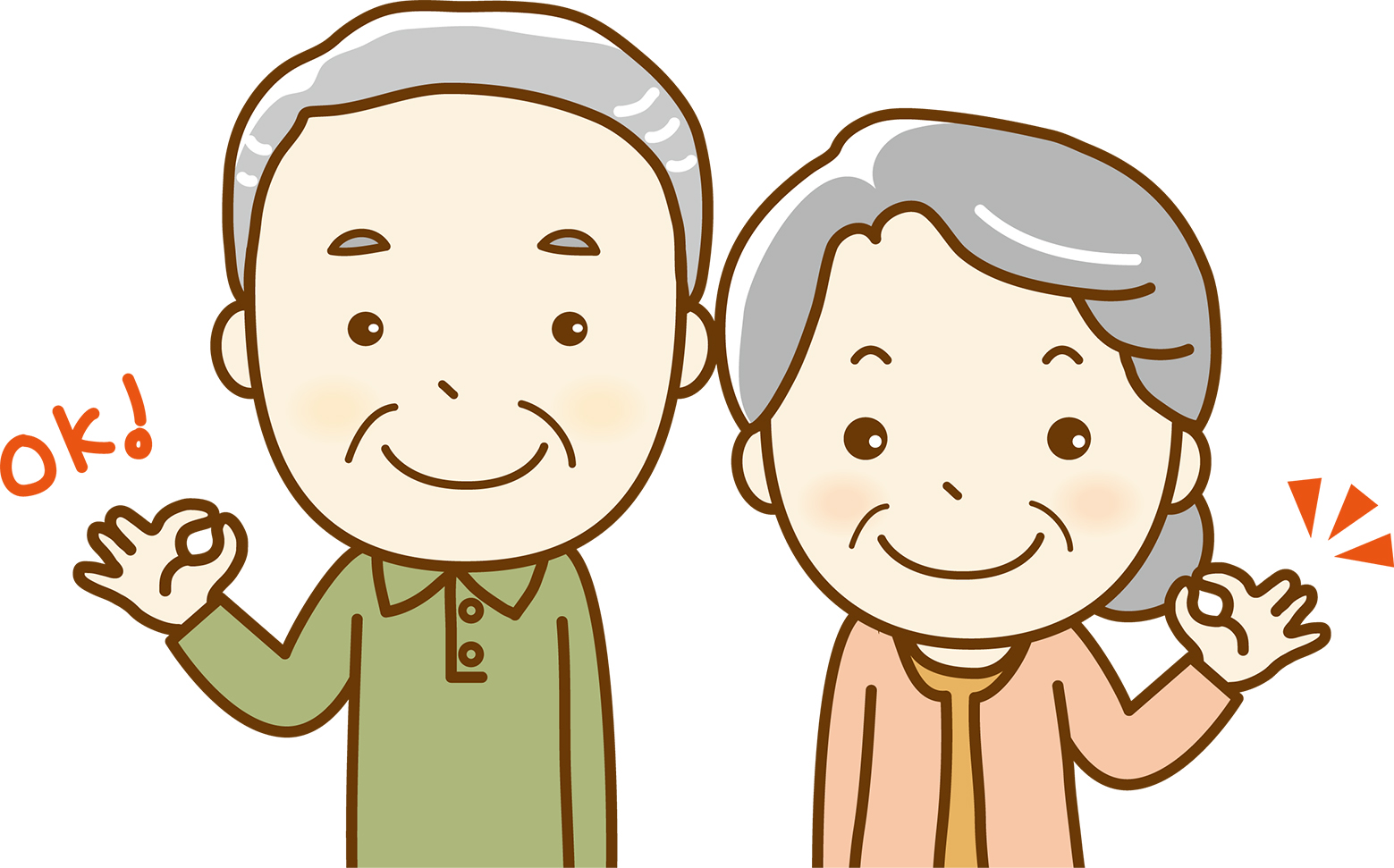 季節はだんだんと冬に近づき、朝晩の冷え込みが厳しい時期になりました。
季節はだんだんと冬に近づき、朝晩の冷え込みが厳しい時期になりました。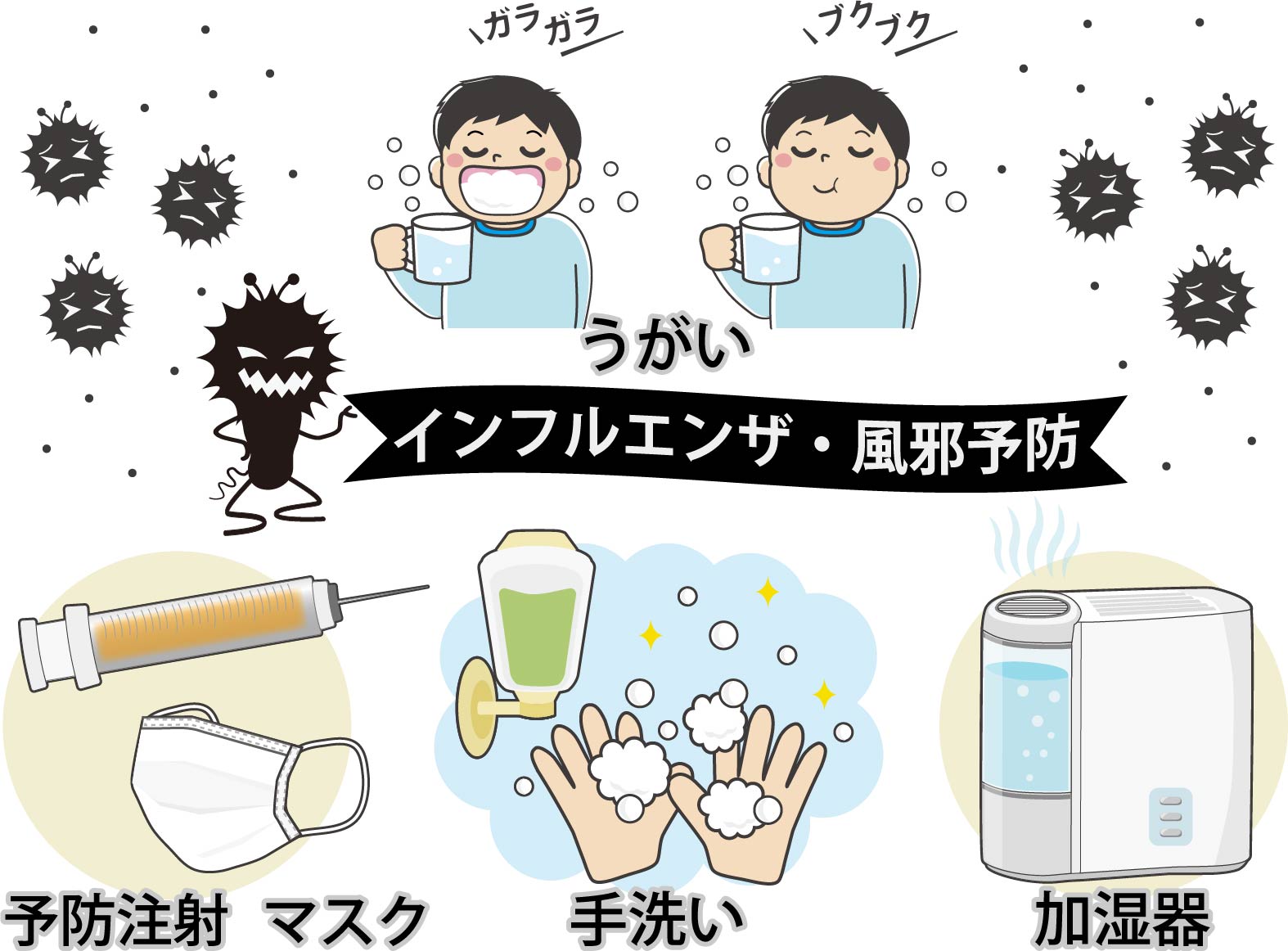 10月も終わりを迎えようとし、急激に寒くなってきました。現在新型コロナウィルスは感染者数が減少し、東京都でも飲食店の時短要請が解除されている等嬉しいニュースが報道されています。しかし寒くなってくるこの時期から流行拡大してくるインフルエンザにも注意が必要です。
10月も終わりを迎えようとし、急激に寒くなってきました。現在新型コロナウィルスは感染者数が減少し、東京都でも飲食店の時短要請が解除されている等嬉しいニュースが報道されています。しかし寒くなってくるこの時期から流行拡大してくるインフルエンザにも注意が必要です。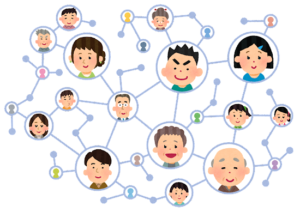 地域医療連携センターは様々な依頼やご相談を病院の内外からお受けしている部署です。
地域医療連携センターは様々な依頼やご相談を病院の内外からお受けしている部署です。