9月に入り猛暑がまだまだ続きそうですが、皆様体調を崩されていませんでしょうか?
先日、暑さと歯の痛みで目が覚めました。
歯の痛みと言えば大体思い浮かぶのが、虫歯で痛い又歯槽膿漏で歯の周りの歯茎が痛いなどがあると思います。
今回の私の歯の痛みは間違いなく就寝中の歯のくいしばりだと思っていました。前から家族に寝ながら歯ぎしりが激しいと指摘もうけていたのと、自分自身でもわかるほど就寝中に食いしばりをし

てる事がわかっていたからです。
一般的に人の噛む力や食いしばった時の力は自分の体重と同程度の力が歯にかかると言われています。普段の食事中は無意識でも噛む力をコントロールしているため痛みがでる事はないといわれています。
しかし、就寝中は無意識の中でも火事場の馬鹿力で歯をすり合わせているため研究ではこの時に奥歯にかかる力は体重の2倍になるとも言われています。
この力が毎晩かかれば歯が割れないにしても、歯にヒビが入ったり、歯茎や歯にダメージを与えてしまいます。
自分は歯ぎしり、食いしばりをしているのかな?と思ったらお口の中でチェックできるので見てみてください。
頬粘膜(ほっぺた)の内側に白い筋があったり、舌のわきがボコボコになっていたりします。 もしも上記の症状や痛みなどがある場合はまず日中でも気づいたら顎の力を抜いて上下の噛み合わせている歯を離してみて下さい。また就寝時はマウスピースを装着をお勧めします。
歯科 k

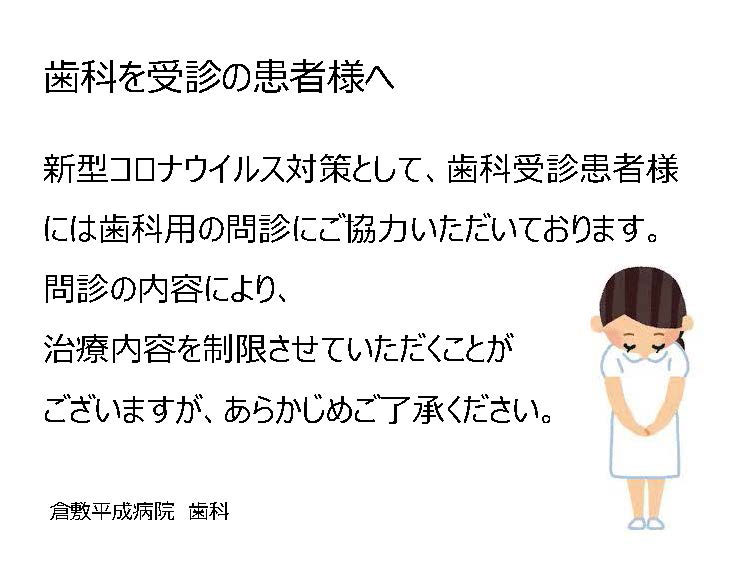
 現在、倉敷平成病院では、多くのフロアの改築工事がされていますが、このたび歯科の診療チェアーも最新機器にリニューアルし、7月27日(月)から、新チェアーでの診療が開始されました。
現在、倉敷平成病院では、多くのフロアの改築工事がされていますが、このたび歯科の診療チェアーも最新機器にリニューアルし、7月27日(月)から、新チェアーでの診療が開始されました。


 歯科でのエアロゾルとは、唾液、血液、義歯などの切削片、タ-ビンなど回転器具の冷却水などを含む霧状の汚染水などです。特に虫歯などに使用するタ-ビンからの冷却水は広範囲に飛び散ると言われています。
歯科でのエアロゾルとは、唾液、血液、義歯などの切削片、タ-ビンなど回転器具の冷却水などを含む霧状の汚染水などです。特に虫歯などに使用するタ-ビンからの冷却水は広範囲に飛び散ると言われています。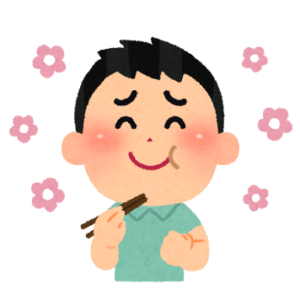

 た・・・私が歯科衛生士になりたての頃、患者さんから“看護師さん”と呼ばれたことが何度もありました。その時は少しビックリしつつ、ああ歯科衛生士という職業は、世間にはまだまだ知られていないんだと痛感したものでした。
た・・・私が歯科衛生士になりたての頃、患者さんから“看護師さん”と呼ばれたことが何度もありました。その時は少しビックリしつつ、ああ歯科衛生士という職業は、世間にはまだまだ知られていないんだと痛感したものでした。 今年は暖冬といわれていますが、寒さが厳しい日が続いています。
今年は暖冬といわれていますが、寒さが厳しい日が続いています。