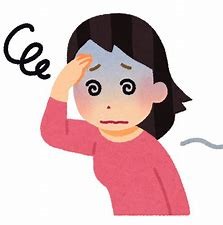 最近疲れやすい、顔色が悪い、そんな悩みを抱えている方はいませんか?それは貧血が原因かもしれません。今回は貧血予防の食事についてご紹介します。
最近疲れやすい、顔色が悪い、そんな悩みを抱えている方はいませんか?それは貧血が原因かもしれません。今回は貧血予防の食事についてご紹介します。
貧血のほとんどが鉄の不足によりヘモグロビンの産生が低下して起こる「鉄欠乏性貧血」です。体内で鉄が不足する原因は、鉄の摂取不足、胃切除や胃酸分泌低下などによる鉄の吸収低下、月経過多、潰瘍、痔など失血による鉄の排泄増加など様々ですが、体内で不足した鉄は補わなくてはなりません。そこで基本となるのが食事療法です。今回は、貧血の食事療法のポイントを紹介します。
①鉄をとりましょう。
食品に含まれる鉄は、肉・魚・レバーなど動物性食品に含まれるヘム鉄と、野菜・海藻・大豆など植物性食品に含まれる非ヘム鉄があります
非ヘム鉄は吸収されにくいですが、
ビタミンC(果物、いも類)、動物性たんぱく質(肉類、魚類、卵類、乳製品)などと
組み合わせることで吸収が促進します。
②たんぱく質をとりましょう。
たんぱく質は、赤血球やヘモグロビンの材料となる栄養素なので鉄と同様に大切です。
③ビタミン、銅をとりましょう。。
ビタミンB2、B6、B12、葉酸、ビタミンC、銅なども造血や鉄の吸収に欠かせない栄養素です。食事量が少なかったり偏食してしまうとこれらを十分に摂取することができません。3食バランス良くきちんと食べることが大切です。
胃液の分泌が高まると鉄の吸収が促進されるため、酸味、香辛料を効かせた料理を積極的に取り入れるなど調理の工夫をしましょう。
また、食事で鉄を補うことが難しい場合は、鉄のサプリメントも上手に利用しましょう。
鉄不足が原因ではない貧血もありますので、鉄をとっても改善がみられない場合は早めに受診しましょう。
管理栄養士Y.N



 和につながることは、数々の研究で証明されています。定期的に運動することが大切で、週に2回以上運動している人はストレスや不安とほぼ無縁と言われています。ランニングなどの有酸素運動を20分ほど、もしくは散歩に出かけるだけでもストレスを抑える効果は望めるとのことです。
和につながることは、数々の研究で証明されています。定期的に運動することが大切で、週に2回以上運動している人はストレスや不安とほぼ無縁と言われています。ランニングなどの有酸素運動を20分ほど、もしくは散歩に出かけるだけでもストレスを抑える効果は望めるとのことです。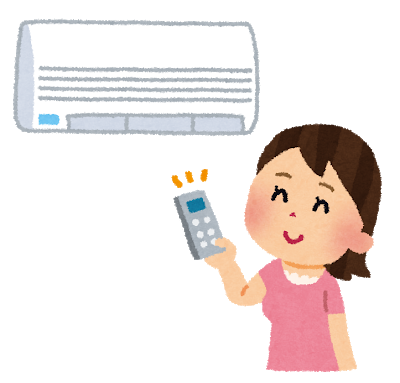 新型コロナウィルス感染者数は日々減少傾向ではありますが、今年は感染症予防をしつつ熱中症の予防も必要という、今まで経験したことのない夏を迎えることとなりました。
新型コロナウィルス感染者数は日々減少傾向ではありますが、今年は感染症予防をしつつ熱中症の予防も必要という、今まで経験したことのない夏を迎えることとなりました。 で男女が逆転します。
で男女が逆転します。
 なっています。6月は食育月間です。この機会に食品ロスについて考えてみましょう。
なっています。6月は食育月間です。この機会に食品ロスについて考えてみましょう。 「夏も近づく八十八夜~野にも山にも若葉が茂る」という歌の歌詞は誰もが耳にしたことがあると思います。この歌詞にある八十八夜とは立春から数えて八十八日目にあたる日のことで、2020年は5月1日です。この時期は茶摘みの最盛期であり、八十八夜に摘み採られるお茶は、古来より不老長寿の縁起物の新茶として珍重されています。
「夏も近づく八十八夜~野にも山にも若葉が茂る」という歌の歌詞は誰もが耳にしたことがあると思います。この歌詞にある八十八夜とは立春から数えて八十八日目にあたる日のことで、2020年は5月1日です。この時期は茶摘みの最盛期であり、八十八夜に摘み採られるお茶は、古来より不老長寿の縁起物の新茶として珍重されています。


