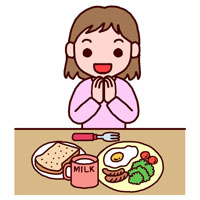1月下旬からやっと冬らしくなりましたが、2月3月は暖冬との予想です。暖冬だと春には花粉の量が多いのかな?と心配になりますね。でも、安心してください!暖冬は関係ありませんよ!!
実は日本気象協会によると、夏の気象条件のデータを基に翌年の花粉飛散予測をすることが多いようです。というのも花粉の飛散数は夏の天候次第で決まるとされているからです。前年の夏の天候が、気温が高く、日照時間が長く、雨が少ないといった気象条件がそろうと花芽が多く形成されるため、翌年の花粉飛散数が多くなると言われています。では気になる昨年夏の天候は?2015年は東日本と西日本で天候が大きく分かれました。西日本は台風の影響を受けやすいために2年連続の冷夏でした。また日照時間は、西日本は短く、太平洋側では特に短かったようです。降水量は、西日本では平年並みが多く太平洋側はかなり多かったようです。
以上を踏まえ、2016年の花粉飛散予測ですが、全体的に『例年よりは少なく、2015年よりも多い』傾向にあるようです。で?どれくらいなのかわかりにくいですが…。
何はともあれ、花粉が飛び始めてから花粉症対策をしていては実は遅いのです。今から体調管理を万全にして、少しでも花粉症の症状を緩和しましょう。
そのためには食事が重要です。規則正しい生活リズムとバランスの取れた食事はもちろんですが、花粉症に効果のある食品を紹介したいと思います。
●ヨーグルト
花粉症の人に1日200ml以上のヨーグルトを1年間摂取してもらったところ、 3割の人の症状が軽くなったという実験結果も報告されています。腸内環境を整える働きをする事で知られるヨーグルト。ヨーグルトに含まれる乳酸菌には、善玉菌を増加させて腸内に悪影響を及ぼす物質を除去し、腸の粘膜を健康な状態に回復させる作用があります。ヨーグルトには、花粉症の原因であるIgE抗体の活動を抑制する作用もある事から、アレルギー症状にも有効とされています。また、花粉症は腸内環境が悪い事も原因のひとつと考えられています。その事からも、ヨーグルトは花粉症対策に効果的な食品と言えるでしょう。花粉の飛散が始まる前から習慣的に取り入れるようにするのがおすすめです。しかし、理研バイオリソースセンター室長によると、「ヨーグルトだけではそこまで効果がなくて、野菜も一緒に食べるのがポイント」だそうです。
●レンコン
ヨーグルトと一緒に食べる野菜で特にオススメなのがレンコンです。これは3ヶ月で81%の人に花粉症の症状緩和が認められたという報告があります。レンコンに含まれる栄養素には、抗アレルギー作用や鼻の粘膜を覆ってくれたりする効果があります。その他にタンニンには、止血や炎症を抑えるなどの効果があるとされ、また抗酸化作用があるポリフェノールを豊富に含んでいます。レンコンの汁を鼻の粘膜に直接塗るのも効果が期待できると言われています。
●えごま油
サラダ油などのリノール酸を摂りすぎることでアレルギーが引き起こされてしまいますが、えごま油などのαリノレン酸にはそうした働きを抑える効果があります。リノール酸の悪影響を減らすためには、αリノレン酸とリノール酸の摂取割合を1:2にすることが望ましいという研究結果がありますが、現代人は1:20ぐらいになってしまっており、リノール酸過剰摂取です。花粉症患者増加の原因の一つかもしれないと、現在研究が進められています。
●トマト
トマトに含まれるリコピンを継続的に摂取することで症状緩和に効果があります。このリコピンは加工品の方が多く含んでいて生のトマトのなんと3倍も含まれています。またトマトの果皮部分に含まれている成分「ナリンゲニンカルコン」には、抗酸化作用や炎症の鎮静作用などがあるとされる事から、花粉症の症状に効果が期待出来ます。この成分も加工品の方が多く含まれていますが、トマトケチャップやトマトジュースは果皮を剥く処理がされているため、花粉症への症状改善の効果はあまり期待できないようです。また、まれに果物過敏症(食物アレルギー症状/口腔アレルギー症候群)を併発する場合もありますので、花粉症に効果的とは言え摂取する際は注意が必要です。
今回紹介したのはほんの一部ですが、参考にしてみてくださいね。食事だけでなく、寒いからといって家の中でじっとしているのも花粉症にはよくありません。食事をした後はしっかり体を動かしましょう!
また、当院では花粉症治療として、『アルゴンプラズマレーザー』による下鼻甲介粘膜凝固手術を行っています。術後の出血や痛みなどもほとんどなく、良好な結果が得られておりますので、耳鼻咽喉科へお気軽にお尋ね下さい。
管理栄養士 S.N
 4月17日(日)に倉敷生活習慣病センターに通院中の患者さんやそのご家族の方と岡山プラザホテルにて食事会を行いました。
4月17日(日)に倉敷生活習慣病センターに通院中の患者さんやそのご家族の方と岡山プラザホテルにて食事会を行いました。