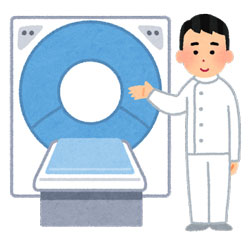1月に入り寒さも一段と増していき、最近では倉敷でも雪がちらほらしてきました。
そんな中インフルエンザになる方も増えてきています。
去年よりも出てき始める時期は遅いですが、A型・B型の両方が既に出ています。
インフ ルエンザの潜伏期間は1~2日で、発症する1日前から発症後5~7日頃まで周囲の人にうつしてしまう可能性があります。特に発症日から3日間ほどが最も感染力が高いと考えられています。さらに、熱が下がってもインフルエンザの感染力は残っていて、他の人に感染させる可能性があります。
ルエンザの潜伏期間は1~2日で、発症する1日前から発症後5~7日頃まで周囲の人にうつしてしまう可能性があります。特に発症日から3日間ほどが最も感染力が高いと考えられています。さらに、熱が下がってもインフルエンザの感染力は残っていて、他の人に感染させる可能性があります。
インフルエンザにならないためにも手洗いやうがい、外出の際にはマスクを着用するなどして予防する事が大切です。
また、空気が乾燥すると、喉の粘膜の防御機能が低くなるため、インフルエンザにかかりやすくなります。 乾燥しやすい冬場の室内では、加湿器などを使って50~60%の湿度に保つことも効果的です。
皆さんも風邪やインフルエンザにかからないようにして楽しく2018を過ごして下さい。
放射線部 MK


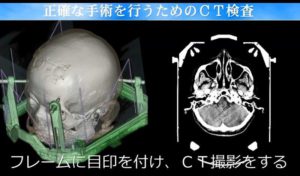
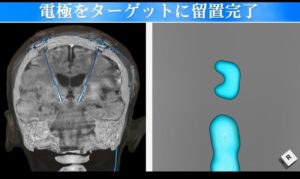
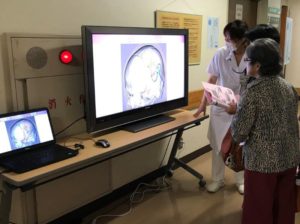

 去る8月にCT装置のプチ・機能アップがありました。
去る8月にCT装置のプチ・機能アップがありました。 マンモグラフィとは、乳がんの診断に欠かせないX線検査です。乳房を圧迫してできるだけうすく引きのばして撮影を行います。「乳房を圧迫してうすく引きのばす」というのは、乳腺の中の細かい病変を見つけるためにとても重要なことですが、この「圧迫」をすることで、どうしても痛いというイメージがついてしまっている検査でもあります。
マンモグラフィとは、乳がんの診断に欠かせないX線検査です。乳房を圧迫してできるだけうすく引きのばして撮影を行います。「乳房を圧迫してうすく引きのばす」というのは、乳腺の中の細かい病変を見つけるためにとても重要なことですが、この「圧迫」をすることで、どうしても痛いというイメージがついてしまっている検査でもあります。