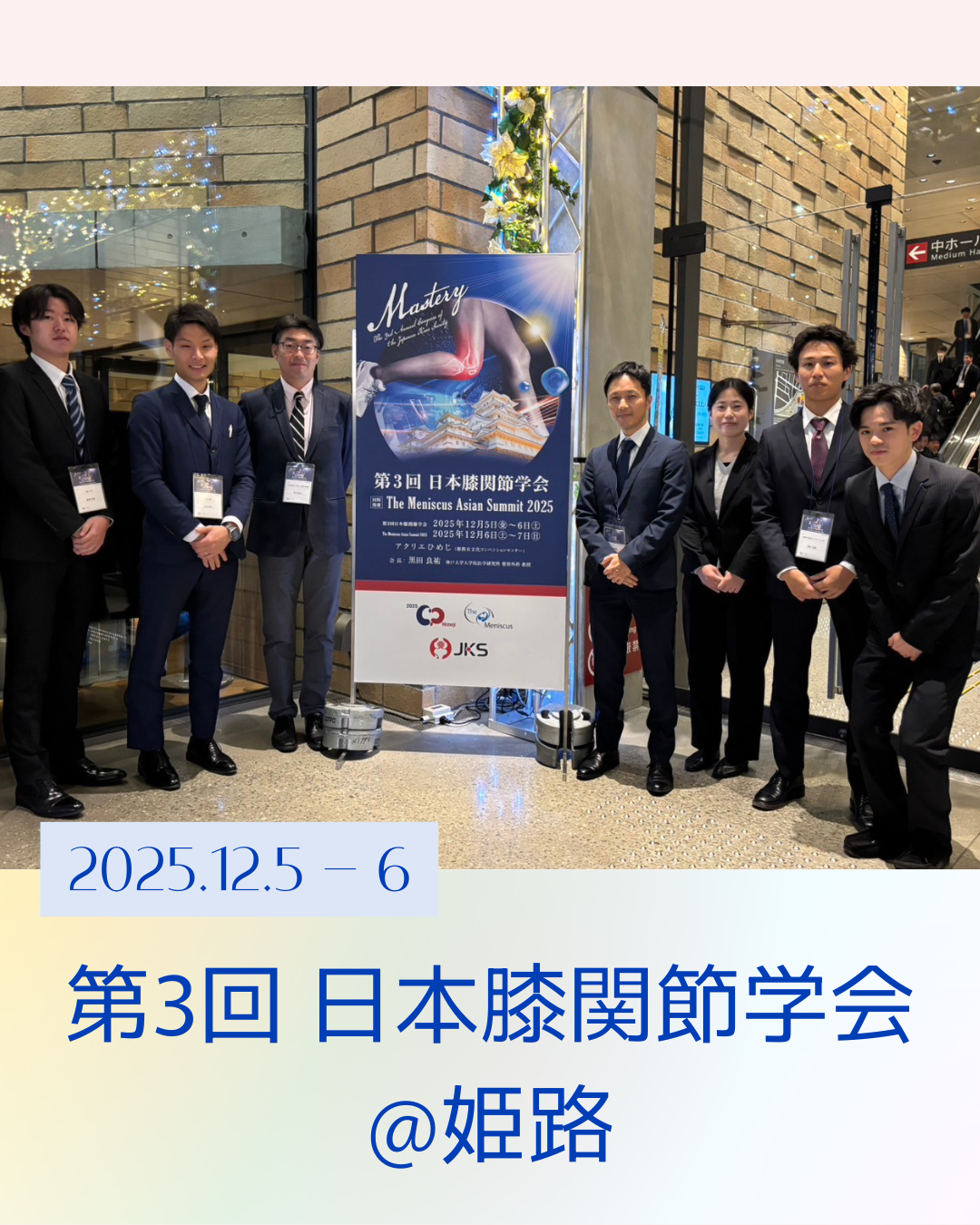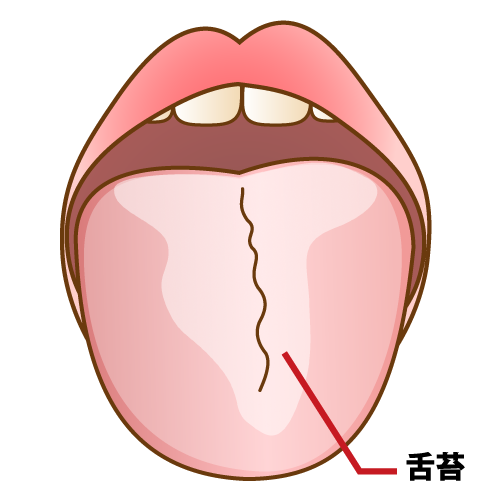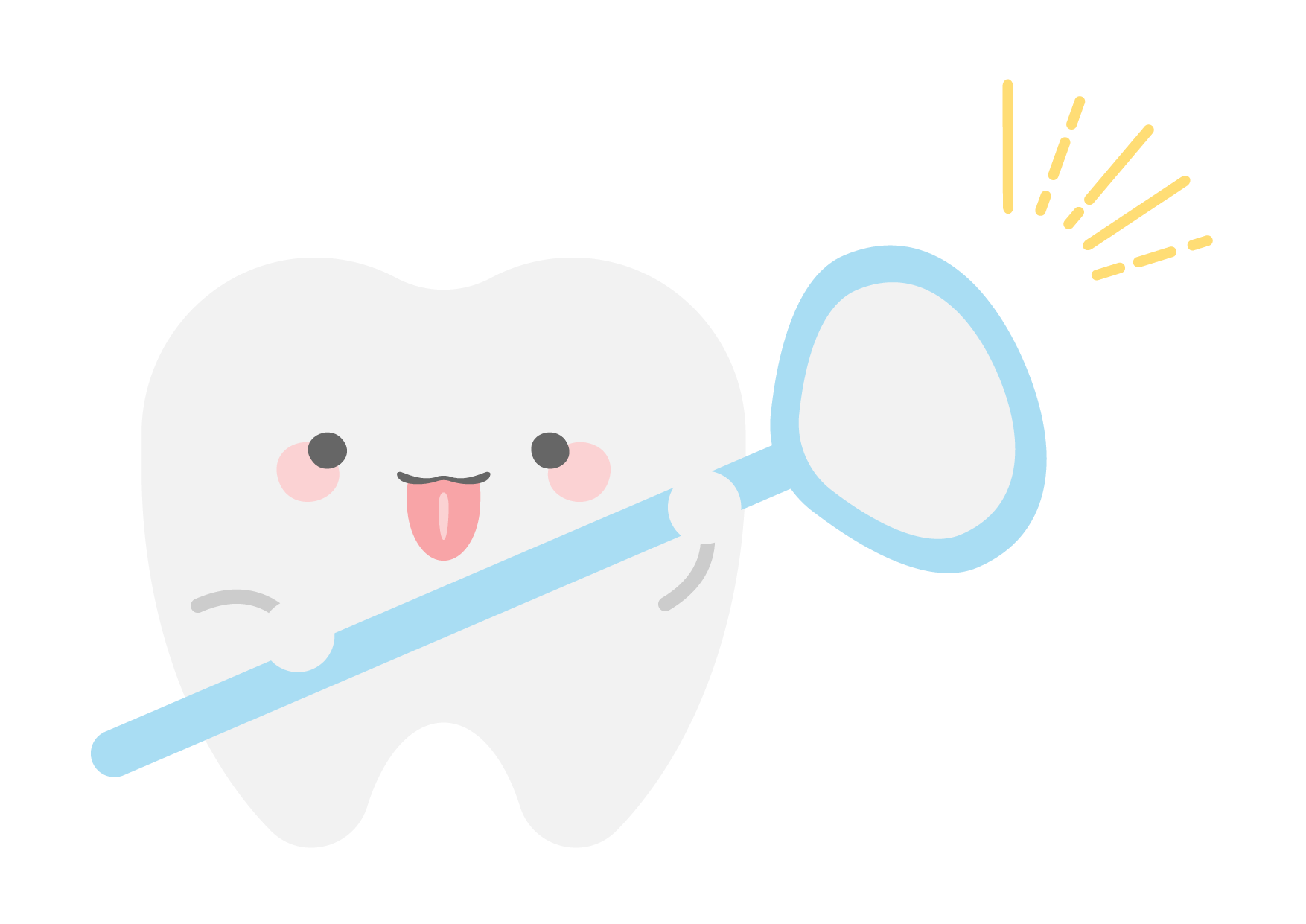一段と寒さが深まってまいりましたが、ご体調はいかがですか。
最近ではインフルエンザの流行が急拡大しているとして、岡山県は11月28日にインフルエンザ警報を発令しました。警報発令は過去10年で最も早いそうです。また、患者の7割越えが14歳以下で、特に学校園を中心に感染が広がっているようです。そこで今回は日常生活でできる予防対策について改めて見ていきましょう。
日常生活でできる予防対策
●1.手洗い・手指消毒:正しい手洗いは最も基本的で重要な予防法です。
正しい手洗い方法
1.流水で手を濡らし、石鹸をつける
2.手のひら、手の甲、指の間、爪の先まで20秒以上かけて洗う
3.流水でよく洗い流す
4.清潔なタオルやペーパータオルで拭く
●2.マスクの着用
•人混みや公共交通機関では適切にマスクを着用しましょう
•咳やくしゃみが出る場合は、必ずマスクを着用し、他者への感染防止に努めましょう
●3.咳エチケット
•咳やくしゃみをする際は、ティッシュや肘の内側で口と鼻を覆いましょう
•使用したティッシュはすぐに廃棄し、手洗いを行いましょう
●4.環境の整備
•室内の湿度を50~60%に保ちましょう
•定期的な換気を心がけましょう
•十分な睡眠と栄養バランスの良い食事で免疫力を維持しましょう
生活習慣の見直し
●1.栄養管理:免疫力を高めるため、以下の栄養素を意識して摂取しましょう。
•ビタミンC(柑橘類、野菜)
•ビタミンD(魚類、卵)
•亜鉛(肉類、海産物)
•発酵食品(ヨーグルト、納豆)
●2.睡眠:成人は7~9時間の質の良い睡眠を心がけましょう。睡眠不足は免疫機能の低下につながります。
●3.運動:適度な運動は免疫機能を向上させます。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で継続しましょう。
これらの対策で、身の回りのウイルスを排除することができ、自分の免疫力が高まりインフルエンザに感染しにくい体をつくることができます。日常生活の中でこれらを意識してインフルエンザに感染しにくい環境・体をつくっていきましょう。
参考
・丹野内科 インフルエンザ流行の基礎知識と対策法
イラスト:イラストAC
臨床検査部 S.F