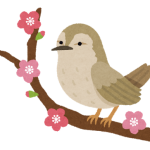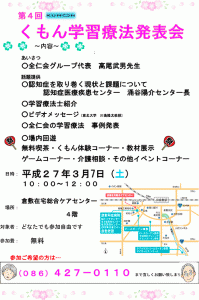今日は2月27日に倉敷市立西小学校で行われた車椅子贈呈式に入所者様と参加した様子をレポートします!!毎年倉敷西小学校や地域の皆さんが、一生懸命集めたアルミ缶を換金したお金で、車椅子を購入して施設に寄付をされています。なんと、この活動は今年で21年目だそうです(゜o゜)倉敷老健でも毎年新しい車椅子を1台贈呈して頂いています。その際に学校行事として「車椅子贈呈式」が企画され、この度も招待して頂きました。学校に訪問し、子供達と触れ合うという貴重なチャンスです。今年は、いつも明るく周囲の人とお話しをされる、笑顔の素敵な増田和美さんにお願いしました(^o^) 増田さんは、1週間前から「ちゃんと出来るやろうかー?」と心配そうに、何度も「挨拶」の練習をしてきました。

いよいよ当日。さすがは大人の女性!!当日は朝からお化粧をするなど身だしなみを整えておられました。少し緊張している様子はありますが、表情はいつも通りにこやかで子供達に会えることを楽しみにしている様子でした。さあ、「挨拶」の最終確認をして準備完了です!! 倉敷西小学校に着くと早速、児童達が元気良く挨拶をして出迎えてくれました。校長室へと案内して頂き、お茶を頂きながら開式を待ちました。その間も、お話上手な増田さんは校長先生と楽しく会話されていました。

 時間になり、児童達に案内されて体育館に入場すると、全校生徒の皆さんが大きな拍手で出迎えてくれました!!増田さんは児童達の姿が、ご自身の曾孫と重なり、すでに涙目になっていました(^^)児童代表の方の元気な挨拶が終わり、車椅子を贈呈して頂きました。いよいよ、増田さんの「挨拶」の出番となりました。感動のあまり声が震える場面もありましたが、気持ちのこもった素晴らしい挨拶をされました! その後は児童の皆さんが用意した○×クイズや合唱を披露してくれました。全校生徒での合唱は迫力があり、きれいな歌声で本当に心に響きました♪一部の児童達は踊りながら歌ってくれていてとても上手で可愛かったです!最後に校長先生のお話があり、式は終了しました。
時間になり、児童達に案内されて体育館に入場すると、全校生徒の皆さんが大きな拍手で出迎えてくれました!!増田さんは児童達の姿が、ご自身の曾孫と重なり、すでに涙目になっていました(^^)児童代表の方の元気な挨拶が終わり、車椅子を贈呈して頂きました。いよいよ、増田さんの「挨拶」の出番となりました。感動のあまり声が震える場面もありましたが、気持ちのこもった素晴らしい挨拶をされました! その後は児童の皆さんが用意した○×クイズや合唱を披露してくれました。全校生徒での合唱は迫力があり、きれいな歌声で本当に心に響きました♪一部の児童達は踊りながら歌ってくれていてとても上手で可愛かったです!最後に校長先生のお話があり、式は終了しました。
 その後、校長室でコーヒーを頂いた後、記念撮影をして帰りました。増田さんは終始楽しそうにされていました。私は去年に引き続き2回目の付添いをさせて頂き、去年の感動を思い出しました。これからも地域の方に倉敷老健を知って頂き、交流を深めていけるよう頑張ります!! 倉敷西小学校の皆さん本当にありがとうございました!頂いた車椅子は大事に使わせて頂きます。
その後、校長室でコーヒーを頂いた後、記念撮影をして帰りました。増田さんは終始楽しそうにされていました。私は去年に引き続き2回目の付添いをさせて頂き、去年の感動を思い出しました。これからも地域の方に倉敷老健を知って頂き、交流を深めていけるよう頑張ります!! 倉敷西小学校の皆さん本当にありがとうございました!頂いた車椅子は大事に使わせて頂きます。

(※写真の掲載はご本人から許可を頂いています)
倉敷老健リハビリY