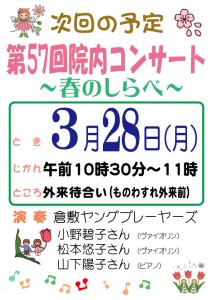4月から入職する新入職員48名が参加し、3月16日(水)~18日(金)の3日間、平成28年度新入職員入職前研修が倉敷在宅総合ケアセンターとサントピア岡山総社で開催されました。
4月から入職する新入職員48名が参加し、3月16日(水)~18日(金)の3日間、平成28年度新入職員入職前研修が倉敷在宅総合ケアセンターとサントピア岡山総社で開催されました。
この入職前研修は、2泊3日の宿泊研修として行われ、社会人、医療人としての心構えや知識、接遇やマナーについて基礎的な事を学び、短期間ではありますが、寝食を共にすることで、チームの中での役割や行動を具体的に学ぶとともに、同期としての絆を深める事を目的としています。
初日の研修は、社会人第一歩としての研修、また同期と初顔合わせということもあり、不安と緊張の中でスタートしましたが、研修がすすむにつれ、コミュニケーションが図れ、会場の雰囲気も和み、自然と同期の絆が生まれていました。
グループワークでは、チームでの役割が自発的に決まり、活発な意見交換が行われる等、有意義な研修が行われました。
積極的な姿勢でひたむきに研修に取り組む新入職員の姿は、私にとって実に新鮮で爽やかなもので、私自身も『初心』に立ち返る大切さを新入職員から学ばせてもらいました。
最終日には、懇親会も開催され、高尾理事長をはじめ、多くの管理職が参加し、新入職員にとって貴重な交流の場となりましたので、4月1日からの初出勤の不安も少しは和らいだのではないかと思います。
新入職員には、全仁会の一員として一日も早く職責を果たしてもらえるよう願うとともに、教育を担当される方々には『共に学ぶ』という姿勢で教育して頂きますようお願い申し上げます。
人事部 S.H