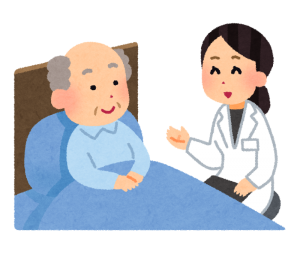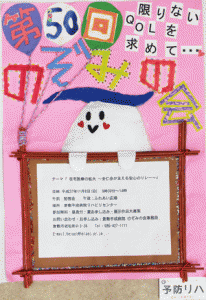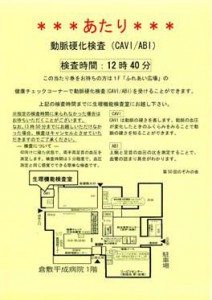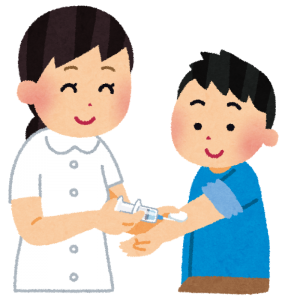最近、写真(仕事の人体が透ける写真ではない)に再びはまりまして、撮影して帰ってパソコンで確認すると喜びとため息の繰り返し(ため息の方が多い。一眼レフは失敗が多い)の日々を送っています。
最近、写真(仕事の人体が透ける写真ではない)に再びはまりまして、撮影して帰ってパソコンで確認すると喜びとため息の繰り返し(ため息の方が多い。一眼レフは失敗が多い)の日々を送っています。
昨年、娘が高校生になり光画部いわゆる写真部に入部しました。最初は自分が使っていたコンパクトデジカメを持たせていましたが、やはり一眼レフでないと光画部らしくないということで購入しました。内心かなり嬉しく購入しましたが、娘が持てるカメラとレンズの重量と性能のバランスにずいぶん悩みました。
娘の写真は、最初のうちはフレーミングが下手でつまらない写真ばかりでしたが、先輩のアドバイスを受け始め(親のアドバイスは聞きたがらない)、一緒に撮影会に行くなどしてメキメキと上達していきました。
そもそも自分が最初に写真にはまったのは23歳の頃で、親父にやはり一眼レフ(フィルム式)を買ってもらい、たくさん撮影していました。しかし、娘がすこし大きくなった頃にデジタルの波が押し寄せフィルム式の一眼レフは撃沈し、懐事情でコンパクトデジカメが浮上してきました。
やはりコンデジなのでどう頑張ってもそれなりで、やがて「それなり」が普通になり証拠写真ばかりになって行きました。
 ある時、親父がデジタル一眼レフを買ってきました。まだまだ画素数がフィルムよりも遙かに劣っている物でしたが、レンズはやはり一眼のでかいレンズで、絞りのコントロールも出来るので時々は借りて撮らせて貰っていましたが、やはり自分の物でないのでのめり込むことも無かったです。
ある時、親父がデジタル一眼レフを買ってきました。まだまだ画素数がフィルムよりも遙かに劣っている物でしたが、レンズはやはり一眼のでかいレンズで、絞りのコントロールも出来るので時々は借りて撮らせて貰っていましたが、やはり自分の物でないのでのめり込むことも無かったです。
しかし、転機は突然現れ、娘の光画部入部(驚きと喜びと不安で複雑でした)のおかげで2人兼用のデジタル一眼レフを購入し、今では娘の作風を真似して撮影しています。
先日、鳥取の花回廊に行ってきました。結婚記念日でのお出かけだったのですが花の撮影会の方がメイン(大山豚のカツ丼がうまかったので許して!)になりました。ここで父親の威厳を保つため頑張って撮影しましたが、十代のアグレッシブさには勝てません。どんな花でも攻めて行く姿は年寄りには無理です。園内を歩き回るので精一杯です・・・。
花は小さい物なので、人間が近くに寄って見てもただ花びらが大きく見えるぐらいですが、一眼で近づくと花の周りがぼやけて、その花だけ、もしくはある部分だけくっきり見えます。花の美しさが驚くほど強調されます。このクローズアップに娘は取り付かれて今はそればかりです。負けじと自分も対抗しています。
そう言えば昔、自分も親父と同じような事をしたなと懐かしく思います。
写真の魅力に取り付かれるのは結局、親父の血筋でしょうか?自分が小さい頃、親父がレンズを磨き、ファインダーを覗いて空打ちしている姿をよく見かけました。自分が就職してから何故か親父がカメラを買ってくれて、そして何故か娘がカメラ女子になり、再び一眼に会えて親子孫共通の趣味が出来ました。濃い血筋を感じます。


放射線部 トンカツ
 思っておりましたら、なんと11月8日(日)に「のぞみの会」があります!!そこで、鍼灸院は「鍼灸相談・体験治療」を行いますので、是非ご参加下さい。
思っておりましたら、なんと11月8日(日)に「のぞみの会」があります!!そこで、鍼灸院は「鍼灸相談・体験治療」を行いますので、是非ご参加下さい。