 12月も半ばに差し掛かり、2019年も残すところわずかになってきましたね。そろそろ年賀状の準備をしなければと思われている方も多いのではないでしょうか。年賀状は新年のあいさつに加え、親戚や友人に対し近況報告をすることができる良い機会です。では、患者と医療者との間の近況報告は一体どのような手段があるのでしょうか。定期的に病院を受診することなど、様々な例があるとは思います。本日は「薬」に関して、患者と医療者、また医療機関同士でも近況報告を行える手段として重要な役割のある「お薬手帳」についてお話していきたいと思います。
12月も半ばに差し掛かり、2019年も残すところわずかになってきましたね。そろそろ年賀状の準備をしなければと思われている方も多いのではないでしょうか。年賀状は新年のあいさつに加え、親戚や友人に対し近況報告をすることができる良い機会です。では、患者と医療者との間の近況報告は一体どのような手段があるのでしょうか。定期的に病院を受診することなど、様々な例があるとは思います。本日は「薬」に関して、患者と医療者、また医療機関同士でも近況報告を行える手段として重要な役割のある「お薬手帳」についてお話していきたいと思います。
お薬手帳とは、いつ、どこの病院で、どのような薬をもらったかがわかるように記録していく手帳のことで、基本的には医療機関や薬局で手に入ります。複数の医療機関を受診した場合や、薬の内容が変わったとき、引っ越しをしたとき、災害時など、この手帳を見せるだけでそれぞれの患者さんの薬の内容がわかるようになります。また、お薬手帳は、複数の医療機関で同じお薬が重複して処方されることを防いでくれ、また、薬の飲み合わせで問題がないかを確認できる資料としての役割もあります。
また、急に体調が悪くなり救急病院に搬送される事態となった場合、ご自身で伝えられる状況にない時も、薬の服薬内容を医療機関に発信できることは治療方針を決定する上でとても役立ちます。実際、当院でも入院時には私たち薬剤師が患者さん1人1人の服薬内容をチェックしていますが、その際お薬手帳があるととても助かっています。
お薬手帳は医療機関側のみが記入できるというものではありません。「先生から薬の変更を伝えられたからメモしておこう。」「この薬が何の薬かわからない。」「最近こんな症状がある。」など、ご自身の気になることや、今の症状など、患者さんご自身で何を記入していただいても大丈夫なものです。お薬手帳という名の、患者さんと医療機関、また医療機関同士をつなぐ“連絡ノート”のような役割を果たすものとも言えるでしょう。
最近はお薬手帳の携帯アプリも登場しています。手帳を持ち歩くことに抵抗がある方はこのようなツールがあることも知っていただき、ご自身で使いやすいと思われるものを選択し、ぜひ活用していただければと思います。
薬剤部 MK

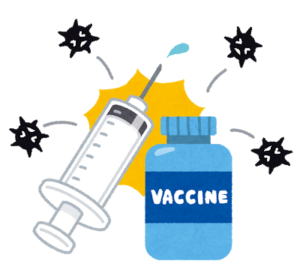 一般的な風邪は1年を通してみられますが、インフルエンザは季節性を示し、日本では例年11~12月頃に流行が始まり、1~3月にピークを迎えます。一般的な風邪は様々なウイルスによって起こり、その多くはのどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こり、高熱を伴って急激に発症し、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感、食欲不振など全身症状が現れます。併せて一般的な風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど、重症化することがあります。
一般的な風邪は1年を通してみられますが、インフルエンザは季節性を示し、日本では例年11~12月頃に流行が始まり、1~3月にピークを迎えます。一般的な風邪は様々なウイルスによって起こり、その多くはのどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こり、高熱を伴って急激に発症し、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感、食欲不振など全身症状が現れます。併せて一般的な風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど、重症化することがあります。

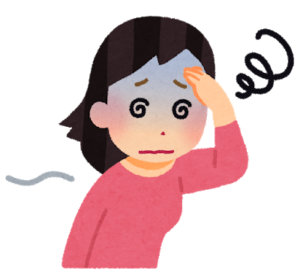


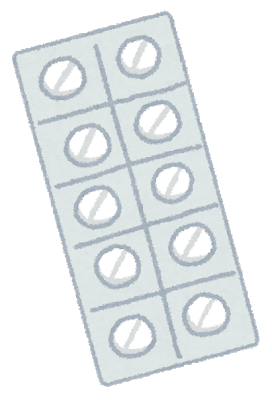
 日本高血圧学会の松岡博昭理事長(獨協医科大学循環器内科教授)は、今回の「高血圧の日」制定について、「高血圧が脳卒中などの重篤な疾患を引き起こすことについて、一般の方の認知が極めて低いことに危機感を覚えています。5月17日は我々も加盟している 世界高血圧リーグが制定した世界高血圧デーです。日本でも同じ日を『高血圧の日』と定め、学会としても日本高血圧協会とともに、各方面の協力を得ながら、一般の方への啓発活動を積極的に進めていきたいと思います。そして、少しでも血圧に不安を感じた方が、医師に相談をしていただけるようになることを期待しています」と述べています。
日本高血圧学会の松岡博昭理事長(獨協医科大学循環器内科教授)は、今回の「高血圧の日」制定について、「高血圧が脳卒中などの重篤な疾患を引き起こすことについて、一般の方の認知が極めて低いことに危機感を覚えています。5月17日は我々も加盟している 世界高血圧リーグが制定した世界高血圧デーです。日本でも同じ日を『高血圧の日』と定め、学会としても日本高血圧協会とともに、各方面の協力を得ながら、一般の方への啓発活動を積極的に進めていきたいと思います。そして、少しでも血圧に不安を感じた方が、医師に相談をしていただけるようになることを期待しています」と述べています。