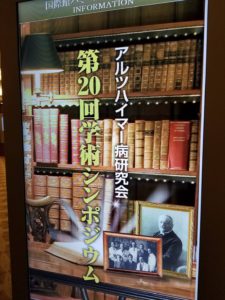身体を動かしやすい季節に入り、運動を始められた方も多いかと思います。しかしもうすぐ梅雨。せっかくのやる気を損ねない為に、今回は雨の日の過ごし方について、いくつかご紹介します。
〇道具を使って普段のペースを守る
雨にも負けず、ペースを崩したくない方にはお勧めです。工夫すれば色々な運動を自宅で行うことが出来ますよ。バランスボール等、タンスの肥やしになっている器具の活用機会にしてみるのもいいでしょう。例えば、『準備運動>ウォーキング>筋トレ>整理運動』を日課としている方であれば、準備運動・整理運動・筋トレはいつも通り行い、ウォーキングの代わりに5~10㎝の踏み台昇降を取り入れる。実践された方からは「TVを見ながらできるから、むしろ普段より時間は気にならない。」とおっしゃっておられました。
ただし、この運動には注意点があります。
①絶対に無理をしないこと。段差昇降は平地に比べ足や腰への負担が大きい為、慣れるまでのスピードや台の高さは『少し物足りない程度』に抑えましょう。
②交互に足を出すこと。右足から上げたら、次は左足から上げるといった具合です。下す順序も同様に順番を変えましょう。脳トレにも繋がりますね。昇段時は先の足に、降段時は後に下す足に負担がかかります。交互に行い、バランスを整えましょう。
③転倒に注意すること。テーブルなどを支えにしても構いません。
〇テレビ体操・ラジオ体操に本気で取り組む
子どもの頃からやり慣れた運動ですが、リズムに合わせて大きく動かすとかなりの運動になります。呼吸や姿勢まで意識すると息が上がる程です。
〇普段より入念にストレッチを行う
できれば普段行わないストレッチを取り入れましょう。テレビや新聞などで紹介されているもので構いません。種類が少ない、物足りないという方は、普段のストレッチや準備・整理体操を2セット行ったり、1つの運動時間を延ばすのも効果的です。
〇日頃の動作を見直す
家事や職場での立ち居振る舞いを見直してみましょう。何気ない動作も少しだけ姿勢を気に掛ける、呼吸を意識するだけで活動量は変わります。「雨の日は、普段しない所まで掃除する。」と決めて、身体にも家族にも喜ばれる方法を取っている方もおられました。
〇思い切って休む
何事にも心身のリフレッシュは大切です。思い切って休むのもいいでしょう。ただし、それが長引かないような強い精神力が必要です。雨が数日続く時は、上の何かに取り組みましょう。継続することが一番です。
いかがでしたしょうか。毎日同じ運動を頻回に繰り返すことはメリットもありますが、負担が一か所に集中し、ケガやモチベーションの低下に繋がるリスクもあります。雨の日を好機と捉え、運動継続に活かして下さい。
通所リハビリテーション 理学療法士(糖尿病療養指導士) T・H