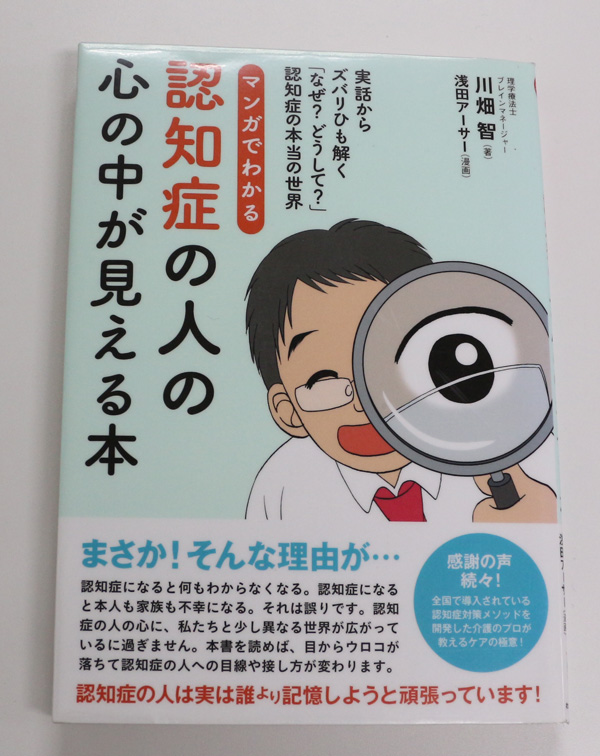倉敷平成病院の脳ドックセンターでは、働く女性が増えたこともあり、多くの女性の方々にも当センターを利用して頂いています。今日は女性の方々に、年齢を重ねてからも元気に過ごして頂くために、男性とは違う女性特有の身体の変化について知って頂けたらと思います。
女性ホルモンには、メタボリックシンドローム(メタボ)や生活習慣病を防ぐ作用があるため、女性は更年期を迎えるころ(おおむね40代後半以降)になると急に健診数値が悪化することがあります。閉経後も健康に過ごすためには、この機会に新たな健康習慣を身につけることをお勧めします。
~更年期以降の脂質異常症に要注意~
女性の体は、一生を通じて卵巣から分泌される女性ホルモン(エストロゲンやプロゲストロン)の影響を受けていますが、更年期を迎えるころから卵巣の働きが低下するに従って女性ホルモンの分泌が急激に低下します。
女性ホルモンには、血管をしなやかに保ち、脂質や糖の代謝を調整したり、内臓脂肪の燃焼を促進する働きがあります。そのため、40代ごろまではメタボや脂質異常症、糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、骨粗しょう症などを防いでくれていますが、女性ホルモンが減少する更年期近くになると、それらの病気のリスクが徐々に高まってきます。
●脂質管理はバランスが大事
卵を食べるとコレステロールが高くなる…と言われ続けていましたが、最近では食品中に含まれるコレステロール量によって、体内のコレステロール値が大きく変わることはないとわかり、2015年版の「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)からは、摂取基準が撤廃されました。米国ではトランス脂肪酸の取り過ぎが問題になっていますが、日本は飽和脂肪酸の取り過ぎの方が問題です。「◯◯油を摂って、◯◯油を摂らない」というよりも、バランスのよい脂質摂取を心がけましょう。 また、脂質だけを制限しても、炭水化物をたくさん取れば中性脂肪が高くなり、動脈硬化を起こしやすい脂質も増えてきます。ビタミンやミネラルが欠乏すると栄養素の代謝がうまくいかなくなります。昔から長寿のもとと言われていた大豆製品は、女性ホルモン類似作用もあり、更年期女性の強い味方です。こうして考えると、よく言われる「バランス」が大事、ということに行きつきます。また、有酸素運動と無酸素運動を交互に行うことで脂肪の燃焼が効率的に行われることもわかっています。更年期以降は、これまで守り神だった女性ホルモンが減ってくるぶん、そのように意識的にがんばる必要が出てきます。
~更年期に気を付けるべき骨粗しょう症の原因と対処について~
骨粗しょう症とは文字通り、骨量が減り、もろくなり、骨折しやすくなる病気です。日本では約1000万人以上の患者がいるといわれており、なかでも閉経後の女性が発症しやすいことで知られています。骨粗しょう症の原因として考えられるのは、女性ホルモンのエストロゲンの減少によるものです。
また、加齢や運動不足などの生活習慣も影響しています。骨にも新陳代謝があり、新しい骨を作ること(骨形成)と、骨を溶かして壊されること(骨吸収)を繰り返していきますが、そのバランスが重要です。更年期や加齢により、骨の分解を抑制するエストロゲンが減少することで、骨の形成が追い付かなくなるからです。
そして、骨量が減ってもろくなったのが、更年期に気を付けるべき骨粗しょう症です。
骨粗しょう症は徐々に進行するため、痛みや自覚症状がありません。しかし、どこかにぶつかったり、軽く転んだりしただけでも骨折しやすいことが特徴です。
特に肋骨、脊椎、手首の骨、太ももの付け根の骨などで骨折しやすいといわれています。中でも、高齢になるほど圧迫骨折といわれる背中や腰椎の骨が徐々に潰れてしまうものがあります。
身長が縮んだり、背中がまるくなったりするのは、この影響も考えられます。圧迫骨折は身体を動かすことで痛みを感じることもありますが、あまり痛みを感じない方、安静にしていればおさまってしまう方もいるため、すぐには気づかないケースも多いです。
骨粗しょう症の診断は骨密度と呼ばれる検査や痛みなどの症状からレントゲン、CT、MRI検査、また血液検査や尿検査による骨代謝マーカー、身長測定などをして判断されます。他の検査や治療などで骨粗しょう症が見つかることもあります。
●骨粗しょう症の予防法について
1.食事で気を付けること
骨粗しょう症は食事からでも予防はできます。カルシウム(牛乳やヨーグルト、ブロッコリー、アーモンドなど)とビタミンD(魚の肝油や脂の多い魚、きのこ、海藻類)を多く含む食材をとり、食事だけでは難しい場合にはサプリメントをあわせて摂取することもいいでしょう。他にも食事では、適量のタンパク質やマグネシウムをとることを意識し、アルコールやカフェインを控えめにすることも大切です。
2.適度な運動をする
体重の負荷がかかる、適度な運動もおすすめです。ウォーキングや階段を昇るなどの運動は骨密度を増加させます。しかし、水泳などの体重の負荷がかからないものは、骨密度は増加しません。転倒リスクを下げるための体幹と筋力のバランスを鍛えることが大切です。
3.その他、生活で気を付けること
適度な運動は必要ですが、骨折の原因となる転倒の予防のためには、さまざまなことを意識する必要があります。特に買い物などの外出時には、足元がしっかりとした靴を選び、動きやすい服装を心がけてください。雨や雪の場合にはなるべく外出を避け、靴底に滑り止めがしっかりとあるものを選びましょう。また、時間に余裕を持って外出することも大切です。時間がないと焦ってしまうと、段差に躓きやすくなったりする可能性があります。自宅にいるときでもふらつくことがあれば、住環境の整備なども必要です。段差をなくし、手すりをつけるなどの調整も検討しましょう。
骨粗しょう症の治療や予防は目に見えて効果が出るものばかりではなく、長期的なものとなります。しかし、自己判断で治療を中止することなく、医師に相談して調整するようにしましょう。
骨粗しょう症というと、かなり高齢の方に起こるものだと考えてしまうかもしれませんが、更年期を境に徐々に骨がもろくなっていきます。治療法としては薬物療法が一般的ですが、日頃の食生活や適度な運動からでも予防できることはあります。今から少しずつ、予防対策を積み重ねていきましょう。
以上、更年期世代以降の身体の変化についてお伝えをしてきましたが、更年期に関して何か気になることがある場合はまず婦人科を受診することも一つの方法です。
また定期的な子宮がん検診を受けることも大切です。当センターでも子宮頸がん検診を実施しておりますので、どうぞ遠慮なくご相談してください。

脳ドックセンター T.Y
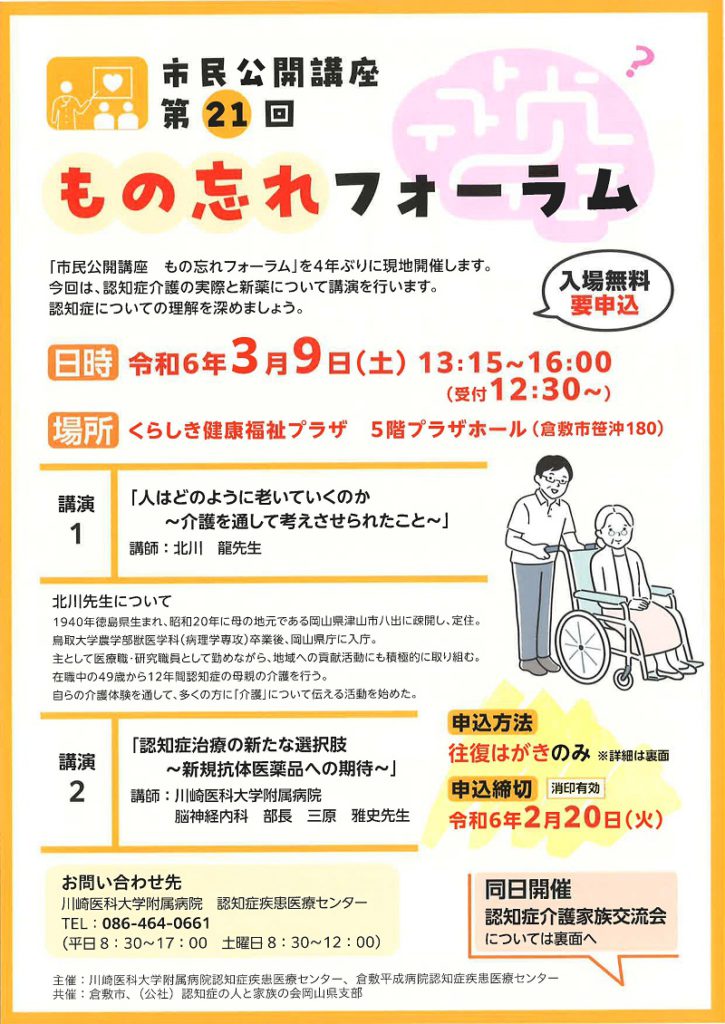


 さて、ピースガーデンショートステイでは12月恒例のクリスマス会を行いました。
さて、ピースガーデンショートステイでは12月恒例のクリスマス会を行いました。 山陽新聞 2023年12月23日(土)朝刊にて、当院整形外科 部長 高田逸朗 医師が受けた取材記事が掲載されました。
山陽新聞 2023年12月23日(土)朝刊にて、当院整形外科 部長 高田逸朗 医師が受けた取材記事が掲載されました。 肩の痛みは原因が特定できないケースもあります。かつて一度整形外科を受診した時には治療法が定まらず、保存療法(薬物療法や運動療法など、直接原因を取り除くのではなく、症状の改善や緩和を目指す治療)を続けられている方もおられるかと思いますが、現在では検査の技術向上により、原因・対策が明らかになるケースもあります。
肩の痛みは原因が特定できないケースもあります。かつて一度整形外科を受診した時には治療法が定まらず、保存療法(薬物療法や運動療法など、直接原因を取り除くのではなく、症状の改善や緩和を目指す治療)を続けられている方もおられるかと思いますが、現在では検査の技術向上により、原因・対策が明らかになるケースもあります。

 ハッピーサポートカタログは、日本生命さんが社会交流活動の一環として行われている活動です。頂きました「はっぴぃサポートカタログ」より福祉用具を選び、患者さんの看護・介護等に使用させていただきます。
ハッピーサポートカタログは、日本生命さんが社会交流活動の一環として行われている活動です。頂きました「はっぴぃサポートカタログ」より福祉用具を選び、患者さんの看護・介護等に使用させていただきます。