誰にも言えない症状こそ、専門医へ。
この度、倉敷平成病院の泌尿器科外来が
10月より午前中の木・金に増設致しました。
当院は、川崎医科大学泌尿器科と提携して行っております。
排尿に関するトラブルはもちろん、何か気になる症状がありましたら、
お気軽にご相談ください。
【予約専用ダイヤル】
電話 086-427-1140
【受付時間】
月~金 8:30~17:00(祝日除く)
土 8:30~12:00(祝日除く)

コロナ禍の影響で、長い間控えていた外食ツアーがようやく再開できるようになりました。
まずは少人数で、午後のコーヒータイムを楽しむことにしました。
普段はお1人で外出することが難しい方3名に職員2名が付き添って、近くのカフェに出かけました。
久し振りの外食ツアーで、入居者様も私たち職員も、少しの緊張とほんの少しの期待を胸に出発しました。
昼食後でしたが、スイーツは別腹です(笑) 「私はいつもウインナーコーヒーなの」と嬉しそう。ケーキを注文するのかと思いきや、「サンドイッチ!」と笑顔。ケーキが来るや否や、3口ぐらいで食べて満足気。にぎやかにお話をするわけではありませんが、各々が静かにゆっくりとコーヒーを味わい、穏やかな時間を過されていました。「言葉」は少なくても、「満足」や「楽しさ」は伝わってくるようでした。
帰所した時には少し疲れた様子もみられましたが、「楽しかった」という一言に、私たち職員の疲れもどこかに消えていきました。
こうした楽しい時間がまた過ごせるよう、新たな外出レクリエーションを企画しています。
乞うご期待を!!
ケアハウス ドリームガーデン倉敷 H
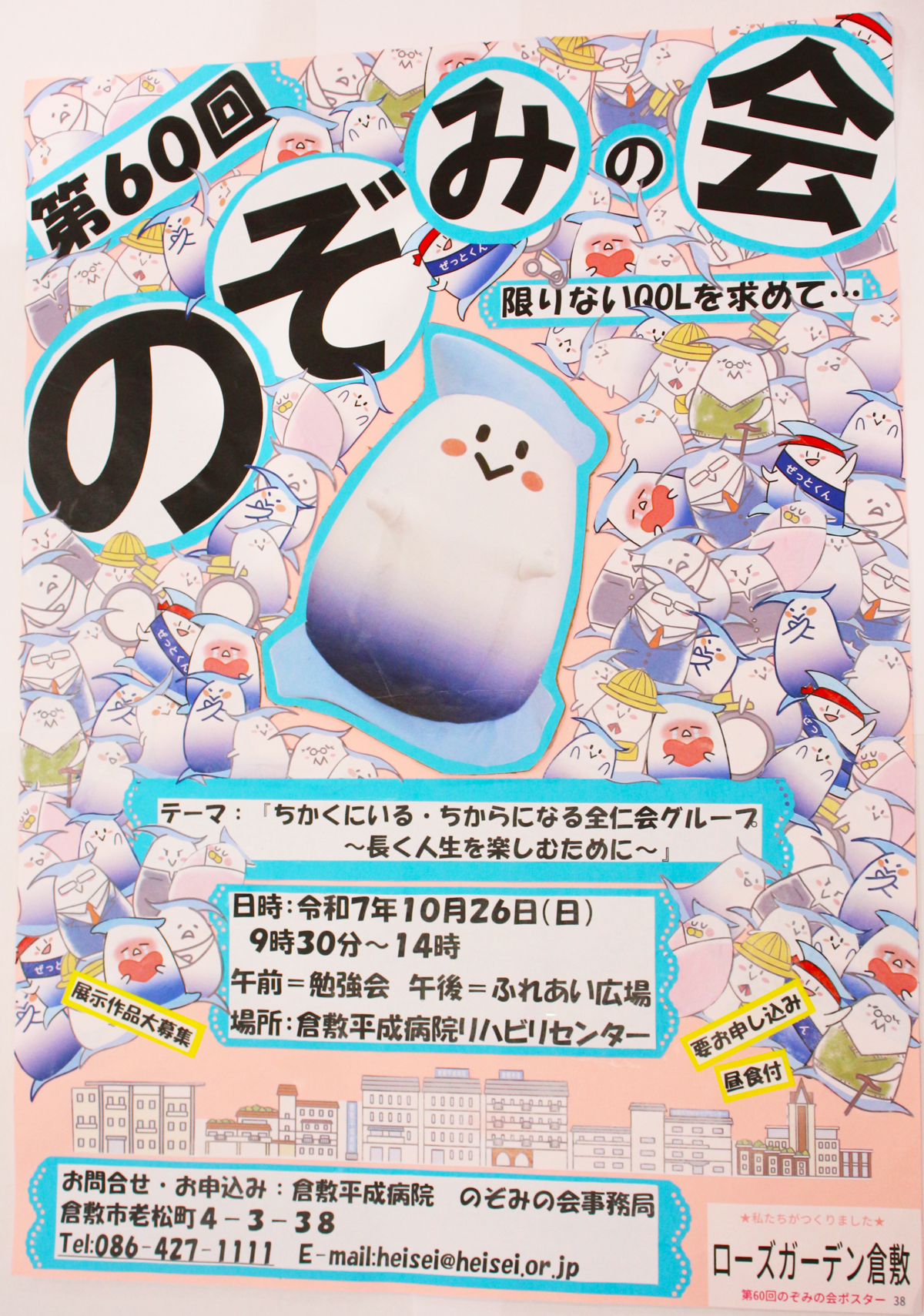
皆さんいかがお過ごしでしょうか
待ちに待った第60回のぞみの会まで明日、9月6日(土)で残り50日となります。
あと50日、もう50日!時が過ぎるのが早く感じます。
スタッフ一丸となって、皆様の笑顔を楽しみにしながら心を込めて準備しています。
のぞみの会のポスターを、病院・施設等の各部署が一生懸命作成しております。
先日は院内ポスターの引っ越しを行いました。
いつも通る廊下のポスターが違う物に変わっていて、
また新鮮な気持ちになるかもしれません。
どの部署も個性があふれており、可愛いゼット君も沢山いました
様々なところに掲載されていますので、来院された際は見ていただけると嬉しいです。
第60回のぞみの会実行委員 広報担当 手術・中材 看護師 O
※ポスターはローズガーデン倉敷が作成したものです。

日本定位・機能神経外科学会では年2回「ニューズレター」を発行されていますが、このたび2025年夏号(第29号)に、倉敷平成病院 臨床工学科 高須賀主任による「第35回日本臨床工学会ニューロモデュレーションシンポジウム開催報告」が掲載されました。
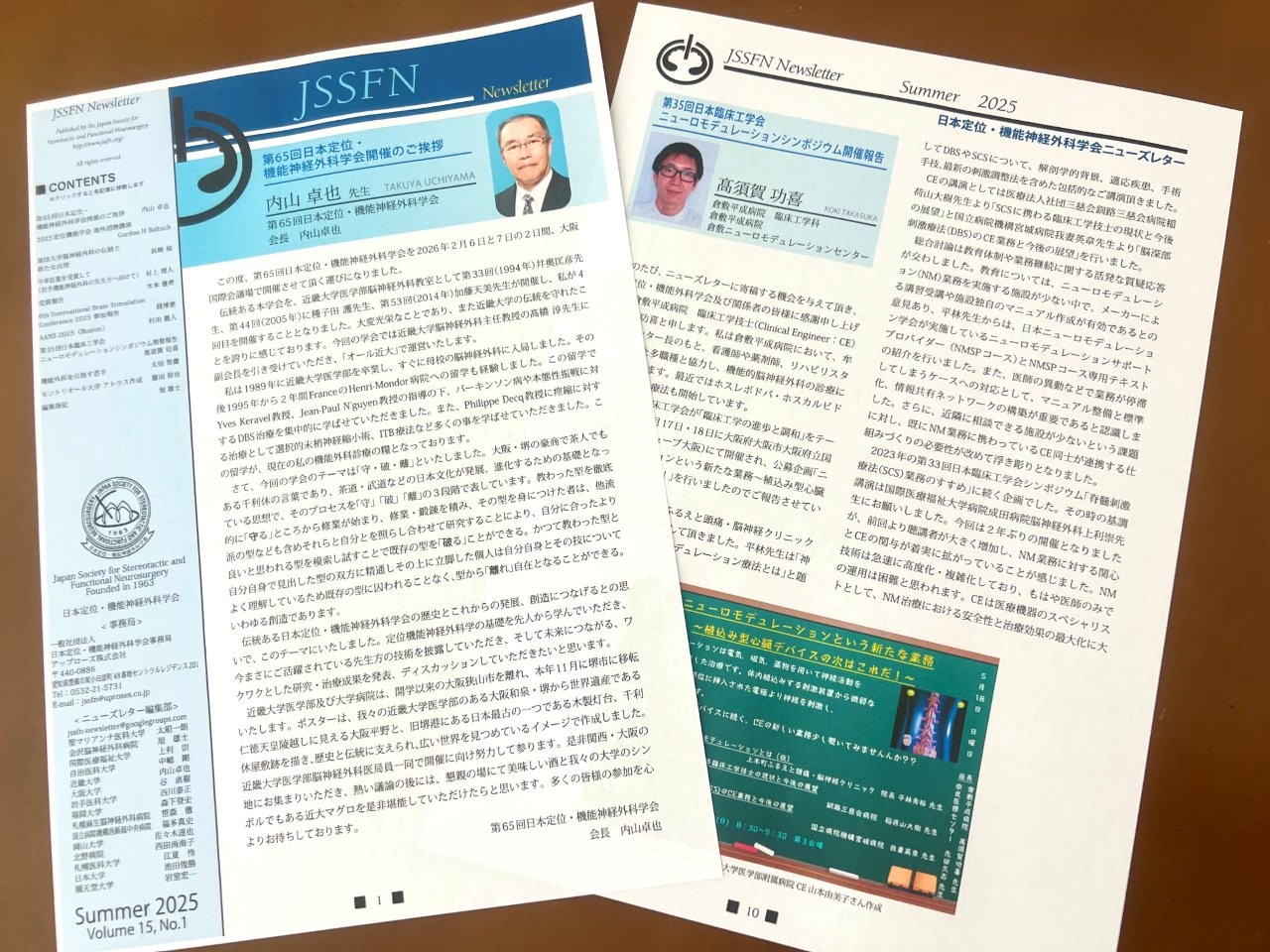
「JSSFN Newsletter」は2011年に創刊され、今年で15年目を迎える学会広報誌です。過去の投稿者は213名(うち外国人14名、脳神経内科医12名、医療スタッフ10名)で、今回の高須賀主任の掲載は、数少ない医療スタッフからの報告となります。
編集後記では次のように紹介されています。「臨床工学技士の高須賀功喜先生より、日本臨床工学会におけるシンポジウム開催のご報告が寄せられました。ニューロモデュレーション治療は機器を扱う治療であり、ぜひ臨床工学技士として日本のリーダーとなっていただき、治療の裾野を広げていただきたいと思います。」
当院スタッフが、全国の学術交流に貢献できたことは大変名誉なことです。倉敷平成病院ニューロモデュレーションセンターでは、これからも最新の知見を取り入れ、患者さんに信頼いただける医療を提供できるよう努めてまいります。ぜひ本誌をご一読いただければ幸いです。(PDF)
広報課
9月に入っても暑さが続き、秋はいつ来るのだろう?と思うような日が続いています。
熱中症や新型コロナ感染症もまた、増えているようです。水分や睡眠をとって長い夏を乗り切りましょう。
長く続いたコロナ禍を機に大きな声を出したり、話す機会が減ったような気がします。そのため、特に高齢者は嚥下機能の低下が不安視され、誤嚥性肺炎のリスクが増えているような気がします。
誤嚥性肺炎の予防として、サ高住グランドガーデン南町、特定施設グランドガーデン全体で昼食時に嚥下体操を実施しています。
ご入居の方からもとても好評で「なかなか声を出す機会がなかったのでうれしい」「しっかり訓練して予防したい」などの声が聞かれます。
積極的に参加されたり、楽しみにされているご入居の方も増えています。
誤嚥性肺炎予防に繋がり、ご入居の方の健康維持のためになればと願います。
グランドガーデン南町 GM M
こんにちは!ヘイセイホームヘルプステーション 介護タクシーです。
お盆も終わったので、通常なら少し秋めいて来てもいいような季節ですが、一段と暑い日が続くため体調を崩さないように注意が必要です。特に、全国各地で災害が続き、復興作業をされている方々は、健康・命を守るために大変な思いをされていると思います。
さて、介護タクシーの最大の特徴といえるのが、車イスのまま車の乗り降りができるという事です。
スロープを兼ね備え、介護に特化した福祉車両の介護タクシーは、通常のタクシーやご家庭の乗用車では移動の難しい、車イスに乗られた方、または寝たきりの方などの移動を可能にしてくれます。車イスをお持ちでない方でも、状況に応じて適した種類の車イスを無料で貸し出しができます。
また、高齢者や障害を持っておられる方の移動を支援するに際し、ドライバーは普通自動車二種免許の他、介護福祉士、またはホームヘルパーの資格を取得しているため、ご家族や付添いの方が介助を行う必要はなく安心してご利用できます。
通院や入退転院時のご利用だけではなく、お出かけにためらいがちな車いす生活の中に、介護タクシーを取り入れることによって、お買い物や行楽など、外出の幅を広げられる可能性もあります。
先日、倉敷市白楽町にお住まいのご利用者様から、買い物がしたいからコーナンとダイソーに行きたいとご依頼がありました。まず、倉敷駅裏のホームセンターコーナンさんへお送りし、車いすに乗られたまま店の入り口まで介助しました。店内では付添いのご家族様が介助をし、約1時間お買い物を楽しまれました。買い物が終わったころお迎えに伺い、宮前の100円ショップダイソーさんへ移動しました。帰りの車内では、一度に2か所も行きたい所に行けて大変嬉しいと喜ばれていました。
このように、ヘイセイ介護タクシーは、ちょっとした日常の買い物などにも便利に使うことができます。
お気軽にご用命ください。
ヘイセイ介護タクシー I
画像:イラストAC
みなさん、こんにちは。
8月は夏ですが、暦の上では8月7日で立秋とのことです。いかがお過ごしでしょうか。今年は特に暑い日が続いているため、こまめに水分や塩分の補給をして脱水症状にならないようにお気をつけ下さい。クーラーの使用や十分な休息を行うように心がけましょう。
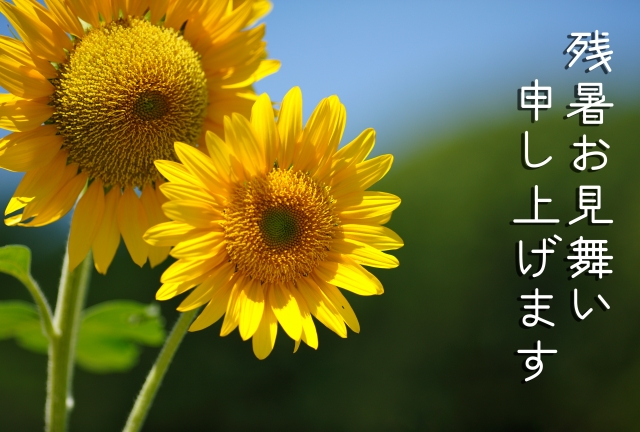
私は今年度から倉敷平成病院に入職し、約4ヶ月が過ぎようとしています。徐々に職場の雰囲気や業務にも慣れてきた頃ですが、まだまだ分からないことも多く先輩方に助けて頂きながら仕事に励んでいます。
この4ヶ月間で私が学んだことは、症状について考察していくことはもちろん患者さんの今後の生活を考えながら関わっていくことが重要であるとわかりました。機能改善だけではなく、生活や仕事、趣味など様々な面から患者さんについて知ることが大切であると思います。それらを踏まえて、自分に出来ることを考えながら日々リハビリを行っていくことが私の役割であると思っています。
まだまだ未熟でありますが、知識や技術を吸収して少しでも患者さんに寄り添うことができるように頑張っていきたいと思っております。
最後に、暑さが厳しい日々が続きますがご自愛頂きますようにお願い申し上げます。
リハビリテーション部 ST T
画像:写真AC
2025年8月18日(月)に倉敷平成病院リハビリセンターにて、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー岡山県協議会主催の『令和7年度第1回テーピング講習会』が開催され、当院スポーツリハビリテーションセンターの小畑副センター長(JSPO-AT,PT)、川元(JSPO-AT,PT)が講師を務めました。
スポーツ現場で役立つ足関節の基本的なテーピング技術を指導しました。
参加者の皆さんは実技を交えながら学び、怪我の予防やサポートに活かせる知識と技術を身につけていただけたと思います。
スポーツリハビリテーションセンター H
#倉敷平成病院スポーツリハビリテーションセンター
#倉敷平成病院
#スポーツリハビリテーションセンター
#アスレティックトレーナー
#日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
#テーピング
9月1日は防災の日です。8月30日から9月5日までが防災週間です。
「防災の日」「防災週間」には、地震や台風などの大災害への備えや防災への意識を高めるために、全国で防災訓練や説明会などさまざまな防災・減災を目的とした訓練が実施されています。
防災訓練以外には、「備蓄品を完備する、古くなった備蓄品を交換する」など、各家庭でできることを行います。
地震だけでなく、日本は台風・豪雨などの自然災害が発生しやすい国です。様々な災害に備え、今一度防災対策について考える良い機会になればと思います。
私の所属する訪問看護ステーションでも、ご利用の方に対し、災害情報を知る方法の有無、災害時の連絡手段、避難場所の確認、避難開始するタイミングの把握をしているか、備蓄品の参考例や緊急連絡カード作成のご提案、人工呼吸器使用中の方は発電機・バッテリー・予備の酸素ボンベの準備ができているかの声掛けを行っています。
・緊急速報メール(エリアメール)
気象庁が発信する緊急地震速報や津波警報、市が発令する避難所情報等をスマートフォン・携帯電話に一斉送信されます。
・テレビなどのメディア
市からの避難情報をテレビなどで発信しています。
・ラジオ
電波障害に強く、持ち運びができるので災害時の情報収集に活躍します。手回し充電できるラジオは電池が不要です。
・SNS
近年の災害では、スマートフォン等を利用したSNSが情報の発信・伝達手段として利用されますが、フェイクニュースなどに惑わされないように注意が必要です。
自宅で7日間過ごす時に必要な備蓄品を用意しておきましょう。
大災害発生時、支援物資がすぐに届くとは限らず、コンビニなどのお店にも人が殺到し、商品がすぐなくなる可能性もあります。電気、水道、ガスといったライフラインは災害発生直後は停止し、利用できなくなることもあると知っておきましょう。
!水・食料・トイレ用凝固剤は必ず備蓄しておきたいものとされています。
避難所で2~3日間過ごす時に必要な備蓄品を用意しておきましょう。
非常持出品は、災害の危険が迫り自宅から避難するときに最初に持ち出すものです。非常持出袋などにまとめ、すぐに持ち出せる場所に用意しておきましょう。
訪問看護ステーション 理学療法士T
イラスト:イラストac