 10月27日(日)倉敷南小学校体育館にて「第12回くらしきみなみ文化祭」が開催されました。会場では地域の方の力作が並ぶ作品展示コーナーや、科学実験、漫才など多くの方が楽しめる内容となっていました。
10月27日(日)倉敷南小学校体育館にて「第12回くらしきみなみ文化祭」が開催されました。会場では地域の方の力作が並ぶ作品展示コーナーや、科学実験、漫才など多くの方が楽しめる内容となっていました。
当院からはリハビリスタッフ5名、学習療法スタッフ1名、事務1名の計7名が参加しました。今回は特別に広島大学の田中亮先生にもご協力頂き、動作解析システムを用いた歩行年齢測定とInBodyという体成分分析装置を使用した体脂肪や筋肉量の測定を地域の方々に体験して頂きました。
歩行年齢測定はカメラに向かって歩いて頂き、速度・バランス・姿勢から年齢を出すものでした。日頃、自分の歩き方を測るという機会はなかなかないと思います。その珍しさもあるためか、多くの方に興味を持って体験をして頂くことができました。結果説明の際には、参加者の方が楽しみながらも真剣に話を聞いておられる姿が印象的でした。
 体脂肪、筋肉量の測定は体の部位別で行えます。その結果を参考に身体のどこを特に意識して運動をすれば良いか、などのアドバイスを個別にさせて頂きました。
体脂肪、筋肉量の測定は体の部位別で行えます。その結果を参考に身体のどこを特に意識して運動をすれば良いか、などのアドバイスを個別にさせて頂きました。
今回の企画を通じて、改めて地域の方々の健康や身体に関する関心の高さを感じることができました。またこの体験をきっかけに、身体のケアや運動することをより意識される方が増えると嬉しいです。運動は続けることが大事だと思いますが、1人ではなかなか続かないことも多いと思います。是非、家族や近所の方などと協力して一緒に身体を動かす機会を作ってみて下さい。
最後になりましたが、この度当院のコーナーにご参加頂いた皆様、くらしきみなみ文化祭運営スタッフの皆様、貴重な機会を頂きありがとうございました。

理学療法士 Y

 第2競技は綱引きです。といっても、本物の縄を引っ張ると尻もちをついたりして危ないので新聞紙を細長く切ったものを使用しました。向かい合った人と新聞紙を引っ張り合い、手に持っている新聞紙が長く残っていた方が勝ちなのですが、すごく短くなってしまった人もいて、意外に盛り上がりました。
第2競技は綱引きです。といっても、本物の縄を引っ張ると尻もちをついたりして危ないので新聞紙を細長く切ったものを使用しました。向かい合った人と新聞紙を引っ張り合い、手に持っている新聞紙が長く残っていた方が勝ちなのですが、すごく短くなってしまった人もいて、意外に盛り上がりました。
 先日、第18回倉敷チーム医療研究会に参加してきました。倉敷チーム医療研究会は、糖尿病をはじめとする生活習慣病の患者教育や治療に関わるスタッフを対象とした研修会です。今回の研究会のメインテーマは『うつ病と糖尿病』でした。研究会で学んだことについて簡単に報告させていただきます。
先日、第18回倉敷チーム医療研究会に参加してきました。倉敷チーム医療研究会は、糖尿病をはじめとする生活習慣病の患者教育や治療に関わるスタッフを対象とした研修会です。今回の研究会のメインテーマは『うつ病と糖尿病』でした。研究会で学んだことについて簡単に報告させていただきます。 恒例となりましたゆるキャラグランプリ2019で、今年は企業・その他部門185位(885pt)の成績を収めました!
恒例となりましたゆるキャラグランプリ2019で、今年は企業・その他部門185位(885pt)の成績を収めました!


 私はまだぽかぽかと暖かかった今年の4月に倉敷平成病院に入職いたしました。臨床検査技師の国家試験を2月に終え、すぐに卒業、そして就職と急激な環境の変化に戸惑うこともありました。しかし、同期や先輩方に助けていただきながら少しずつ仕事にも慣れていき、振り返ってみるとあっという間の半年だったように感じます。
私はまだぽかぽかと暖かかった今年の4月に倉敷平成病院に入職いたしました。臨床検査技師の国家試験を2月に終え、すぐに卒業、そして就職と急激な環境の変化に戸惑うこともありました。しかし、同期や先輩方に助けていただきながら少しずつ仕事にも慣れていき、振り返ってみるとあっという間の半年だったように感じます。 では、どうすればより良い検査が行えるかを考えた結果、私が患者様の立場だったらどうされたいだろう?と考えてみることも大切なのではないかと感じました。それから、患者様は今どのような体調だろうか?どうすれば痛みもなく検査を終えられるだろうか?と考えながら検査を行うことで、最近では「まったく痛くなかった!」や「もう終わったん?早かったわー!」などと言っていただけることも増え、患者様の目線に立って検査を行うことの大切さに気付かされました。
では、どうすればより良い検査が行えるかを考えた結果、私が患者様の立場だったらどうされたいだろう?と考えてみることも大切なのではないかと感じました。それから、患者様は今どのような体調だろうか?どうすれば痛みもなく検査を終えられるだろうか?と考えながら検査を行うことで、最近では「まったく痛くなかった!」や「もう終わったん?早かったわー!」などと言っていただけることも増え、患者様の目線に立って検査を行うことの大切さに気付かされました。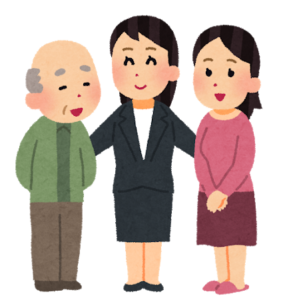 自然災害のみならず、突然の疾病や怪我によっても当たり前の日常生活が送れなくなります。
自然災害のみならず、突然の疾病や怪我によっても当たり前の日常生活が送れなくなります。 『おもてなしあしゆ』という足湯です!
『おもてなしあしゆ』という足湯です! 使用後は血液の循環が良くなり、実際に利用された方からは、「気持ちよかった」「足がぬくもった上に軽くなった!」「全身がぬくもったわぁ」という声をいただいています。
使用後は血液の循環が良くなり、実際に利用された方からは、「気持ちよかった」「足がぬくもった上に軽くなった!」「全身がぬくもったわぁ」という声をいただいています。 この足湯を体験してみたい、予防リハビリってどんなところ?と興味を持たれた方は、随時見学を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
この足湯を体験してみたい、予防リハビリってどんなところ?と興味を持たれた方は、随時見学を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。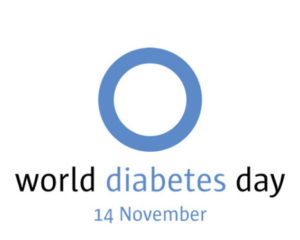 世界糖尿病デーは、世界に拡がる糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF(国際糖尿病連合)とWHO(世界保健機関)が制定し、2006年12月20日に国連総会において認定されました。11月14日は、インスリンを発見したカナダのバンティング博士の誕生日であり、糖尿病治療に画期的な発見に敬意を表し、この日を糖尿病デーとして顕彰しています。
世界糖尿病デーは、世界に拡がる糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF(国際糖尿病連合)とWHO(世界保健機関)が制定し、2006年12月20日に国連総会において認定されました。11月14日は、インスリンを発見したカナダのバンティング博士の誕生日であり、糖尿病治療に画期的な発見に敬意を表し、この日を糖尿病デーとして顕彰しています。