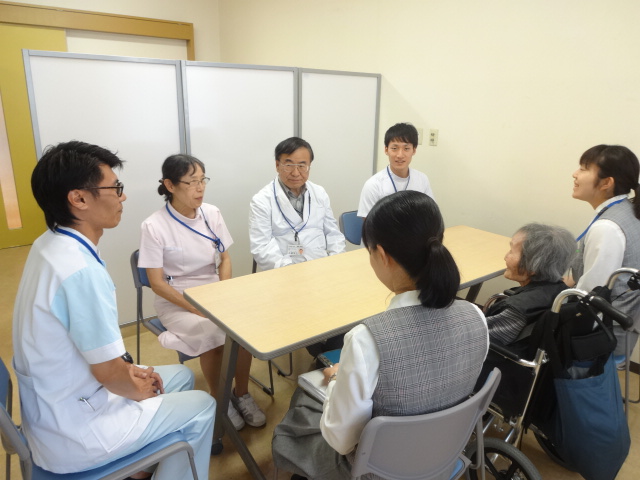令和元年5月15日(水)当通所リハビリを利用されているMさんが老松保育園のばら・すみれ組さん(年少)を対象にに絵本の読み聞かせボランティアを実施しました。新緑がまぶしい季節、晴天に恵まれ、園児たちがダンゴムシを見つけたと教えてくれたり、園庭を走ったり元気いっぱいの様子でした。
令和元年5月15日(水)当通所リハビリを利用されているMさんが老松保育園のばら・すみれ組さん(年少)を対象にに絵本の読み聞かせボランティアを実施しました。新緑がまぶしい季節、晴天に恵まれ、園児たちがダンゴムシを見つけたと教えてくれたり、園庭を走ったり元気いっぱいの様子でした。
 Mさんは『はじめまして』の大型絵本を読まれました。『はじめましてのごあいさつ。みんなはちゃんとできるかな。ねこくんもぞうさんもピアノさんもいすくんも…』と身近な動物たちがテンポよく挨拶してくれる内容に園児たちも集中しているようでした。
Mさんは『はじめまして』の大型絵本を読まれました。『はじめましてのごあいさつ。みんなはちゃんとできるかな。ねこくんもぞうさんもピアノさんもいすくんも…』と身近な動物たちがテンポよく挨拶してくれる内容に園児たちも集中しているようでした。
また、今回は職員による歌とリズムも披露し、歌に合わせて一緒に手拍子をしたりお膝をポンポンと叩く動きを取り入れたりして過ごしました。最後に園児より手作りの首飾りをプレゼントしていただき、今回は少人数だったので一人一人と握手をしてゆったりした時間を過ごしました。帰る際には、バイバイと手を振ってくださり、あどけない子どもたちに癒されました。感想をうかがうとM様は「本当にかわいいね。こんな頃があったんだねぇ。頑張って練習してよかったわぁ」とおっしゃっておられました。老松保育園の方々ありがとうございました。来月もよろしくお願いいたします
※令和元年度は5~9月まで月1回の計5回の開催を予定しています。
※了承を得て写真掲載しています。
通所リハビリ 介護士 M