日に日に気温が高くなり、日中は暑く感じることも多くなりました。朝晩はまだ肌寒いため体調管理にお気を付け下さい。
さて、最近はお口のホームケア用品がいろいろあり、歯ブラシ、歯磨剤、洗口液などの種類も豊富です。
その中でも今回は義歯洗浄剤についてお話ししたいと思います。
義歯洗浄剤も錠剤のものや泡タイプのものなど様々なものが販売されています。
義歯は水洗いだけではきれい見えても、カビの一種であるカンジダ菌が付着し義歯性の口内炎の原因になることがあります。義歯洗浄剤にはカンジダ菌を除去する成分が含まれているものが多いため、毎日ではなくても義歯洗浄剤で洗浄することをお勧めします。
また、バネが金属の部分義歯は『部分入れ歯用』をお選び下さい。部分入れ歯用の表示がないものを使用すると、金属部が変色することがあるためです。
特に注意が必要なのが、義歯を洗浄する時の水の温度です。熱湯を使用すると、義歯が変形してしまいますので、必ず水かぬるま湯をご使用下さい。
義歯の種類もいろいろあるため、どのような義歯洗浄剤が適しているのかご質問がありましたら、お気軽にお尋ね下さい。
歯科衛生士 まろ

 桜も徐々に咲き始め、私たち歯科の診療室から見える桜の木も綺麗なピンク色に色づいてきました。
桜も徐々に咲き始め、私たち歯科の診療室から見える桜の木も綺麗なピンク色に色づいてきました。 本日から3月ですね。まだまだ寒い日が続いておりますが、ブログをご覧の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
本日から3月ですね。まだまだ寒い日が続いておりますが、ブログをご覧の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。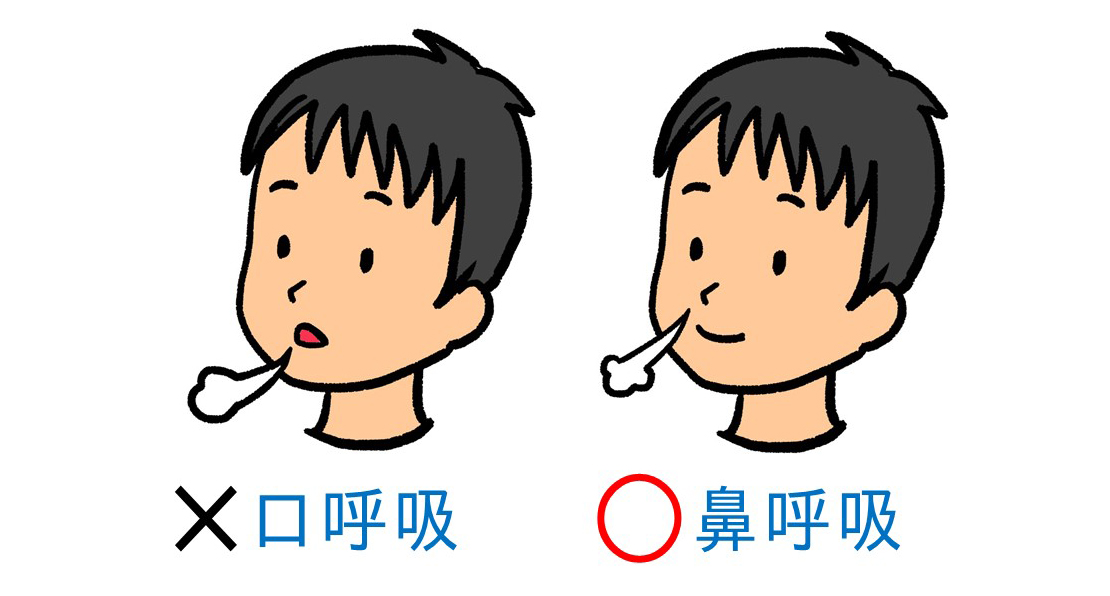
 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 いよいよ今年もあと2ヶ月となりました。
いよいよ今年もあと2ヶ月となりました。 オーラルフレイルの症状には、
オーラルフレイルの症状には、