この度、令和4年3月1日付けでマンモグラフィ検診施設画像認定を更新しました。
乳腺画像診断には適切に撮影されたマンモグラフィが必要になります。その画像の質を客観的に評価するためにマンモグラフィ検診施設画像認定という制度があります。この認定を取得するには、“撮影する装置”、“実際に撮影した画像”、“被ばく線量”等に細かい基準があり、すべてを満たしていなければなりません。その基準の中の“実際に撮影した画像”について、どのような点が評価されるのか簡単に紹介したいと思います。
まず実際に撮影された乳腺濃度の異なる4種類の画像(乳腺の割合が高いものから高濃度、不均一高濃度、乳腺散在、脂肪性)を提出します。これは乳腺濃度によって病気の見つけやすさがが変わるためです。
その各々の画像について、必要な撮影情報がもれなく表示されているか、適切なX線量かつ適切なポジショニングで撮影されているかということが細かい項目毎に点数化されます。
評価項目の例として、ポジショニングについては、左右対称であるか、乳房が真横を向いた状態であるか、圧迫されて乳腺がひろがっているか、乳腺がもれなく全体が入っているか、乳腺が奥まで入っているという証明として大胸筋が十分に入っているか、などがあります。
この評価項目をそれぞれ点数化して最終的にA~Dの評価が出されます。評価の合計が100点満点のうち76点以上のB評価以上で認定となります。また、施設認定は1回取得すれば終わりでなく3年で更新が必要になるので、適切なマンモグラフィが維持されるようになっています。
評価項目の例として挙げたポジショニングひとつとっても、撮影される方の体型が千差万別で同じ人であっても左右差があるので高評価の画像を撮影することは容易ではありません。が、できるだけ全ての項目をを満たすように心がけて毎回撮影をしています。
今後も適切なマンモグラフィを撮影できるように努力し、みなさんの検診に役立てるように精進していきたいと思います。
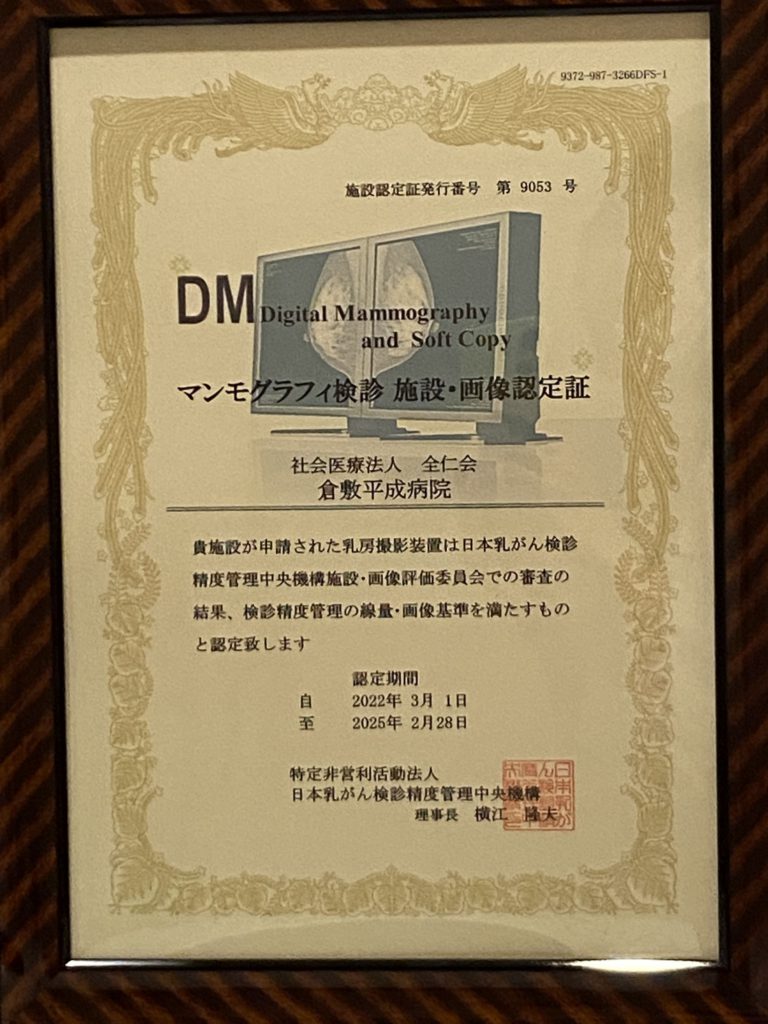
放射線部 TM

 最近テレビやドラマで取り上げられ、以前よりも放射線技師について知ってもらえるようになりました。
最近テレビやドラマで取り上げられ、以前よりも放射線技師について知ってもらえるようになりました。 この石灰化は心筋梗塞の発症リスクを予測する一つの因子となり、石灰化が多いほど、動脈硬化も多く、心筋梗塞を起こすリスクも高くなるという訳です。
この石灰化は心筋梗塞の発症リスクを予測する一つの因子となり、石灰化が多いほど、動脈硬化も多く、心筋梗塞を起こすリスクも高くなるという訳です。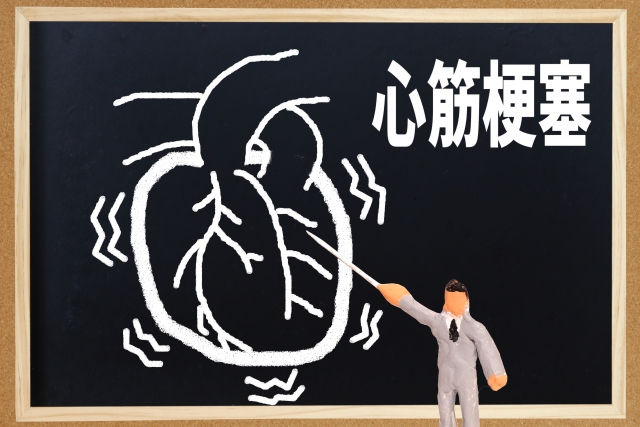 ここから、放射線技師なりの技術的なお話をします。
ここから、放射線技師なりの技術的なお話をします。 このところコロナウィルスの波も小康状態を保っており、岡山でも感染者ゼロの日が出てきています。クリスマスを控え、街も昨年に比べにぎやかなようです。ただ、新しい株の出現もあり、まだ収束までには時間がかかりそうです。
このところコロナウィルスの波も小康状態を保っており、岡山でも感染者ゼロの日が出てきています。クリスマスを控え、街も昨年に比べにぎやかなようです。ただ、新しい株の出現もあり、まだ収束までには時間がかかりそうです。 当院でも日本乳癌検診学会から出されている“乳がん検診にあたっての新型コロナウィルス感染症への対応の手引きVer.2.1”に則り、マンモグラフィに携わるスタッフにおいては
当院でも日本乳癌検診学会から出されている“乳がん検診にあたっての新型コロナウィルス感染症への対応の手引きVer.2.1”に則り、マンモグラフィに携わるスタッフにおいては ①起床・就寝時間を固定する
①起床・就寝時間を固定する
 9月になり、少しずつ涼しくなり過ごしやすい日も増えてきました。
9月になり、少しずつ涼しくなり過ごしやすい日も増えてきました。 2021.7下旬に電子カルテ更新に伴い放射線科情報システムRIS(Radiology Information System)の更新がありました。
2021.7下旬に電子カルテ更新に伴い放射線科情報システムRIS(Radiology Information System)の更新がありました。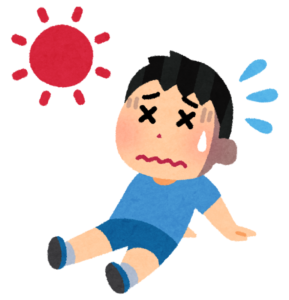 日を追うごとに暑くなりますが、皆様お元気で過ごされていますか。
日を追うごとに暑くなりますが、皆様お元気で過ごされていますか。