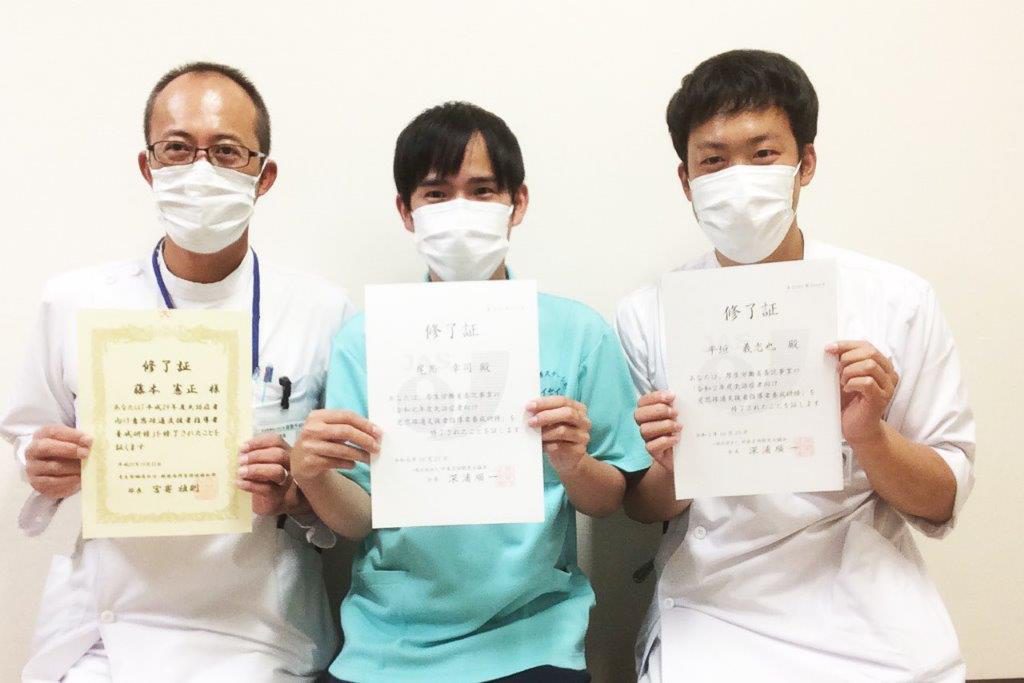皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
今年度入職致しました作業療法士(以下OT)のYと申します。まずは入職して2ヶ月経った現在の私の生活について話をします。
私はこの度、就職とともに倉敷市で1人暮らしを始めました。現在1人暮らしを始めて、気づき始めたことがあります。
それは両親と暮らしていた時に「当たり前」だと思っていたことが1人になると当たり前ではなかったことです。家に帰ったら食事が用意してあること、体調を崩したときに看病してくれること、洗濯・掃除をやってくれていることなど様々な当たり前だったことが、今は当たり前ではないため両親のありがたみが分かりました。まだまだ慣れる気はしませんが、これも良い人生経験だと思いながら頑張っていきます。手紙で両親に感謝の気持ちは伝えましたが、コロナ禍落ち着いた時には、両親を食事や旅行に招待して親孝行したいと思います。
さて、ここからはOTとして働き始めての話となります。現在、患者様にリハビリをさせて頂いたり、先輩方のリハビリを見学して患者様の症状や生活と向き合いながら奮闘している所です。患者様によって症状、痛みの程度、合併症、禁忌事項、介助量などが異なるため、分からないことや気をつけることなどは先輩方に相談に乗ってもらいながら頑張っています。
先輩方に教えてもらう度に、自身の技術や知識の乏しさを痛感しますが、担当させて頂いている患者様の現在・今後の生活をより良くするために、今後も文献を読んだり、勉強会に参加して自己研鑽していき、患者様に「リハビリを頑張ったから生活が良くなった」と思ってもらえるように日々精進していきます。 現在入職して間もないため、先輩方に教えてもらうことが当たり前のようになっていますが、この状況が当たり前ではないことを忘れず、1年後には先輩に頼ってばかりではなく自分で考えて行動できるような人になりたいと考えています。
現在入職して間もないため、先輩方に教えてもらうことが当たり前のようになっていますが、この状況が当たり前ではないことを忘れず、1年後には先輩に頼ってばかりではなく自分で考えて行動できるような人になりたいと考えています。
コロナ禍により、ストレスの溜まる日々が続きますが終息することを願って体調管理・感染対策をみんなで頑張っていきましょう。
OT Y

 みなさまこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
みなさまこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。 みなさんこんにちは。
みなさんこんにちは。




 新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。 私は、2回目の退院前訪問でしたが緊張と準備不足がないかと不安で一杯でした。現在は、チームの方々や先輩方のアドバイスをいただきながら退院後の生活を見据えて治療を進めています。リハビリを進めていく上で、知識不足と先輩方の幅広い着眼点を日々痛感しています。今回の退院前訪問や治療で学んだ1つ1つのことを吸収していき、日々精進し今後の治療に活かしていきたいです。
私は、2回目の退院前訪問でしたが緊張と準備不足がないかと不安で一杯でした。現在は、チームの方々や先輩方のアドバイスをいただきながら退院後の生活を見据えて治療を進めています。リハビリを進めていく上で、知識不足と先輩方の幅広い着眼点を日々痛感しています。今回の退院前訪問や治療で学んだ1つ1つのことを吸収していき、日々精進し今後の治療に活かしていきたいです。