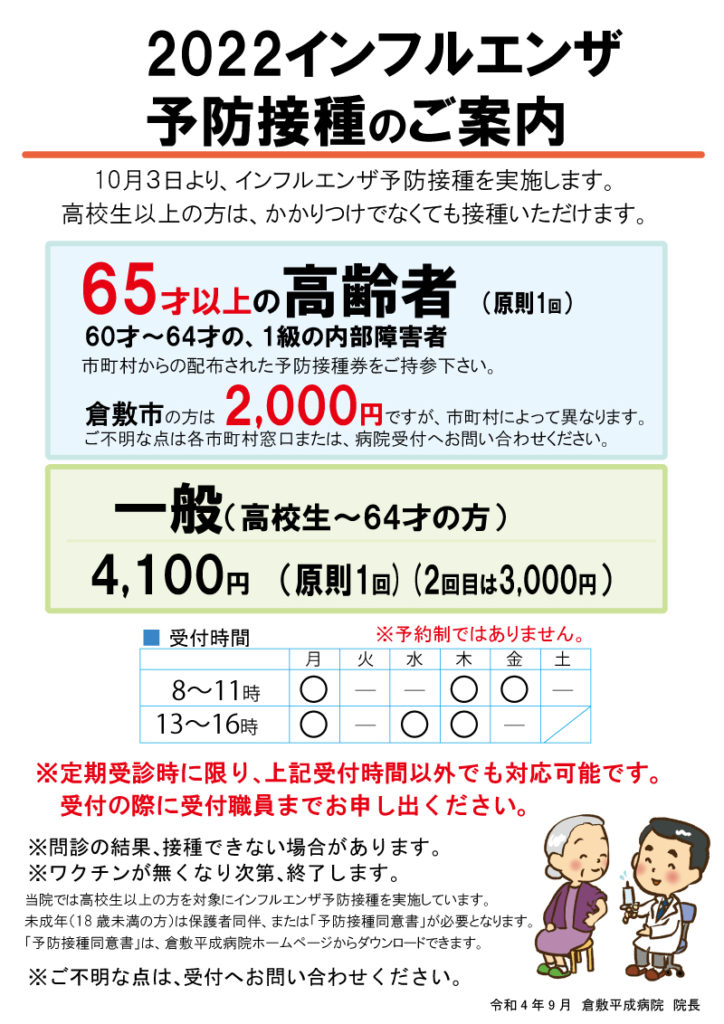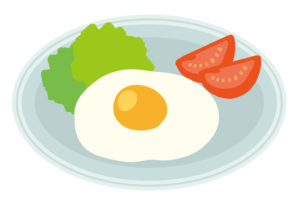 日本人の食事摂取基準では、1日に必要なタンパク質の量は、成人男性が65g、成人女性が50gとされています。1食あたりの摂取量としては、20gずつを目安に摂るのが理想的ですが、男性でも女性でも、また子どもから高齢者まで朝食でのタンパク質摂取量は低く、逆に夕食では高いと言うのが日常ではないでしょうか。タンパク質を3食均等にとっている人の方が筋肉の合成が盛んであり、夕食にタンパク質を多くとっていても朝が足りていないと筋肉維持に役立たないという研究結果も出ています。
日本人の食事摂取基準では、1日に必要なタンパク質の量は、成人男性が65g、成人女性が50gとされています。1食あたりの摂取量としては、20gずつを目安に摂るのが理想的ですが、男性でも女性でも、また子どもから高齢者まで朝食でのタンパク質摂取量は低く、逆に夕食では高いと言うのが日常ではないでしょうか。タンパク質を3食均等にとっている人の方が筋肉の合成が盛んであり、夕食にタンパク質を多くとっていても朝が足りていないと筋肉維持に役立たないという研究結果も出ています。
朝から十分な量のタンパク質を摂取すると、体内時計がリセットされて生活リズムが整い、やる気にあふれた1日を過ごせます。結果夜もよく眠れるようになるのです。子どもの場合は勉強のやる気が出るとか、高齢者だとサルコペニア、フレイルの予防になるとか、暴飲暴食を抑えられたり、糖尿病がよくなるといった効果も報告されています。以前は朝食さえ食べていればいいという考え方でしたが、これからは朝食にタンパク質が欠かせないということです。
年と共にタンパク質の消化吸収率が落ちること、タンパク質は食べ溜めができないので、年をとるほど若い頃よりもタンパク質の摂り方に気をつけなくてはいけません。起床後一時間以内に食べること、タンパク質だけでなく糖質も一緒に食べることが大切です。1食のタンパク質の目安は手のひらサイズ、肉、卵、魚など何でもいいです。毎日ちょっと早起きして朝食の時間を確保し、ご飯と納豆と味噌汁とか、パンと卵とサラダ、などタンパク質をとり入れた朝食をとってみてください。
栄養科 管理栄養士 A子

 10月に入り、あんなに暑かった夏が終わり、羽織り物や上着が欲しくなる季節になりました。皆様衣替えはもうお済みでしょうか?
10月に入り、あんなに暑かった夏が終わり、羽織り物や上着が欲しくなる季節になりました。皆様衣替えはもうお済みでしょうか?





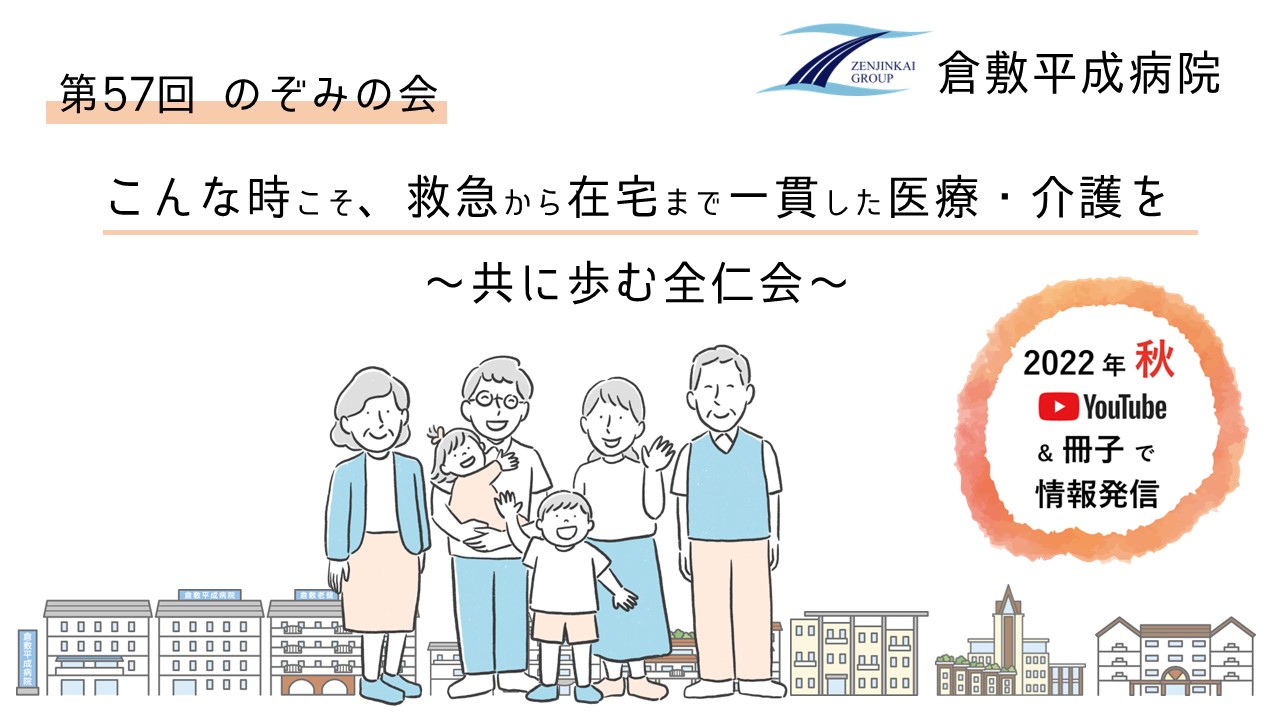 「第57回 のぞみの会」今年のテーマは
「第57回 のぞみの会」今年のテーマは 9月の連休を利用して、当院歯科の診察室をリニューアルしました。平成13年7月に当院に歯科が開設され、約21年が経ちます。改めて振り返ると20年以上経つのですね。
9月の連休を利用して、当院歯科の診察室をリニューアルしました。平成13年7月に当院に歯科が開設され、約21年が経ちます。改めて振り返ると20年以上経つのですね。

 皆さんは次のような症状はありませんか?
皆さんは次のような症状はありませんか?
 当施設の花壇は、ご入居の皆様の日々の「心のこもった管理」によって成り立っているのですが、朝夕の水やりなどは、その時期や気温なども考えながら実施されているそうです。
当施設の花壇は、ご入居の皆様の日々の「心のこもった管理」によって成り立っているのですが、朝夕の水やりなどは、その時期や気温なども考えながら実施されているそうです。