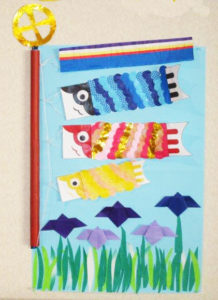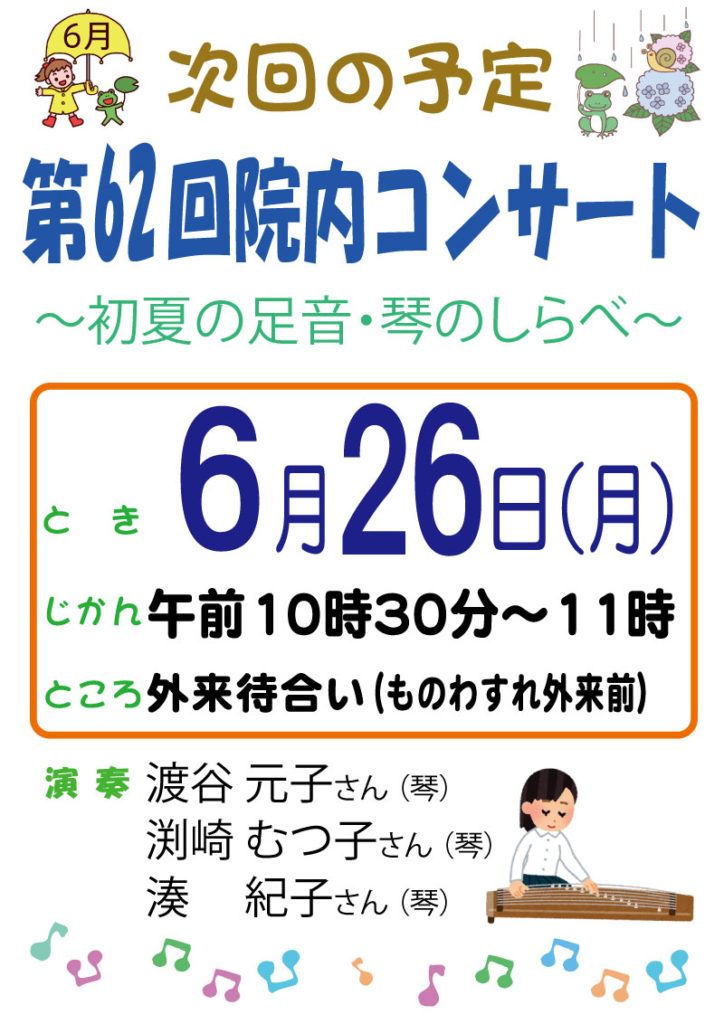皆さんは、「介護予防」のために、筋肉を意識して運動されていますか?
前回(2017年4月11日)、前々回(2017年3月9日)に、サルコペニアと筋肉の種類とトレーニングについて紹介をさせて頂きました。今回は、より効果的な筋力トレーニングの種類と頻度について紹介します。
「介護予防」のために、どこの筋肉を意識して運動するのがいいのでしょうか。
介護予防を目的とした筋力トレーニングは、65歳以上であれば、特に、食事・排泄・整容・移動・入浴等の能力や生活活動量と関連の深い筋や加齢による萎縮が著しい筋を中心に筋力トレーニングを実施することが重要であると考えられています。例えば、歩行能力の維持向上のためには、萎縮が生じやすい大腿四頭筋やヒラメ筋のトレーニングとして、スクワットなどを行い、起居移動作能力の維持向上や寝たきり予防のためには、体幹深部筋のトレーニングとして、深呼吸や背筋を伸ばした状態で座っておくことが有用といわれています。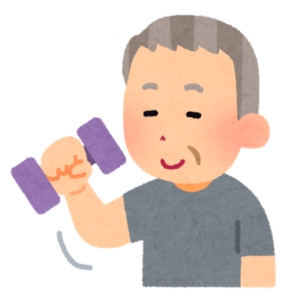
では、週に何回、筋力トレーニングを行うのがいいのかご存知でしょうか?
一般的には、週2~3回が適切な運動頻度であるとされています。その理由は、筋肉は運動によってダメージを受けると筋肉の線維が壊れ、その筋肉の線維が回復するためには、48時間必要といわれているからです。
いかがでしょうか。今回は「介護予防」のために、どこの筋肉を意識し、週に何回運動すればいいか、お伝えしましたが、当通所リハビリテーションでは、筋肉の線維の回復過程を重要視し、週2~3回のご利用をお勧めしています。楽しみながら運動が出来るようなプログラムを実施しているので、興味がある方は、いつでも見学にお越し下さい。
倉敷老健通所リハビリテーション 介護士 中山