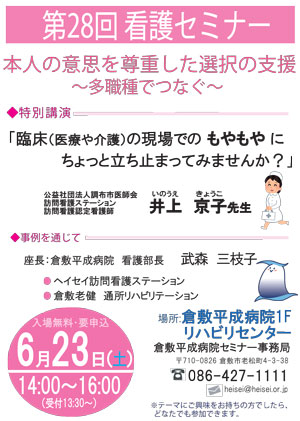今回は通所リハビリテーション 認知症ケア専門フロア(5フロア)の紹介を致します。
プログラムの工夫
当施設ではご利用者様がプログラムに集中し、安心して穏やかに過ごせるように、認知症ケア専門士や臨床心理士が中心となり専門性の高い対応や細やかな個別ケアを提供しています。ご利用者の集中力が切れるタイミングでプログラムが切り替えられるようスケジュールを調整しています。また、リラックス効果があると言われているアロマセラピーも取り入れています。
●来所直後は好きな活動に
午前中は、認知症の周辺症状の誘発要因にもなる不安やストレスの軽減を目的とし、個々に合わせてぬり絵、計算、手芸など行っています。個人のニーズに合ったプログラムが提供できるよう、ご本人やご家族から興味、関心、趣味、職業歴などの聴き取りが重要となります。そこで、個人個人の情報収集の為、ケアマネジャーや家族に協力して頂きプロフィールシートの作成を進めていきます。
●体操や歌で機能維持を
残存機能の活用、生活動作訓練を目的とした運動プログラムを行います。回想しながら行うと集中力が持続するため、なじみの歌を使用した体操DVDを活用しています。テンポの異なる曲を使用したり、こまめな声かけを行ったりして変化や刺激を加えることで飽きることなく集中して取り組むことができます。しっかりと運動に取り組んだ後は、認知機能訓練、声量維持、口腔状態維持を目的とし、歌を歌ったり、しりとりをして過ごします。ひらがなカードを使用し、単語の連想を行うミニゲームや文字パズル・絵合わせカードも良好な反応が得られます。
●自己紹介で関係作りを
ご利用者様全員が来所されるタイミングでRO(Reality Orientation)法を行います。事前に関係する土地の名物などの画像を用意しておくと話が盛り上がります。自己紹介をしていただきながら回想をすることで利用者間の交流を深め、利用者同士が“なじみの関係”となり安心して過ごせるように援助します。
●午後からはレクリエーションで楽しみを
昼食後は口腔ケア、リラクゼーション体操を行い身体を整えた後に身体機能訓練、認知機能訓練を目的としたレクリエーションを行います。音楽を使用しゲームを盛り上げたり、ゲームで使用する物品をご利用者様と作ることもレクリエーションとしています。ご利用者が青春時代流行った曲や思い出のある歌を選びカラオケも提供しています。スタッフの笑顔がご利用者様にも伝わるので、スタッフも楽しんで全員笑顔となるような内容を日々考えています。
●外に出てリフレッシュ
16時前後は帰りたくなる方が多くなるため、気分転換を目的に散歩をしたり畑に行ったりして外に出ることもあります。園芸では間引きや草花の名前、季節の野菜作りの手入れの仕方を教えて下っています。
また、収穫した野菜で何を料理するかと話が盛り上がり、活き活きした表情がうかがえます。
●当日のメンバーに合わせた工夫も
夕方はカルタなどの知的な遊びを行い、雑談を楽しみながら穏やかな時間を過ごして頂いています。知的な課題へ取り組むことが苦手な方が多い日は運動プログラムを多くするなどの工夫が必要となります。棒やボールを使用した集団体操を行っています。ご利用者様の体調に合わせ、無理強いすることなく前向きに取り組めるような声かけが重要となります。日常生活動作の訓練として、洗濯物を畳んでいただいたり、机を拭いていただいています。
3.在宅生活継続への支援・その他
●連絡ノートで家族支援
少人数対応とすることでご家族への支援も効果的となります。当施設ではご家族へご利用者様の利用中の様子を伝えるために始めた連絡ノートが、介護負担感の軽減と情報の共有で有用となっています。利用中のご様子を知って頂くとともに、ご家族の日頃抱えている介護に対する不安や疑問、ストレスを聞かせて頂き、アドバイスや情報提供を行います。ご家族との信頼関係が築けた頃には、交換ノートのように内容も明るくなり「読むのが楽しみ」「相談しやすい」という言葉をいただいています。
●病院との連携も
利用者様の多くは当法人内の認知症疾患医療センター/もの忘れ外来を受診しています。外来では臨床心理士がご本人への認知機能検査・ご家族への問診を行っており、当施設の臨床心理士を通じて主治医との連携を図りやすい環境にあります。受診前に通所リハビリでの様子や変化点について情報提供を行うことで、内服の変更や主治医からの助言に繋がることも多く、在宅生活を支える一助になっているのではないかと考えて取り組んでいます。
次回の通所リハビリテーションでは、2フロア(重度の介助が必要な方のフロア)のご紹介を致します。施設内の見学は随時承っていますので、お気軽にご連絡ください。皆様のご利用を心よりお待ちしています。
※許可を得て写真の掲載をしています
通所リハビリテーション 介護福祉士I






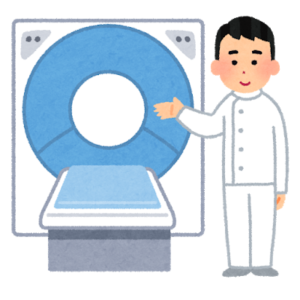
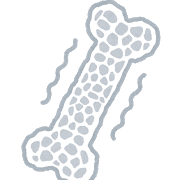
 余談ですが、「アヤメ」と「ショウブ」はどちらも漢字で書くと「菖蒲」なんですね。しかし、同じ漢字でも別物だそうです。「アヤメ」と「ショウブ」の違いについてはここでは省略いたしますが、さて、デイサービスに咲いている花は「アヤメ」でしょうか、「ショウブ」でしょうか?
余談ですが、「アヤメ」と「ショウブ」はどちらも漢字で書くと「菖蒲」なんですね。しかし、同じ漢字でも別物だそうです。「アヤメ」と「ショウブ」の違いについてはここでは省略いたしますが、さて、デイサービスに咲いている花は「アヤメ」でしょうか、「ショウブ」でしょうか? 続いて、園芸として、今年の夏はデイルームと訓練室の外にゴーヤのカーテンを作ろうと考えています。利用者さんと一緒にプランターに苗を植え、今はまだやっとツルが伸び始めたところです。
続いて、園芸として、今年の夏はデイルームと訓練室の外にゴーヤのカーテンを作ろうと考えています。利用者さんと一緒にプランターに苗を植え、今はまだやっとツルが伸び始めたところです。