12月に入り2022年もあとわずかとなりました。寒さが厳しくなり始めていますが、いかがお過ごしでしょうか。
皆さん、冬でもしっかり水分を摂取できていますか。蒸し暑い夏に比べ喉の渇きを感じにくく水分を積極的にとらない人も多いかと思います。ですが、乾燥する冬は体の水分が蒸発しやすいため脱水状態に陥りやすいのです。
成人の場合は体重の約60%、65歳以上の高齢者の場合は約50%を水分が占めています。尿や汗で体の外へ排出される水分と飲食によって体内へ入る水分のバランスがとれることで一定に保たれています。
水分を積極的にとらないことで知らず知らずのうちにバランスが崩れ自覚のないまま脱水状態へと移行してしまいます。
口の中が粘つく、つばが少ないなどの症状はもうすでに脱水の状態に陥っています。その状態を放置いると脱水症になり、頭痛・筋肉痛・胃もたれなどの症状が出てきます。
そして体内の水分が少なくなると血液が濃くなり血栓ができやすくなります。血栓ができると、脳梗塞、心筋梗塞などのリスクが高まります。入浴後や飲酒後、起床時は特に脱水が起こりやすいので要注意です。
防ぐためには、こまめな水分補給はもちろん加湿器の使用や洗濯物や濡らしたタオルを室内に干すなど、冬の乾燥対策も脱水を防ぐために効果的です。
こまめに水分、乾燥対策もして元気に過ごしましょう。
あなたのかかりつけ健康サイト サワイ健康推進課「冬こそ注意しよう! その不調、かくれ脱水かも!? 」 から引用
臨床検査部 Y.F

 日中も過ごしやすい気温になり、だんだんと秋めいてまいりました。皆様、季節の変わり目に体調を崩されてはいませんか?
日中も過ごしやすい気温になり、だんだんと秋めいてまいりました。皆様、季節の変わり目に体調を崩されてはいませんか?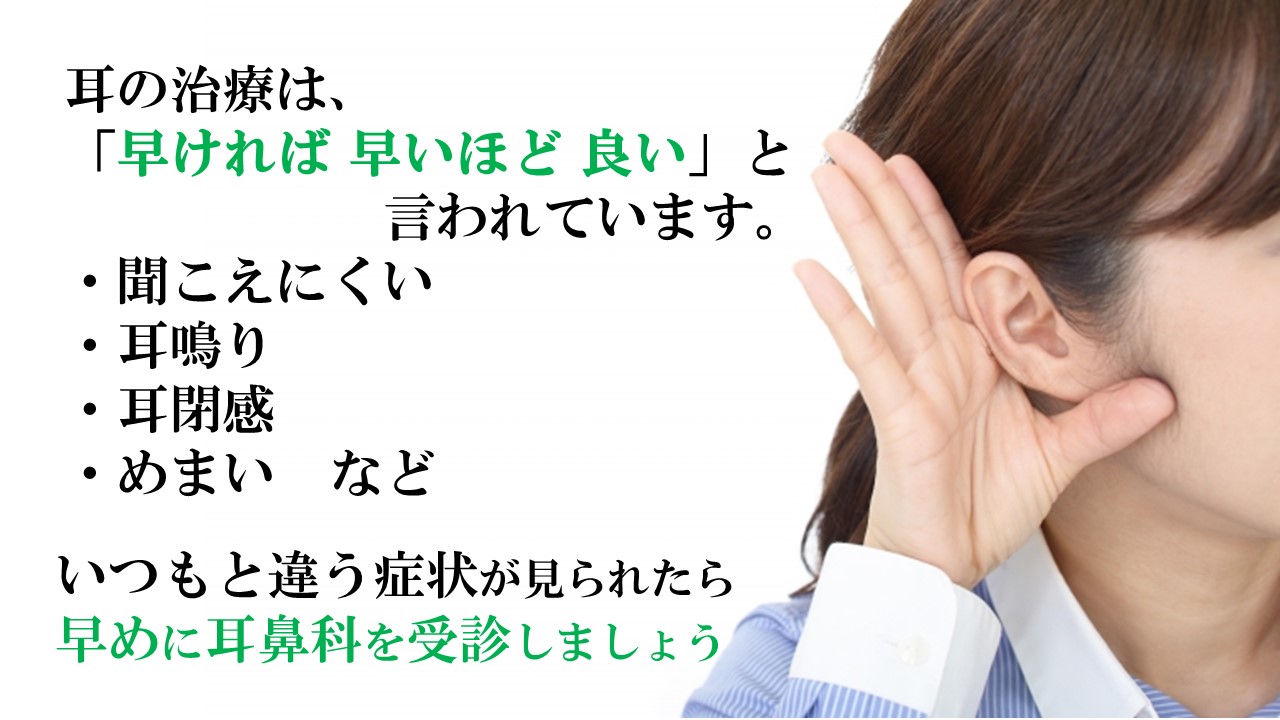 当院で実施している主な聴力検査
当院で実施している主な聴力検査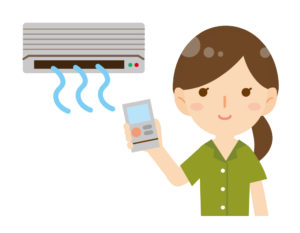 蒸し暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
蒸し暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?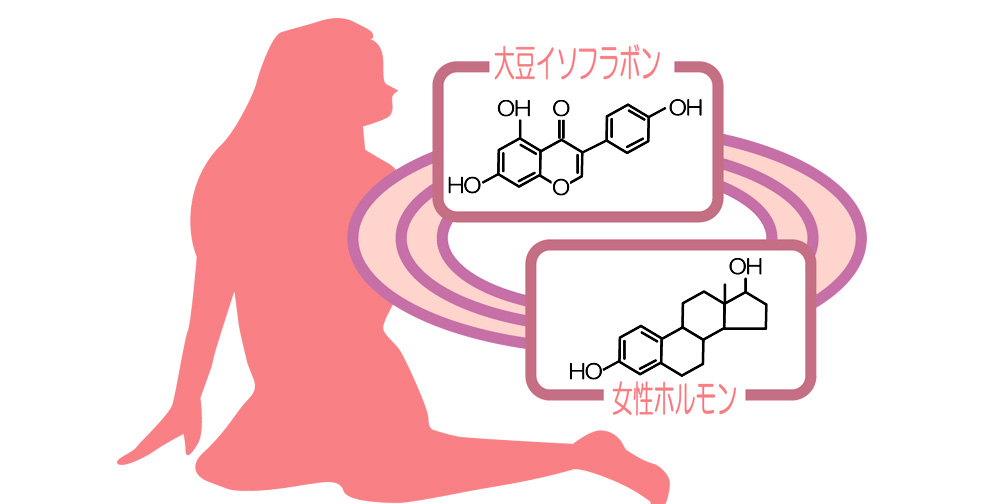


 では、それらをたくさん摂取して、あまり時間をあけずに、血液検査でカリウムを検査したらどうなるでしょう?個人差はありますが、食事で大量に摂取したことにより、血液中のカリウムが一時的に上昇し、異常値になってしまう可能性があるのです。一例では、朝食に野菜ジュースやバナナ、アボカドなどカリウムを2000mg(おおよそ一日量カリウム)摂取した後、採血を行い、血清カリウム値が6.0mmol/L(基準値3.6~4.8 mmol/L)の異常高値となった例が報告されています。
では、それらをたくさん摂取して、あまり時間をあけずに、血液検査でカリウムを検査したらどうなるでしょう?個人差はありますが、食事で大量に摂取したことにより、血液中のカリウムが一時的に上昇し、異常値になってしまう可能性があるのです。一例では、朝食に野菜ジュースやバナナ、アボカドなどカリウムを2000mg(おおよそ一日量カリウム)摂取した後、採血を行い、血清カリウム値が6.0mmol/L(基準値3.6~4.8 mmol/L)の異常高値となった例が報告されています。 春はお出かけの時、紫外線も気になってくる季節。女性はしみを気にして紫外線にあたらないようにする方は多いですよね。でも、紫外線、悪い面ばかりではありません。ビタミンD合成に重要となり、紫外線にあたることにより皮膚で合成、体内へ吸収されます。その他、ビタミンDは魚やきのこなどの食べ物の摂取によっても合成されます。体内に取り込まれたビタミンDは肝臓で25水酸化ビタミンDに変換されて、血液中を循環します。腎臓で活性型の1,25(OH)2Dへ代謝され、小腸、骨、副甲状腺などの標的臓器に作用することで血中カルシウム濃度の調整を行います。
春はお出かけの時、紫外線も気になってくる季節。女性はしみを気にして紫外線にあたらないようにする方は多いですよね。でも、紫外線、悪い面ばかりではありません。ビタミンD合成に重要となり、紫外線にあたることにより皮膚で合成、体内へ吸収されます。その他、ビタミンDは魚やきのこなどの食べ物の摂取によっても合成されます。体内に取り込まれたビタミンDは肝臓で25水酸化ビタミンDに変換されて、血液中を循環します。腎臓で活性型の1,25(OH)2Dへ代謝され、小腸、骨、副甲状腺などの標的臓器に作用することで血中カルシウム濃度の調整を行います。 花粉症の季節になりました。花粉症の症状がでている方もいらっしゃるかもしれません。
花粉症の季節になりました。花粉症の症状がでている方もいらっしゃるかもしれません。