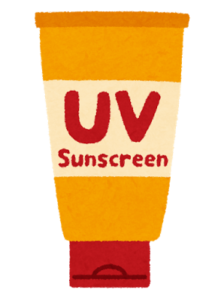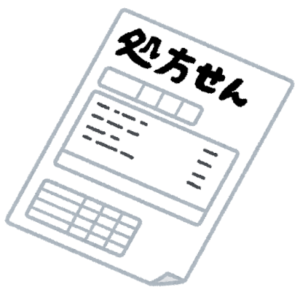吸入型インフルエンザ薬はイナビルとリレンザがありますが、当院ではイナビルが使用されています。
治療では10歳以上は1回40mg(2容器)、10歳以下は20mg(1容器)を単回投与で治療完了します。
予防目的では、治療と同じ単回投与と10歳以上は1回20mg(1容器)を2日間に分けて使用する方法があります。
予防効果は10日間あることが確認され、吸入当日から効果が発揮されます。
吸った瞬間咳込んでしまい、「容器の中の粉を吐き出してしまった!」「ちゃんと吸入できたかな?」と心配れる患者さんもいらっしゃいますが、目に見える白い粉は添加物(乳糖)で薬効成分は速やかに吸入され、容器の中身を半分吸入できていたら効果があるので大丈夫です。
ところで、インフルエンザの予防目的の場合、イナビルは誰でも簡単に処方してもらえるわけではありません。
イナビルを予防で使用することが認められるのは、原則としてインフルエンザ発症者と一緒に生活している方です。
また以下のような持病があり、インフルエンザ発症時の重症化などのリスクが高い方にも予防として処方されることが可能で す。
す。
・慢性呼吸器疾患または慢性心疾患がある方
・糖尿病などの代謝性疾患がある方
・腎機能障害がある方
・65歳以上の高齢者
ただし、イナビルを予防目的で使用する場合は保険診療としては適用されないため、全額自費になってしまうので注意してください。
益々寒さが厳しい季節となりますが、まずは、手洗い・うがいを基本にして、十分な睡眠、加湿、予防接種、人込みを避けるなどを意識しましょう。
薬剤師 F


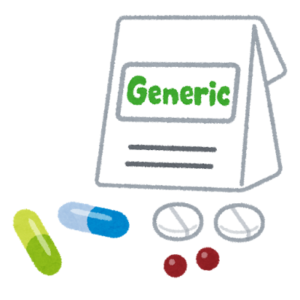
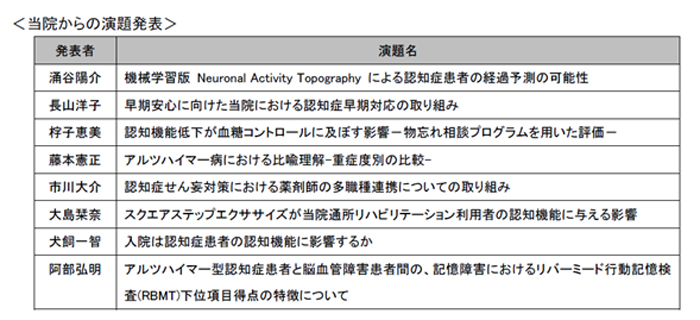

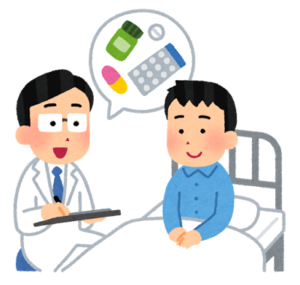 最近よく使われるようになった言葉で、「抗菌薬適正使用支援」などと訳されます。
最近よく使われるようになった言葉で、「抗菌薬適正使用支援」などと訳されます。