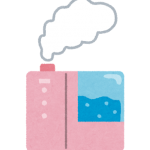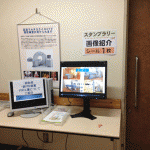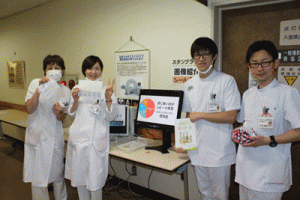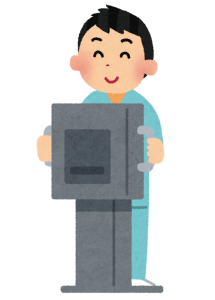早いもので、もう5月も中旬を迎えました。
早いもので、もう5月も中旬を迎えました。
毎年、6月になると、倉敷市でも市民対象の市主催の検診が始まります。
当院の放射線部では「胸部レントゲン検診」、「胃がん検診」と「マンモグラフィ検診」の受診が可能となっています。
この中で、今回、「胃がん検診」(バリウム検査)の内容について少し詳しくお話させて頂きます。
胃の検査と言えば、「げっぷ」を我慢しながら、美味しくないバリウムを飲まされ、右から左からとグルグル回転させられる、しんどい検査というイメージを浮かべる方がほとんどだと思います。
胃の検査においては、この「げっぷを我慢する」ということが非常に重要です。
検査前日からの絶飲食のために、胃は小さく縮んでいます。ここにそのままバリウムを流し込んでも胃の状態を正確に検査することは出来ません。
バリウムを飲む前に発泡剤という粉薬を飲んで頂くことにより、胃の中で空気を作り出します。これにより胃が適度な大きさに膨らみ、胃内部の粘膜の表面にバリウムが絡まりやすい状態が出来ます。ところが、胃が膨らむとお腹が張った状態になってしまうので「げっぷ」を出してしまいたくなります。しかし、ここで出してしまうと、せっかく膨らませた胃が、また前の検査しにくい状態に戻ってしまいます。
これが「げっぷ」を我慢して頂く理由です。かなりしんどいですが、正確な検査を行うためにも出来るだけ我慢してください。
検査時間は検査室入室から検査終了まででおおよそ15分程度です。
胃の健康状態を確かめるためにも、検診受診用のハガキが送られてきた方は出来るだけ受診をおすすめします。
放射線部 千