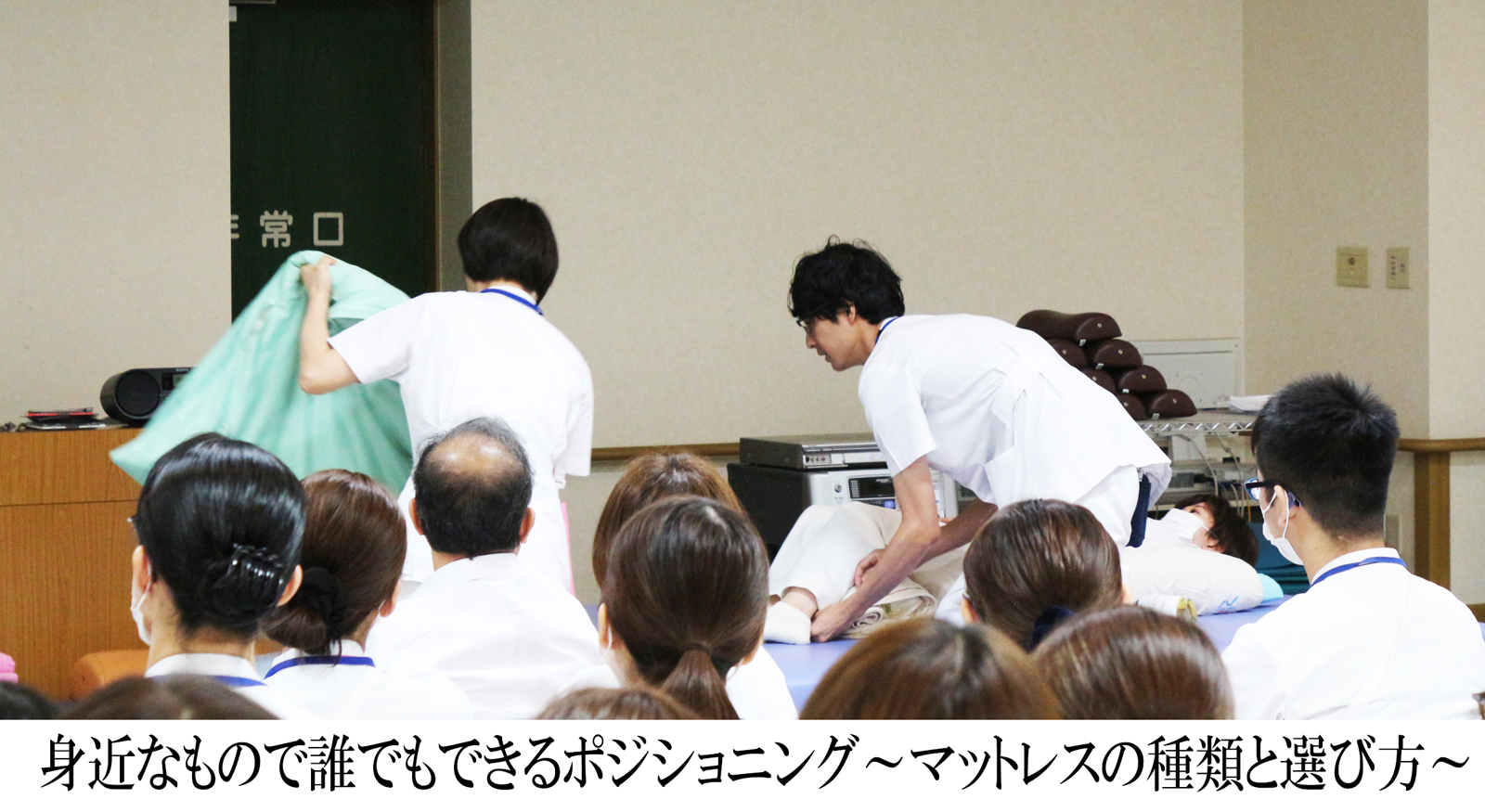10月21日(土)第36回神経セミナーが開催され、職員100名が参加しました。

 岡山大学脳神経内科 教授 石浦浩之先生を講師にお迎えし、「神経疾患の最新治療 片頭痛から難病、アルツハイマー病まで」をご講演いただきました。
岡山大学脳神経内科 教授 石浦浩之先生を講師にお迎えし、「神経疾患の最新治療 片頭痛から難病、アルツハイマー病まで」をご講演いただきました。
講演では、脳神経内科で診る多様な疾患について分かりやすくお話しくださいました。まず、アルツハイマー病やレビー小体型を始めとする認知症の臨床的な特徴・病理学的変化、そして9月に承認されたばかりのアルツハイマー病の抗体療法を含めた治療法についてお話しくださいました。
次に、多発性硬化症、重症筋無力症などの神経免疫疾患の抗体療法など、難病とされている疾患でも治療法に様々な選択肢があることをご教示下さいました。最後に、先生ご自身が脳神経内科を専門にされるきっかけとなった遺伝性疾患について具体例をご提示され、分かりやすくご説明くださいました。講演を通し、医療に携わる者として先生の医学に対する熱意に刺激を受けました。

セミナーの様子は、後日当院YouTubeにて動画配信いたします。
動画がアップされましたら改めてご案内いたします。
ぜひご視聴ください。
秘書・広報部




 今回は開催にあたり、感染対策にアクリル板の設置や約30名という極少数の参加の他、YouTubeにて動画配信(準備出来次第公開予定)での講演となりました。講師に国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長 櫻井孝先生をお迎えし、「認知症予防をはじめよう 本人・家族を中心とした認知症予防」をご講演いただきました。厚労省の発表では、2025年には700万人が認知症に、すなわち65歳以上の高齢者のうち5人に1人が罹患すると推算されており、認知症の予防や発症後の生活について国民の多くが関心を寄せているテーマであります。
今回は開催にあたり、感染対策にアクリル板の設置や約30名という極少数の参加の他、YouTubeにて動画配信(準備出来次第公開予定)での講演となりました。講師に国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長 櫻井孝先生をお迎えし、「認知症予防をはじめよう 本人・家族を中心とした認知症予防」をご講演いただきました。厚労省の発表では、2025年には700万人が認知症に、すなわち65歳以上の高齢者のうち5人に1人が罹患すると推算されており、認知症の予防や発症後の生活について国民の多くが関心を寄せているテーマであります。 認知症は世界的に、手厚い介入によって患者を支える様々な取り組みがなされており、先進国では認知症の有病率は減少傾向にあります。認知症の予防とは発症を止めることではなく、発症や進行を遅延させること。発症したとしても、共存できるように社会全体で取り組んでいくことが重要であると述べられました。
認知症は世界的に、手厚い介入によって患者を支える様々な取り組みがなされており、先進国では認知症の有病率は減少傾向にあります。認知症の予防とは発症を止めることではなく、発症や進行を遅延させること。発症したとしても、共存できるように社会全体で取り組んでいくことが重要であると述べられました。


 前半は倉敷生活習慣病センター診療部長の青山先生より、「糖尿病入院患者さんの治療の実際」についての講義が行われました。糖尿病治療は3本柱の食事療法・運動療法・薬物療法だけでなく、まずは飲水や点滴・経管栄養による水分量を確保すること、食事開始1時間後の運動が大切であるということを教えて頂きました。
前半は倉敷生活習慣病センター診療部長の青山先生より、「糖尿病入院患者さんの治療の実際」についての講義が行われました。糖尿病治療は3本柱の食事療法・運動療法・薬物療法だけでなく、まずは飲水や点滴・経管栄養による水分量を確保すること、食事開始1時間後の運動が大切であるということを教えて頂きました。 後半は、褥瘡認定管理栄養士でもある栄養科の小野主任より、「褥瘡と栄養の関係、退院後の効果的な栄養摂取方法」についての講義が行われました。褥瘡の段階によって必要な栄養素が異なるため、今の状態をよく観察し、何をどれだけ食べたかまで把握した上で栄養強化を行う事が大切であると学びました。
後半は、褥瘡認定管理栄養士でもある栄養科の小野主任より、「褥瘡と栄養の関係、退院後の効果的な栄養摂取方法」についての講義が行われました。褥瘡の段階によって必要な栄養素が異なるため、今の状態をよく観察し、何をどれだけ食べたかまで把握した上で栄養強化を行う事が大切であると学びました。
 近年医療界でも必要不可欠となっている倫理的配慮に関して学びを深めようと、「神経難病の臨床倫理について」をテーマに、10月19日(土)、第32回神経セミナーが開催され、340名が参加しました。中京大学法科大学院教授の稲葉一人先生を講師にお迎えし「臨床倫理的問題への対処法入門」と「神経難病をめぐる法と倫理」の2題をご講演いただきました。
近年医療界でも必要不可欠となっている倫理的配慮に関して学びを深めようと、「神経難病の臨床倫理について」をテーマに、10月19日(土)、第32回神経セミナーが開催され、340名が参加しました。中京大学法科大学院教授の稲葉一人先生を講師にお迎えし「臨床倫理的問題への対処法入門」と「神経難病をめぐる法と倫理」の2題をご講演いただきました。 神経難病における終末期の倫理的配慮は特に難しく、職種による価値観の相違や、医療従事者が患者さんにとって最適と考える事と、患者さんの求める事とに相違がある場合が実際の医療現場では起こりうること。そこで最適な判断を求められることの多い医師や看護師が負担や不安を一人で抱えこまないための倫理コンサルテーション・チームの必要性を提示されました。
神経難病における終末期の倫理的配慮は特に難しく、職種による価値観の相違や、医療従事者が患者さんにとって最適と考える事と、患者さんの求める事とに相違がある場合が実際の医療現場では起こりうること。そこで最適な判断を求められることの多い医師や看護師が負担や不安を一人で抱えこまないための倫理コンサルテーション・チームの必要性を提示されました。