子育てや教育・人材育成の現場において、最近では「叱らずに褒めましょう」という考え方が広まってきています。
ですが、「叱っちゃいけないのはわかるけど、でも結局叱らないと分からないし、伝わらない」
「叱っちゃダメなんていう人は現場のことを分かっていない。叱らずに済ますことなんて出来ない」とういのが本音ではないでしょうか?
少なくとも私はこの考えでした。現在の職場において後輩に対して叱って指導するような場面は今のところありませんが、我が子の子育てにおいては圧倒的にこの考えでした。
良くないことを何度も繰り返す我が子を目の前にして「何度注意しても直らないんだから叱ってでも教えていくしかない」「怒るじゃなく真剣に叱るということをすれば必ず子どもたちにも伝わるはずだし、これはこの子たちの将来のためだ」と考えていました。そんな私のやり方を見かねた妻からは「そんなに叱ったところでまったく伝わらないばかりか、委縮してしまうだけだから意味がない、むしろ褒めて教えていかないとダメ!」と逆に私が叱られる始末・・・。
実際、何度注意しても、叱っても全く変わらない状況に困り果てて、「叱っちゃダメというけどどうすればいいんだ!こんな状況で褒めるなんて無理!」と頭を抱えていました。
そんな時、ある本に出会いました。今回はこの本について少し紹介させていただきます。
「<叱る依存>が止まらない」というタイトルで、臨床心理士・公認心理士の資格を取得されている村中直人さんが執筆された本です。
この本では「叱る」が、脳・神経科学や心理学を中心とした科学的な視点から分析・解説されていました。
・「叱る」にはそんなに大した効果はない。
・少なくとも「叱る」による人の学びや成長を促進する効果は、世間一般に考えられているほどではない。
・「叱る」には、一見するととても「効果があるように感じるだけ」で、実は問題解決にはあまり役には立っていない。
その理由として、「叱る」行為は言葉を用いてネガティブな感情体験(恐怖、不安、苦痛、悲しみなど)を与えることで相手の行動や認識の変化を引き起こし、自分の思うようにコントロールしようとする行為である。叱られると「叱られた側」には強いネガティブ感情が生じてストレスを感じ、それに対して「何とかしてこの時間を早く終わらせたい」「どうしたら終わってもらえるか」といった「ネガティブ感情からの回避」を考えるようになる。
実はこれが「ごめんなさい、もうしません」「次からは気を付けます」という言葉として出てくる。この言葉により、叱る側は「分かってくれた、言っていることが伝わった」と感じる。つまり相手が「学んだ」と思い込んでしまう。
しかしながら、叱られる側のとった行動は単なるネガティブ感情からの逃避に過ぎないため、本来その場では何が求められていて、どう考えどう振る舞うべきなのかという「本当の意味での学び」にはなっていない。なのでまた同じことを繰り返す。
そして何度も叱られると「馴化」(慣れ)が生じ、叱る側からすると思ったような効果が得られないため、更に強く叱るようになる。これが繰り返され、叱ることでしか問題解決を図ることができなくなり<「叱る」依存>に陥る。
また、「怒る」と「叱る」は違うと言われているが、これらの言葉は「叱る側」のことしか考えておらず、「叱られる側」にしてみれば、怒られようが叱られようが、強いネガティブ感情が生じる点で大きな違いはない。つまりその違いは、叱る側の感情の違いに過ぎない。
というものでした。
(本書ではもっと多方面から詳しく科学的・理論的に述べられていますが、大まかにはこのようなニュアンスです。)
これを私が子ども達に叱っている場面に当てはめて考えると、「なるほど!今まで悩んでいた「叱る」という負のループに対してものすごくしっくりくる!こういうことだったのか!」と感心したと同時に「叱る」の間違った使い方に対する反省とそれによって悲しい気持ちにさせてしまっていた我が子への申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
本書では「叱る」を完全否定しているわけではなく、「叱る」ことと上手くつきあっていくための方法や徐々に手放していくための方法、「叱る依存」に陥らないための方法、また、叱られるすぎるとどのような悪影響があるのかなどについても理論的・科学的に書いてあり、私とってはすごく学びのある一冊になりました。
この本に出会ってからは、子供たちに「叱る」ことが無くなった・・・わけではありませんが、大分少なくはなりました。「叱らずに」子育てをやっていければ一番いいのですが、なかなかそうもいかず・・・。(汗)
それはさておき、この理論は職場での人材教育・育成においても大変参考になるのではないかとも思います。
「叱る」を手放す方法については勿論ですが、「叱ることで人材育成しようとする」ことの弊害や「叱る必要のない状態」を目指すための取り組み方についてなどは、業務上におけるリスク回避にもつながる有効な手段の一つとも考えられます。
もし興味を持たれた方がおられましたら、一度手に取って読んでみてはいかがでしょうか。
出典:村中 直人【著】,『“叱る依存”がとまらない』,紀伊國屋書店
放射線部 千

 この度、当院2階の歯科前にある飾り棚の中身を一新しました。
この度、当院2階の歯科前にある飾り棚の中身を一新しました。
 令和4年6月1日より特定施設入居者生活介護グランドガーデン(以下、特定施設)のご入居の定員が23名から46名となりました。元々3階を特定施設として令和2年より運営しておりましたが、この度2階も特定施設となりました。
令和4年6月1日より特定施設入居者生活介護グランドガーデン(以下、特定施設)のご入居の定員が23名から46名となりました。元々3階を特定施設として令和2年より運営しておりましたが、この度2階も特定施設となりました。 わりはないでしょうか。鍼灸院は変わらず元気でございます。パッと見て皆さんの体調が解れば、このような事を聞かなくて良いのですが…。という事で、今回のお話は見ただけで相手の状況が分かってしまう「神技」にしたいと思います。
わりはないでしょうか。鍼灸院は変わらず元気でございます。パッと見て皆さんの体調が解れば、このような事を聞かなくて良いのですが…。という事で、今回のお話は見ただけで相手の状況が分かってしまう「神技」にしたいと思います。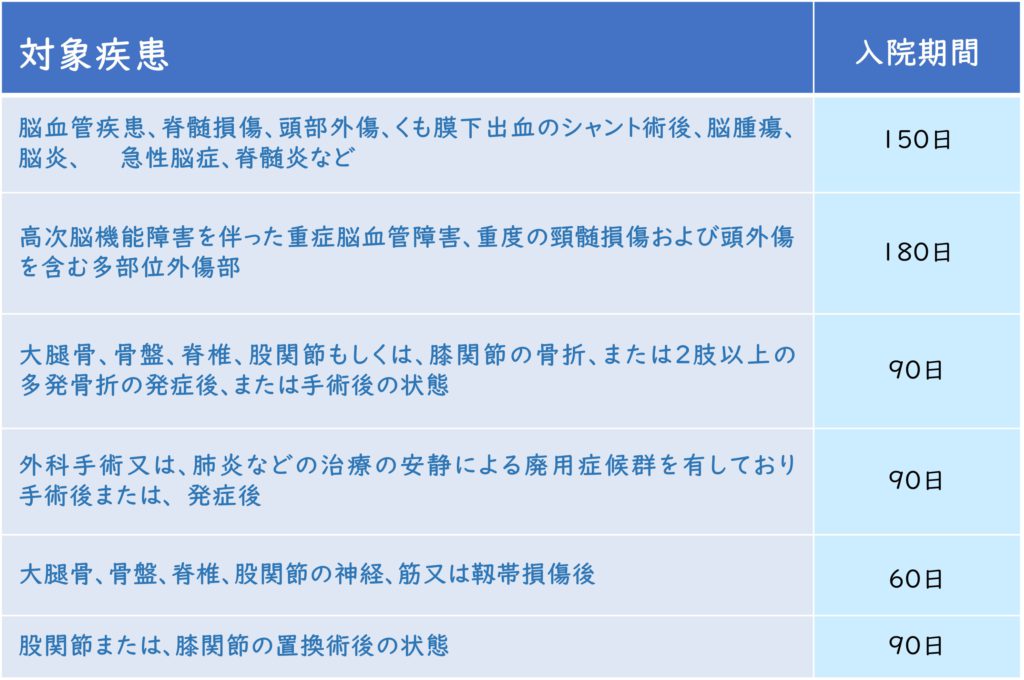
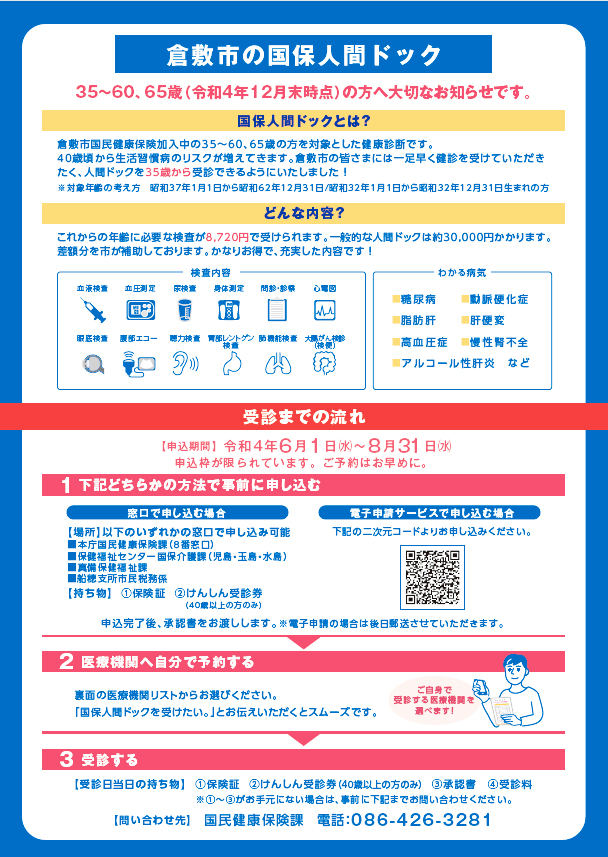
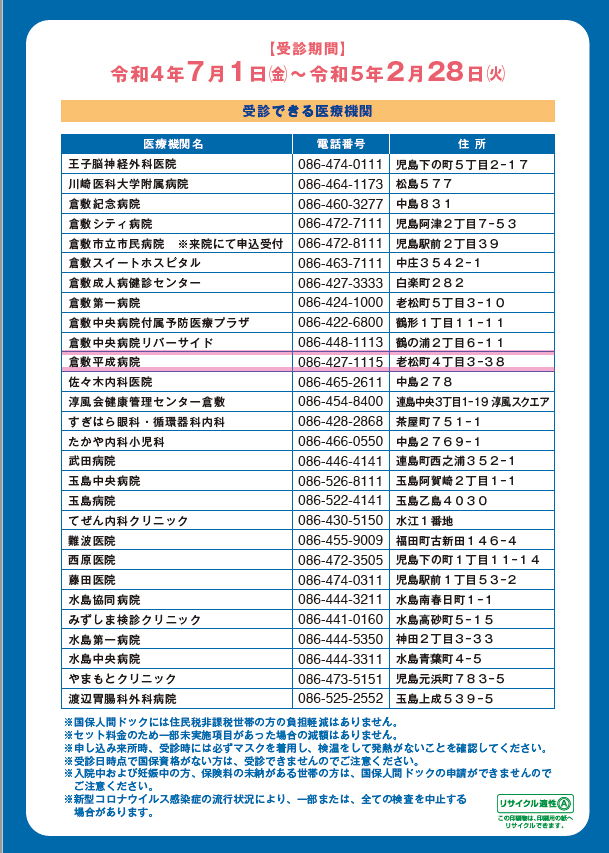
 こんにちは グループホームのぞみです
こんにちは グループホームのぞみです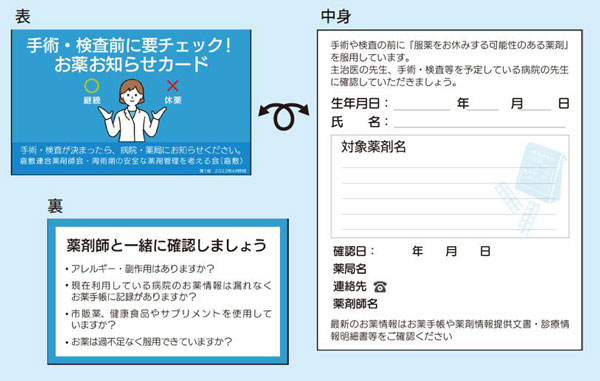

 平成14年6月に、生活習慣病(糖尿病)の予防から治療まで一貫した対応ができる部門として、開設された「倉敷生活習慣病センター」が20周年を迎えました。
平成14年6月に、生活習慣病(糖尿病)の予防から治療まで一貫した対応ができる部門として、開設された「倉敷生活習慣病センター」が20周年を迎えました。