年末年始は比較的天気にも恵まれ、初詣に行ったり、家族や親せきとのんびり過ごしたり、福袋を買いに並んだりなど、充実したお正月を過ごされた方も多いことと思います。久しぶりに会った家族や親せき、友達などと楽しく食事する機会も多く、「少し食べすぎたかな?」という方も少なくないのではないでしょうか。今回は、「冬場の生活習慣病対策」ということで、コレステロールの話題を取り上げました。「コレステロールは動脈硬化の原因になる」「LDL値は低いほうが良くて、HDL値が高いと良い」「卵は多く食べても脂質異常症にならない」などと、理解されている方も多いと思います。「脂質異常症」を放っておくと、動脈硬化が進んで脳卒中や心筋梗塞のリスクが高くなります。
コレステロールは主に肝臓で作られますが、体内で作られる量の1/3相当は食物から摂取されます。通常は、コレステロールを多く含む食事をとっても、作られるコレステロール量が減って、体内のコレステロール値は一定に保たれます。コレステロールには、どちらかというと悪いイメージがつきまといますが、細胞を合成する材料となり、体内で合成されるホルモンや胆汁酸の材料ともなる、人体にとっては必要な物質です。コレステロールは、そのままでは血液に溶け込むことができず、「LDL」という粒子になって、血液の流れに乗って全身に運ばれます。つまり、「LDLコレステロール(悪玉コレステロール)」は、組織に運ばれる途中のコレステロールで、高すぎると血管壁に取り込まれて動脈硬化が進みやすくなり、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの合併症を引き起こします。一方、余ったコレステロールは「HDLコレステロール(善玉コレステロール)」として肝臓に戻されます。ですので、「HDL」が高いと、余分なコレステロールが回収されるということで、この数値は高い方が良いということになります。コレステロールの一部は、肝臓で胆汁酸となって十二指腸に排出され、その多くは腸で再び吸収され、また肝臓に戻るという循環もしています。こうしたバランスが乱れると「脂質異常症」ということになります。
「家族性高コレステロール血症」という遺伝的に発病するものもありますが、多くは、食べすぎや運動不足、肥満、コレステロールの多い食事生活などが背景となっています。第一の治療方法は、バランスの取れた食事と適度な運動です。薬物治療も年々進歩しており、「メバロチン(一般名:プラバスタチン)」が発売された1989年以降から、スタチン系と呼ばれる「HMG-CoA還元酵素阻害剤」というコレステロール合成を抑える薬が多くの方に処方され、高脂血症の治療は飛躍的に進みました。この他にも、肝臓での中性脂肪産生を抑制する「フィブラート系」、小腸からのコレステロール吸収を抑える薬、ニコチン酸製剤、EPA製剤なども使用されています。最近では、「家族性高コレステロール血症」に著効する「PCSK9阻害剤」という注射薬も発売されました。「脂質異常症」のタイプに合わせた薬物治療が選択できるようになっています。
最後になりましたが、タバコはHDLコレステロールを下げ、LDLコレステロールを酸化させ、血管を収縮させて血流を悪くして動脈硬化を進めます。他にも発癌リスクなど、人体への悪影響も報告されています。脂質異常症を治療中の方はもちろん、その他の方も、平成30年の節目に禁煙を始めませんか。気軽に生活習慣病センターにご相談ください。
参考: アステラス製薬ホームページ「なるほど病気ガイド(脂質異常症(高脂血症))」
https://www.astellas.com/jp/health/healthcare/dyslipidemia/
薬剤部 いっちー
 アルツハイマー型認知症には、ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミンというコリンエステラーゼ阻害薬と呼ばれる薬と、メマンチンというNMDA受容体拮抗薬があります。
アルツハイマー型認知症には、ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミンというコリンエステラーゼ阻害薬と呼ばれる薬と、メマンチンというNMDA受容体拮抗薬があります。


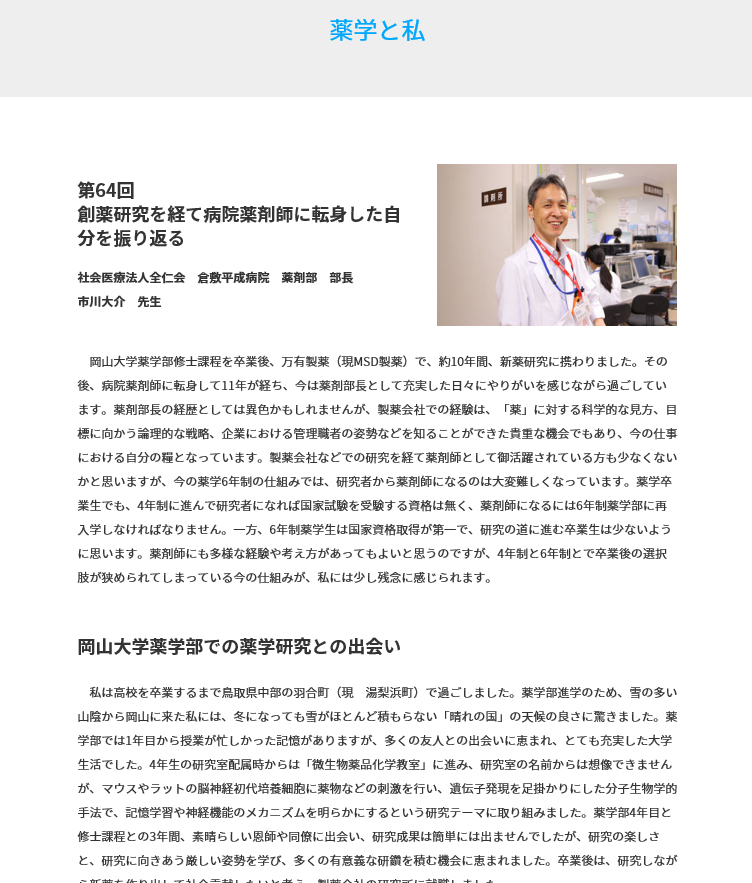


 注意点≫
注意点≫ 用するメリットとしては、
用するメリットとしては、 残薬あり」と回答した方・・・約33%
残薬あり」と回答した方・・・約33%